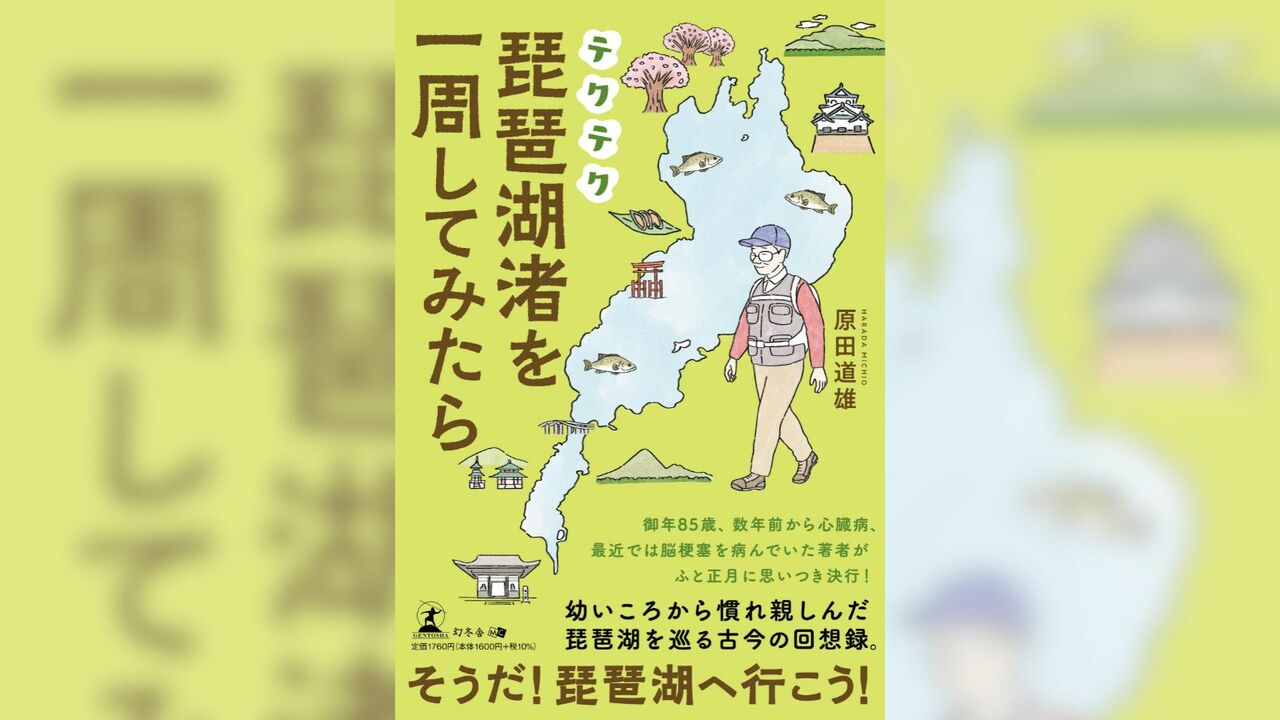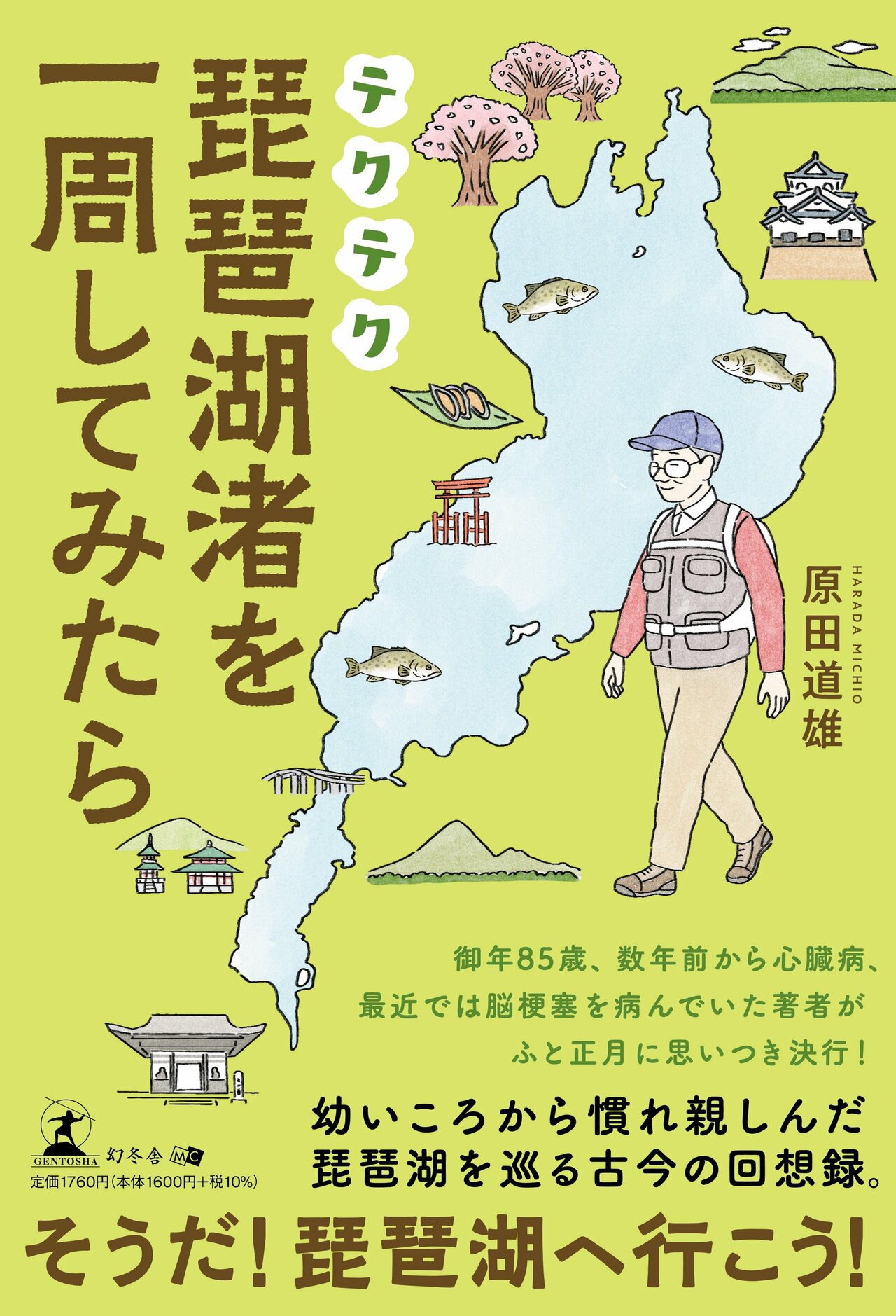【前回の記事を読む】心臓病&脳梗塞 経験あり85歳「琵琶湖一周は約240キロ。歩いてまわってみよう!」毎日コツコツ、その計画やいかに?
歩き旅1 1月4日(水) 1日目
大津市平津じた自宅――膳所本町
ある時一機の飛行機が急降下していくのが見えた。3―4キロ先の東レの工場のようだった。その後から、顔や手に包帯をグルグル巻きにされた人たちが近所の寺に運び込まれてきた。
案外近くに戦争があるのを知って少し怖かった。これは最近知ったのだが、その爆弾は原子爆弾と同じ形状、大きさで原爆の投下訓練であったらしいといわれている。そしてある夏の日、大事な放送があると知らされ、父にラジオの前に座らされた。暑い日の正午だった。
当時のラジオは聞き取り難く、言葉も難しかったのでよくは分からなかった。しかし〝耐え難きを耐え、忍び難きを忍び〟の言葉は聞いたような気がする。父の表情からも深刻な状況になった事は感じられた。
夜、親父が神棚に灯明をあげ子供を前に座らせて話をした。日本は戦争に負けて降伏したからどんな事が起こるかも知れないから覚悟をしろ、と云う様な内容だった。後で母親は子供たちにあんな言い方をするなんて…と言って強く批判していたが。母親は強しだ。
そうして戦争は終わり全てが急激に変わっていった。古い教科書は何か所かが墨で黒色に塗りつぶされた。そのあと新聞紙状のものが配られ、自分で折ったり切ったりして教科書として使っていた事もあった。
戦中戦後は食料品不足で小学校の校庭はサツマイモ畑となった。学校の横にはまだ水車もあった。それが小学校の思い出である。
そこから一時間ほど歩くと粟津中学がある。その湖岸寄りの緑地を歩く。ここまで行くと瀬田川は終わり琵琶湖になる。私が粟津中学に入学したのは戦後5年目(1950年)で6、3、3制の新制中学も出来たばかりでバラックのような校舎だった。
湖岸側は道路を建設すべく埋め立てが始まりその外は琵琶湖だった。中学の敷地の山手真横は、旧東海道、当時の国道一号線で昔ながらの松並木が残っていた。
粟津の地名は木曾義仲が討たれた地としても有名である(1184年、壇ノ浦の戦いの1年前)。近くには義仲に仕えた武将、今井兼平の塚もある。少しばかり先には義仲寺があって義仲の墓がある。が、私の中学の思い出はもっと他にある。
私は中学校時代野球部に入っていた。当時はまだ食糧難も続いていて、食料は乏しかった。野球部の練習は毎日遅くまであって冬場は暗くなってから電車に乗り終点から歩いて家に帰る。近所にもう一人野球部員がいて一緒だった。
帰り道の半ばぐらいに石山寺がある。腹が減ってバテた私たちは石山寺の石段に座ってしばし休むのだった。13、4歳の中学生なのに腹が減ってばてるのだ。その甲斐かどうかは分からぬが私たちの中学は結構強かった。