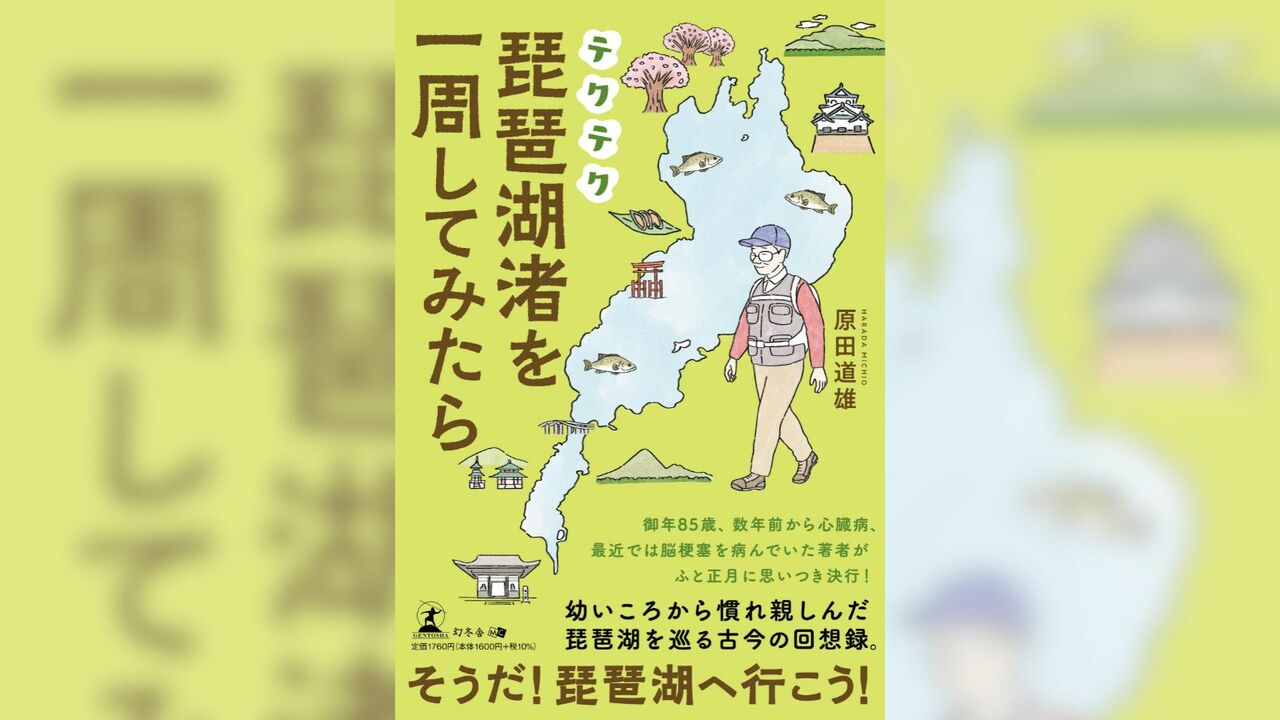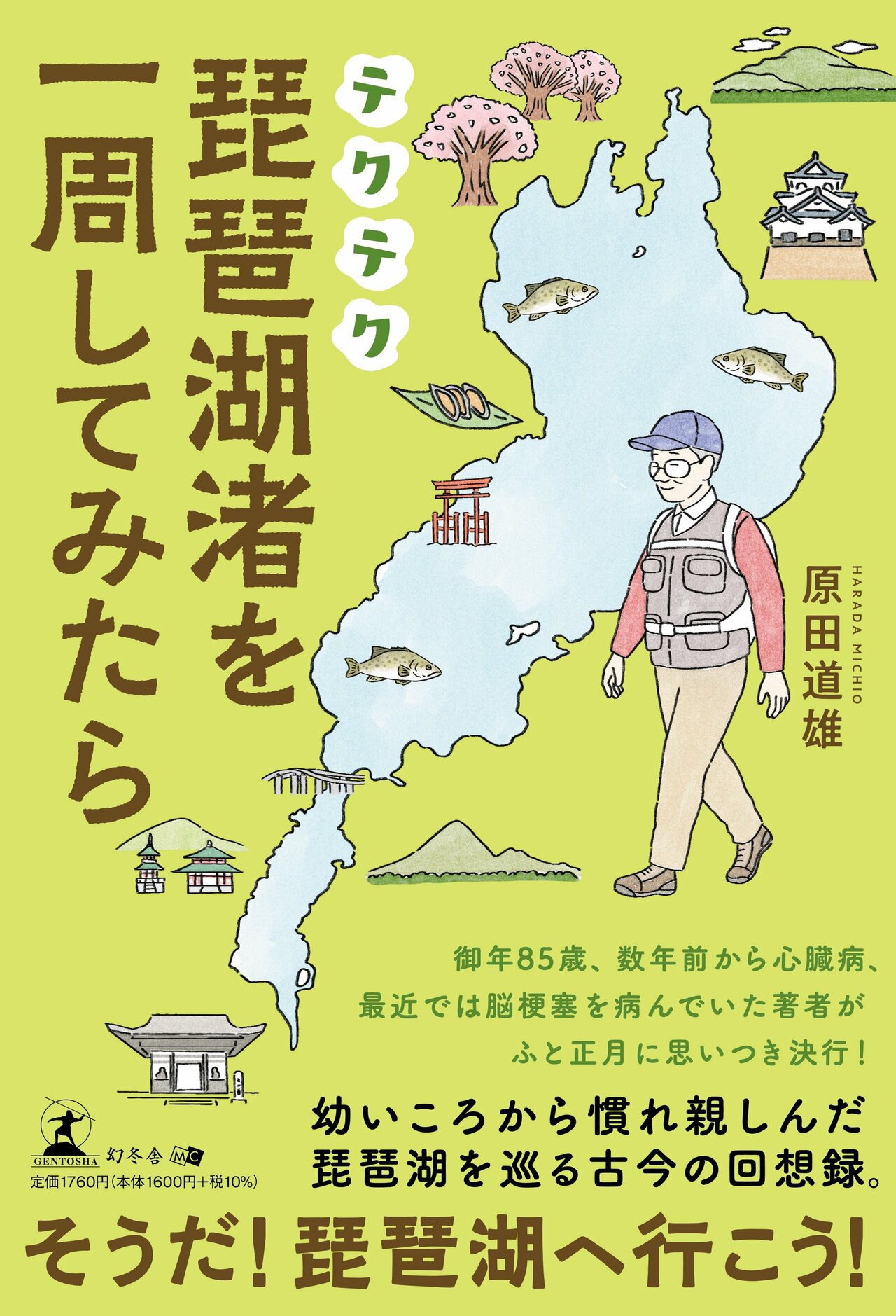【前回の記事を読む】昭和31年春、母校が甲子園に出場――私は応援団の太鼓を任され全力で叩き続けた
歩き旅2 1月7日(土) 2日目
膳所本町――大津市役所前
私は琵琶湖一周の歩き旅一日目の1月4日から瀬田川・琵琶湖のすぐそばを歩いて湖水を覗いて来た。今は最悪期に比べるとある程度水質は改善されて水中が見える。だがその結果がひどい。魚の泳ぐ姿が一匹も見えないのだ。
子供の頃、手作りの竿で小さな魚を釣った頃が懐かしまれる。琵琶湖は約400万年前にできた湖で、世界ではバイカル湖に次いで古いと云われている。
そのため固有種も多い。子供の頃は、必ずボテ(タナゴ)やハヤ(オイカワ)の姿は群れで見ることができたのに。水質は悪化しても、頑張れば富栄養化(ふえいようか)は元の状態に少しは戻すことはできる。
だが一度変化した生態系はどうにもならない。今や瀬田川や琵琶湖の南湖の魚は、ブラックバスとブルーギルがほとんどで、在来魚、特にボテやハヤはその姿がない。
戦後の発展の中で、琵琶湖は広大な範囲を埋め立てられ、その分湖岸はきれいに整備された。しかし湖水の富栄養化は進み、水面、水中、湖底は激変した。我々は今やその中に居る。文明の進歩は経済や諸々の設備を変え、人間の生活は昔に比べてはるかに豊かに便利になった様に思える。
だが経済発展や文明化を進める人たちに比べると、環境問題や自然保護を訴える人の声は小さい。昔に比べると、今はそのような学者の意見に耳を傾ける傾向も増えてきた。が、実際に生態系に変化が起きてしまったら元に戻しようがない。誰か賢い人が現れ、ブラックバスを無くし昔の生態系に戻すことができたら、それはノーベル賞ものだろう。
このあたりから大津にかけては学生時代の面影は一切ない。
先ず真横には近江大橋がかかった。
全長1300mの片側2車線の橋で昔は湖上を船で行き交いしていたのがあっという間に渡れる。最初は有料だったが10年前には無料となった。
昔は矢橋から大津への渡しがあって〝急がば回れ瀬田の唐橋〟の謂れの元となった。冬には季節風が強く吹き波立つこともあったのであろう。
近江大橋を北に向かうと埋め立て地に〝なぎさ公園〟という緑地ができ巨大な砂浜も作られた。その次には滋賀県で一番高いビル〝大津プリンスホテル〟がある。丹下健三氏の設計になる。その琵琶湖沿いには今は季節でないが芝桜の大きな花壇が続いていて、時期になると楽しむ人で賑わう。
膳所公園から大津方面に向かう一帯はまさしく大開発の跡地で、大きなホテルも二つ、その間にオペラハウスまである。
オペラハウスは発展開発の象徴だ。その内陸側、昔の湖岸線のあたりに義仲寺があってそこには木曾義仲の墓と並んで芭蕉の墓もある。