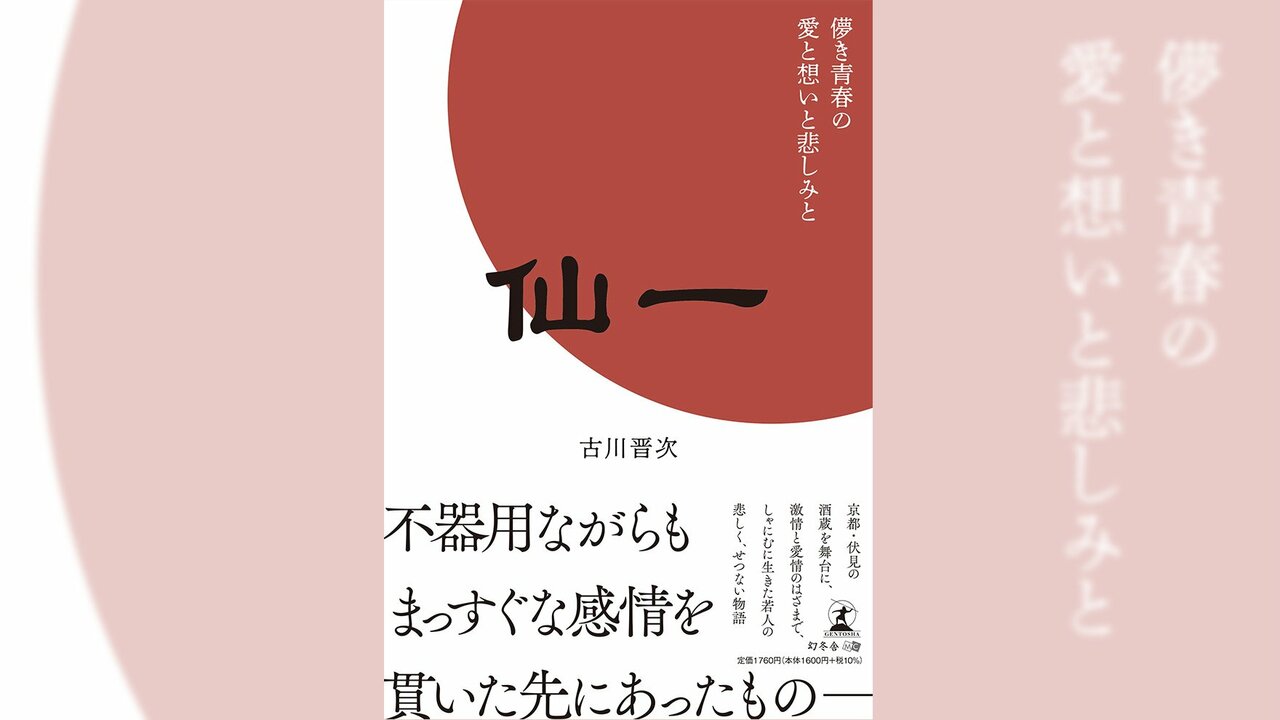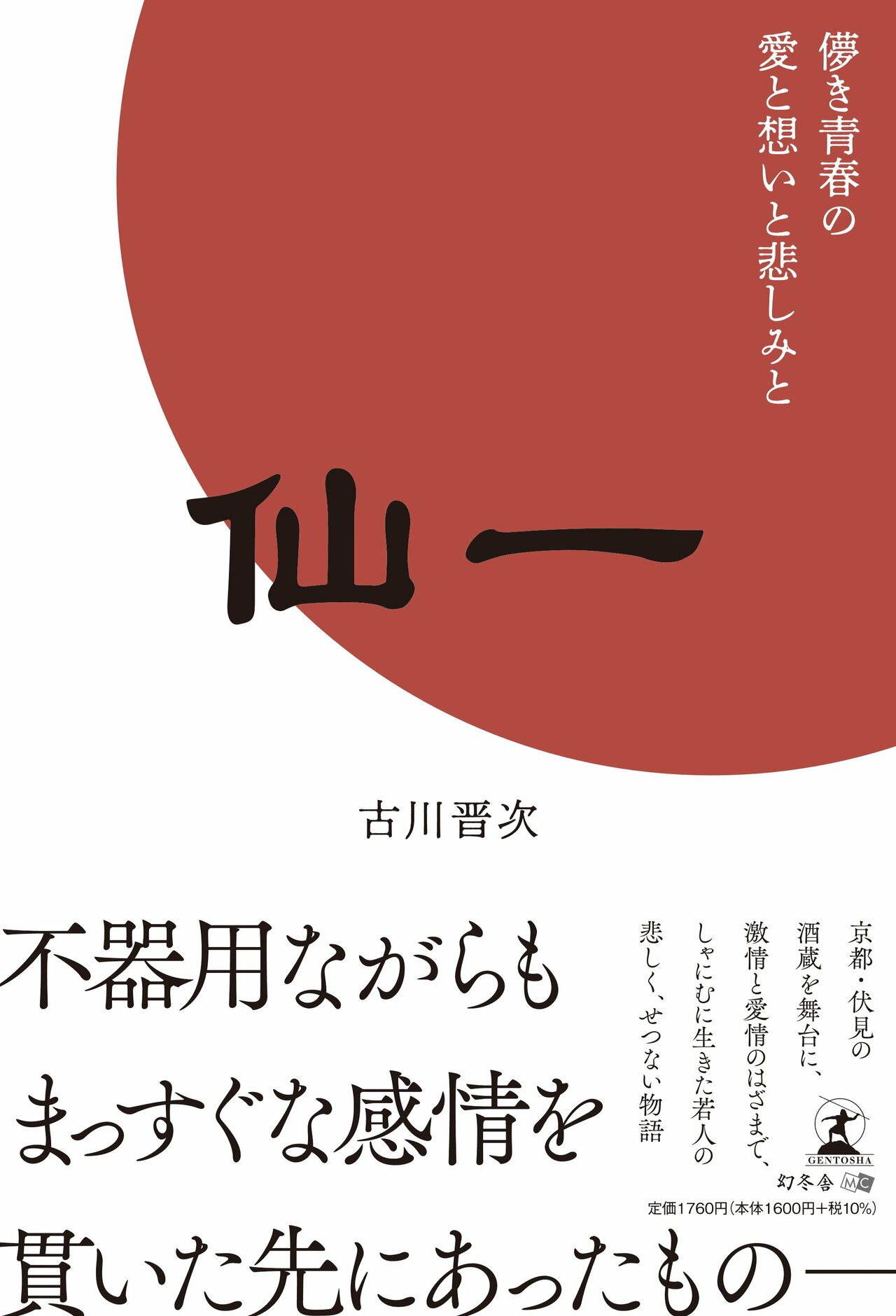【前回の記事を読む】「それなんぼや、わしが買うわ」…自分も欲しかったけど、先輩に先を越された。いつも先輩に譲る様にしている。諦めに似た感情で…
2.夜店の少女
まだあどけなさの残るその少女は、商店街の乾物屋の〝昆布屋〟の娘なのは仙一も前から知っていた。
近所の人達は、昔からその乾物屋の久世さんを、屋号では呼ばず代表の商品で〝昆布屋はん〟と親しみを込めて呼ぶ。
そういった呼び名の簡略化は、その辺りでは別に珍しくもない。
他にも、菓子屋が以前は下駄屋を営んでいた為、未だにその名残で〝下駄屋はん〟と呼ぶ。
又別の駄菓子屋も、ハンコ屋が前世だった為、駄菓子屋にも関わらず〝ハンコ屋はん〟と呼んだ。
子供達もみんな他に倣って、学校から下校して直ぐ、ランドセルを放り投げる様に置くと、母親に「ハンコ屋はんに行くさかい10円おくれ」と、親にその日の小遣いをセビって友達と待ち合わせて、駆け足でその〝ハンコ屋はん〟へ飛んで行くのが毎日の下校後の日課だった。
話は戻るがその少女、年の頃は13、14歳の可愛い子で、近所でも美人で評判の静かな少女。
髪型は、外国映画に出てくる主人公の様に髪を後ろに引きつめて、紺色セーターと合わせ、紺色のサテンのリボンをポニーテールに結び、白っぽいグレーのセミフレアスカート。
小柄で色の白いすらっとした、子供からやっと少女になったばかりの幼い表情の残る可憐な娘だった。仙一は、その女の子が他の数人の子供の間から自分を見ているのに、気づかないふりをして飴細工を見る事に集中した。
誰が注文をしたのか、早くも飴細工のおじさんが作るのは象の後のキリンだった。木の棒に取り付けた黄色く練った熱々の飴をハサミと手を使って器用に細工が進む。
最後に筆で、薄い茶色を配してあっという間の完成である。一夫が買った猿の木登りは、すでに棒には跡形もなく、内頬に出っ張って動いていた。