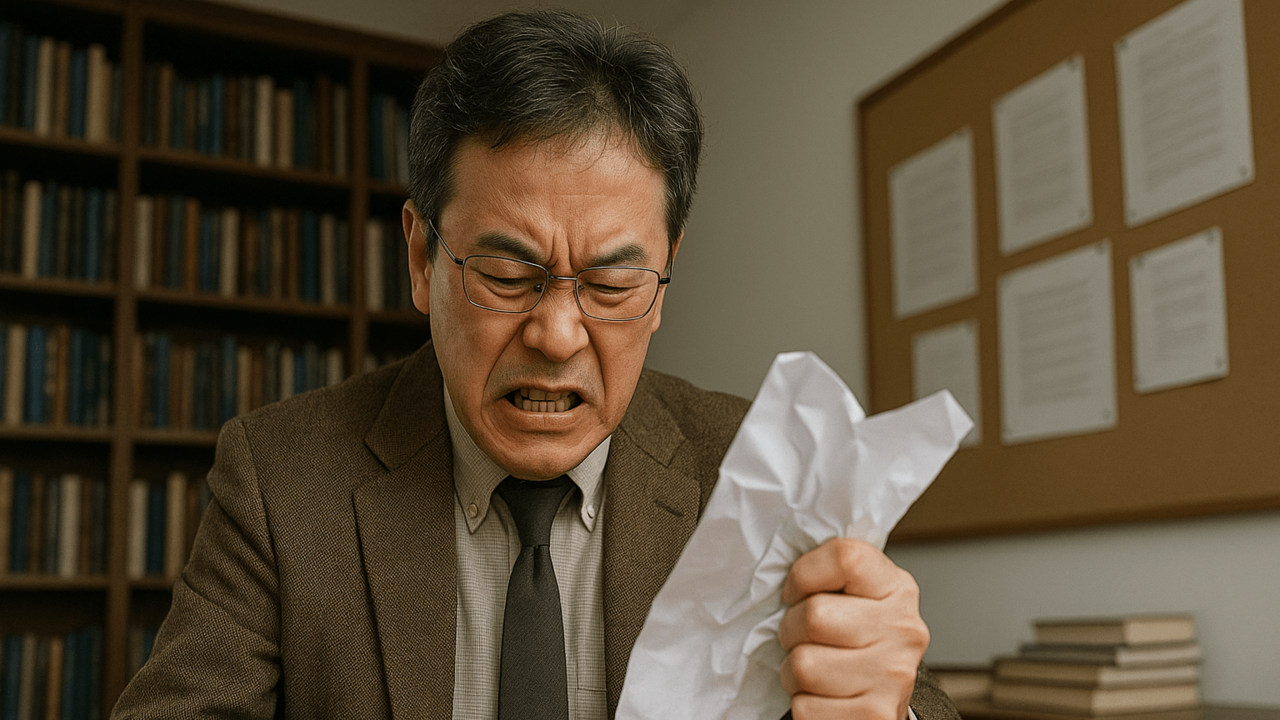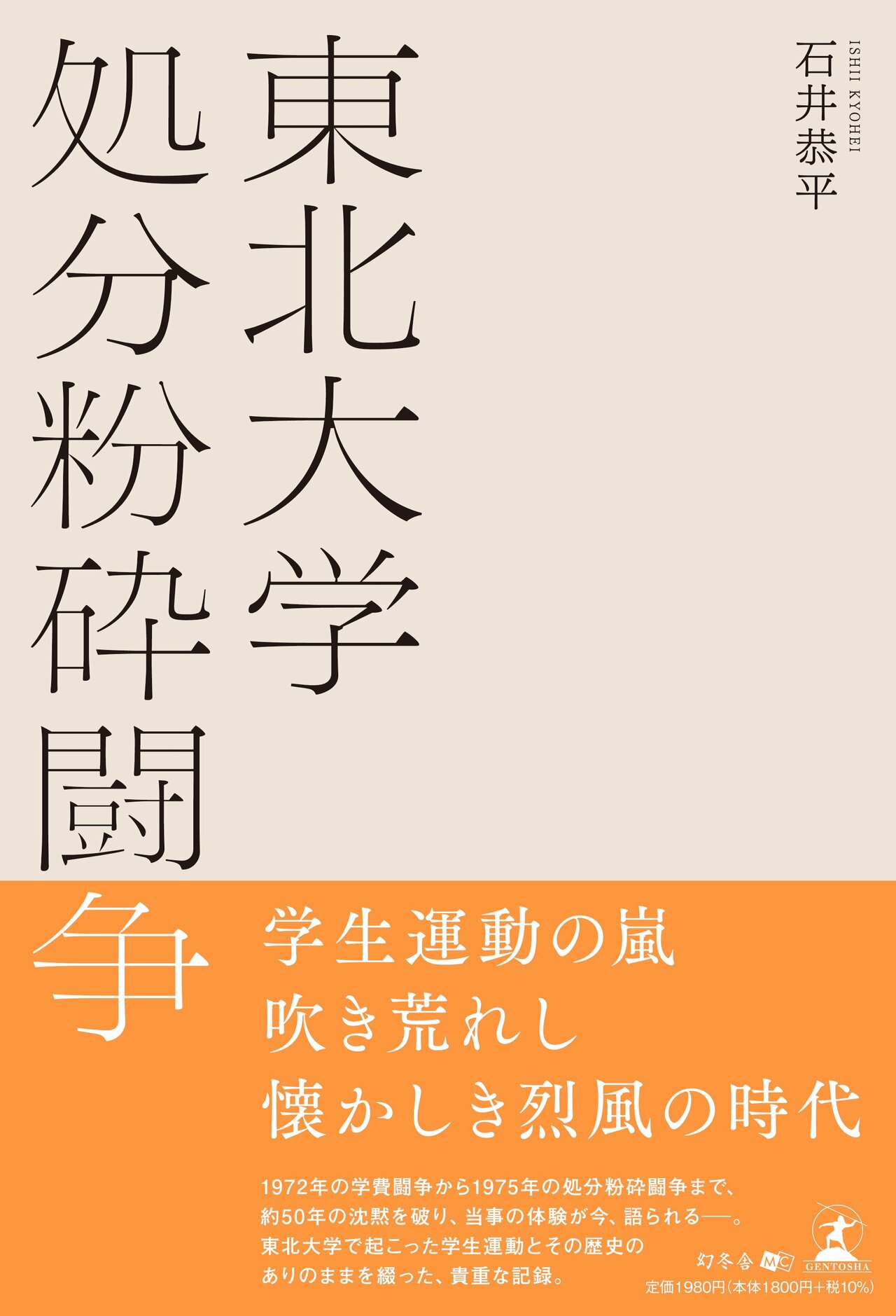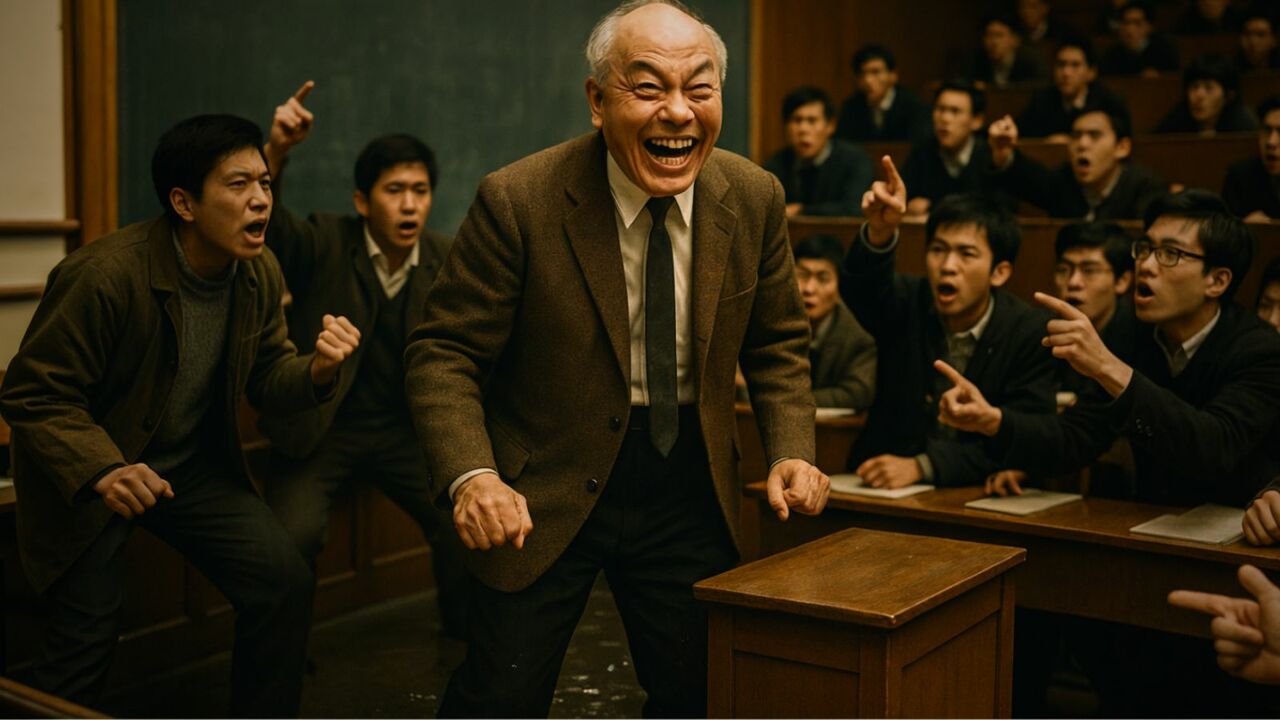【前回記事を読む】「学生1500名が留年」この学費闘争における大量留年のときに秘密裏に行われた教授会…審議に要した時間はわずか15分だった。
その1 始まり
7・30逃亡教養部教授会から8・20政治処分まで
8月11日、被処分者一同が全学教職員向けに、処分の不当性を批判する声明を発表した。8月13日、被処分者一同が高橋教養部長への直接会見申し入れ書を学生生活掛へ提出した。この中で被処分者からは、次の2点の不当性が指摘された。
①処分がすでに決定されてからの異議申し立ての通知であること
②異議申し立てが文書形態であること
この2点は、その後の処分粉砕闘争でもこの処分の手続き上の不当性として問題になっていく。というのも、処分に当たっては、
①当事者の異議申し立てを認めること
②文書ではなく、対面での異議申し立てを行う
この2点は、重要な最低限の手続きだったからである。これがないと、被処分者の異議申立書(後述、39~46頁)でも指摘されるように、学生の将来の影響への重大性にもかかわらず、事実誤認のままに処分することになる。
ましてや、大学当局の主張するように「教育的処分」であるならば、被処分者の学生の申し開きを聞いて、納得させて処分することが必要である。ところが、高橋教養部長は、被処分者との直接会見を拒否した。
学生生活掛が被処分者に口頭で「(高橋教養部長は)会えない。8・4文書の指示した方法に従いなさい。提出しなければ、異議申し立ての意志はないと判断する」と通告してきた。
そこで、被処分者は、やむを得ず
①会見要望書
②被処分者一同意見表明
③異議申立書
を大学当局に送付した。
しかし、これも後で暴露されることになるのだが、この被処分者が提出した「異議申立書」は、教養部教授会の場で吟味されることはなかった。というのも、この処分を画策した「拡大連絡会議」の段階で、どこにも提出されずに握りつぶされてしまったからである。
次に学生処分のための学内的手続きとしては、教養部からの提案により、全学評議会で処分が最終的に決定されることになる。8月20日、全学評議会が、この処分問題で朝10時より始まり、13時間も審議が続いた。何人かの学部の評議員よりの反論もあったが、最終的には、教養部の処分案が承認された。