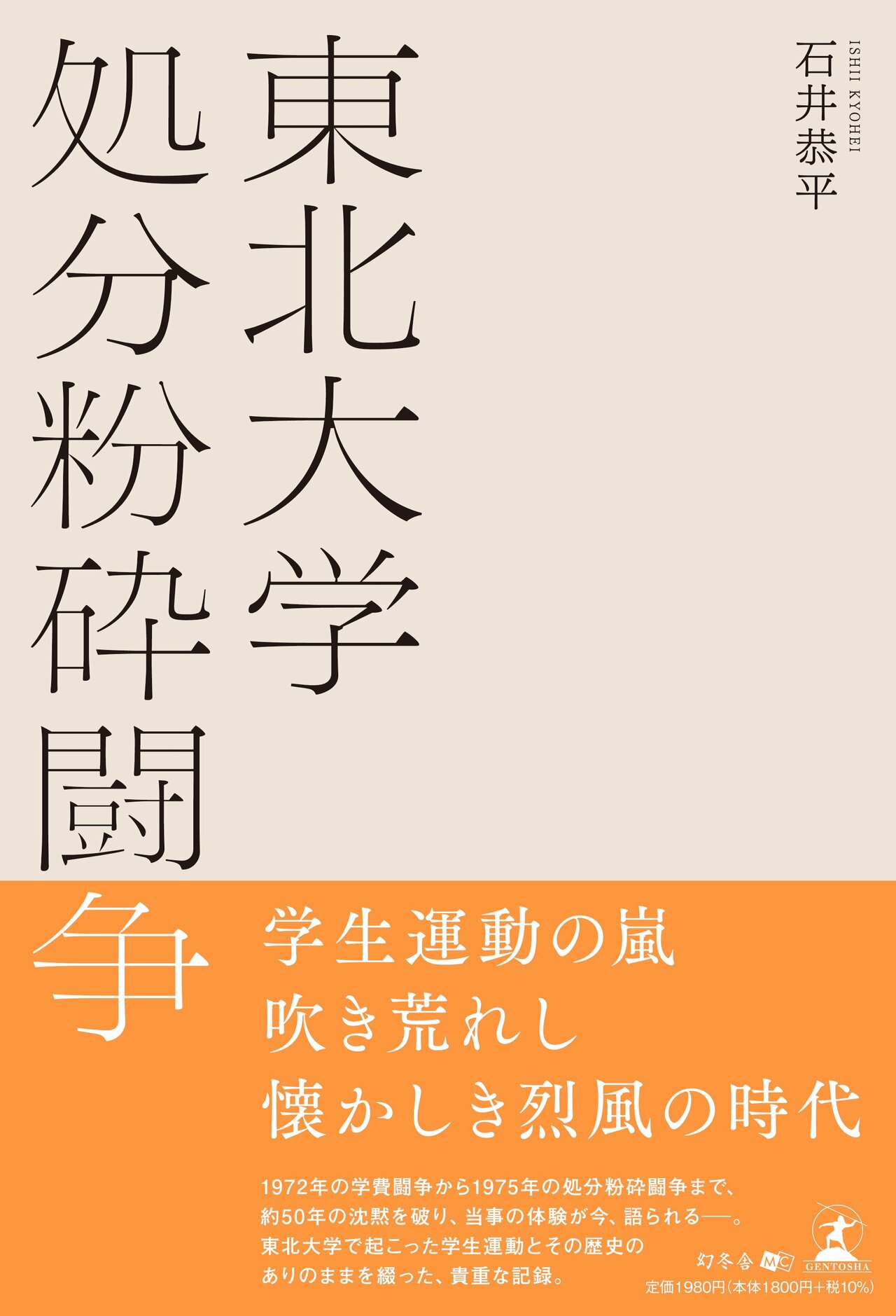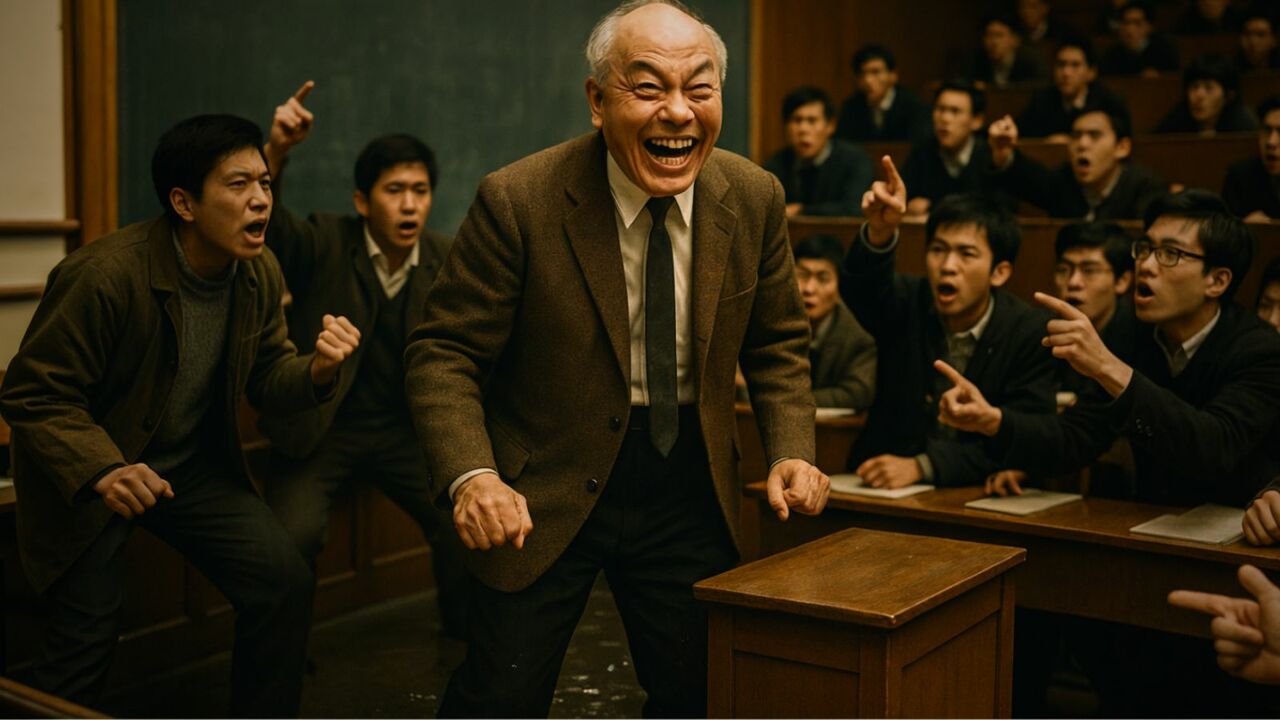サークル部室問題に関して、次のように処分が決定された。
退学 2名
無期停学 6名
警告 11名
そして、このとき高橋教養部長は、次のように決意表明を行った。曰く、「今後も処分するときはする」。
8・20政治処分の問題点
ここで、8・20政治処分の手続き上の不当性や明らかな問題点を被処分者の「異議申立書」を吟味しながら整理しておくことにする。これらの問題点により、8・20政治処分の正当性が問い直され、大学当局は、およそ1年後には、さまざまな経緯がありつつも、処分の全面白紙撤回へと追い込まれるのである。
(1)8 ・4通知の段階においてすでに処分内容(退学、無期停学など)が決定されている。本来、教授会から評議会を経て処分が決定されるものである。これを裁判に喩えるなら、まず判決を下してから、あたかも審理を尽くしたように繕っている。
(2)事情聴取は、全く形式的なものであった。「念のために、文書で釈明もしくは異議申し立てをせよ」ということで、処分理由となった事実関係について、当事者の釈明や申し開きを認めない一方通行的なものであった。しかも、「異議申立書」は、学生側に対してアリバイ的に行われたもので、教養部教授会には一切提出されなかった。
(3)処分理由の中に東北大学学部通則29条の「学生の本分に違反した」というのがあるが、「学生の本分」というのは、広義に恣意的に解釈される余地がある。つまり、大学当局に都合よく解釈される危険性がある(実際、高橋富雄教養部長は、後に学生の追及に対して「学生の本分とは、教養部教授会で決めることである」と答えている)。これについては、次の二つの問題点が指摘される。
①「学生の本分に反した」という学則違反については、今回の懲戒処分が初めてで あり、1969年の学生との団交の場でその凍結を確認してから、たびたび「死文化」されたものとして確認されてきた。
② 罪刑法定主義 (「どのような行為が処罰されるか及びその場合どのような刑罰が加えられるかは行為前の法律⦅成文法⦆によってだけ定められるとする立法上の立場。近代刑罰論における基本原則である。憲法三一条は、手続面の適性の保障とともに、その前提として実体法上の罪刑法定主義を保障したものとして解されている」『法律用語辞典』法令用語研究会編 有斐閣 第5版2020)が主流であり、あらかじめ文書化されていない、曖昧な規則で処分するのは法の精神に反する。
(4)前サークル協議会運営委員4名、現「サークル協議会運営委員」1名が含まれているのは、「サークル協議会」そのものの非合法化を目的としている。
(5)処分理由の誤認がいくつもある。例えば、参加していない闘争を「参加した」と強弁し、事実関係をねつ造している。
【イチオシ記事】妻の姉をソファーに連れて行き、そこにそっと横たえた。彼女は泣き続けながらも、それに抵抗することはなかった