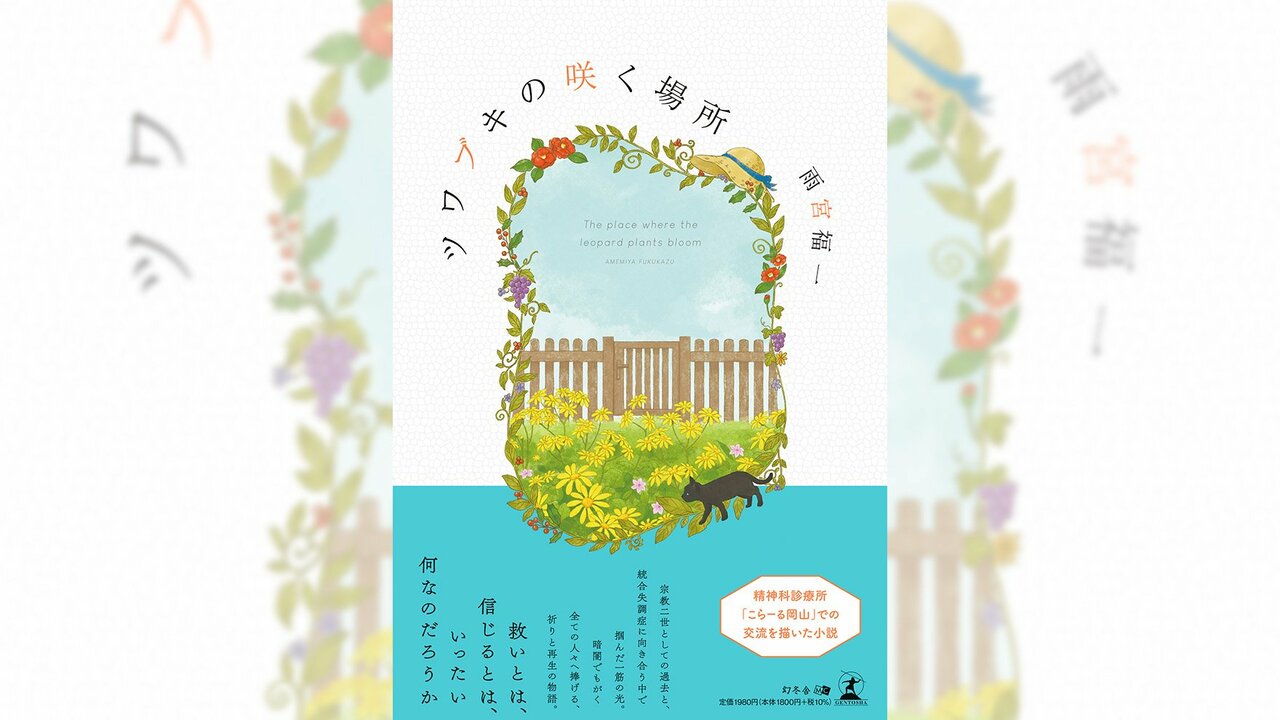【前回の記事を読む】子どもの私が、教祖と呼ばれていた壇上の老人に手を振る。思い出すのは、大人達の狂った言動と、視野が血で赤くなるほどの暴力。
第一章 靴
【三】
「こっちだ。喫煙所があるんだ」
にかっと音がしそうな笑みを浮かべて、彼は私を連れていく。教会の外に設営された小さなプレハブの喫煙所の出入口はガラス戸で、カラカラッと乾いた音を立てた。備付けの椅子に腰掛けたら、教会の庭をぐるり見渡すことができる。
喫煙所の内部は、数種の煙草の香りが混じり合った匂いがする。私の見知らない誰かもまた、ここで喫煙を楽しんだものと思われる。黒い角柱の上に、孔がいくつも開けられた銀色の受け皿の載った、平凡なデザインの吸殻入れが設置されてある。
「びっくりしただろう」
言いながら、永ちゃんは煙草を取り出して口に咥えた。その煙草の先っぽへ、手のひらにすっぽり隠れるくらいの大きさをしたライターの火が点く。煙をすぅと吸い込み、ひとしきり香りを味わった後、紙臭い匂いをさせながら吸った煙を吐き出す。
頷いた私の手を見つめて永ちゃんは言った。
私は菅野さんの聖書を手持ちにしている。
「そうか。実はな。俺は今朝、お前が聖書を持って眠っているのを見て、すっげえ驚いた」
「あっ、こっ、これは。なぜか急に思い出して。菅野さんがくれたんだよ」
「……菅野が。そうか」
永ちゃんは、しみじみと言う。
「俺はキリスト教を信仰しているんだ」
「信仰……」
「いつも、ボランティア活動の話をしてるだろ?それはここでしていることなんだ」
永ちゃんは、さらに続ける。
「それからな、ここは菅野も所属してた教会なんだ」
「えっ!?」
そのせりふは、私をとても当惑させた。二人はつまり、自分たちの信仰を私にずっと黙っていたということになる。私の中の何かが、打ち明けるという行為を彼らに思いとどまらせていたわけである。
私が何か言い出すよりも早く、永ちゃんが言う。
「菅野も、俺もな、キリスト教だけじゃなく、お前が神の存在というか、目に見えないものを信ずることそのものに、どうしてだろうと疑問を感じていると知っていてな、それでどっちも言い出せなかったんだ」
遠い日の追憶に、私は心をしばし遊ばせる。
思い起こせば、ずいぶん昔のことである。菅野さんと永ちゃんと連れ立って、街歩きをしていた時のことだ。
――あれは菅野さんが健在であったころのこと。ある年の元旦の話である。にぎやかな雰囲気に浮かれる人々の列が、神社の本殿まで長く延びていた。
祈願をする際の仕草を互いに確認し合う家族。神社へ来たのは初めてらしい子どもに、初詣での意味を話して聞かせる親。祖父母に絵馬を買ってもらう受験生と思しき少年。
そんな風景を眺めながら、私が思わず言ってしまったこと。
「祈ったところで、何になるんだろう……」