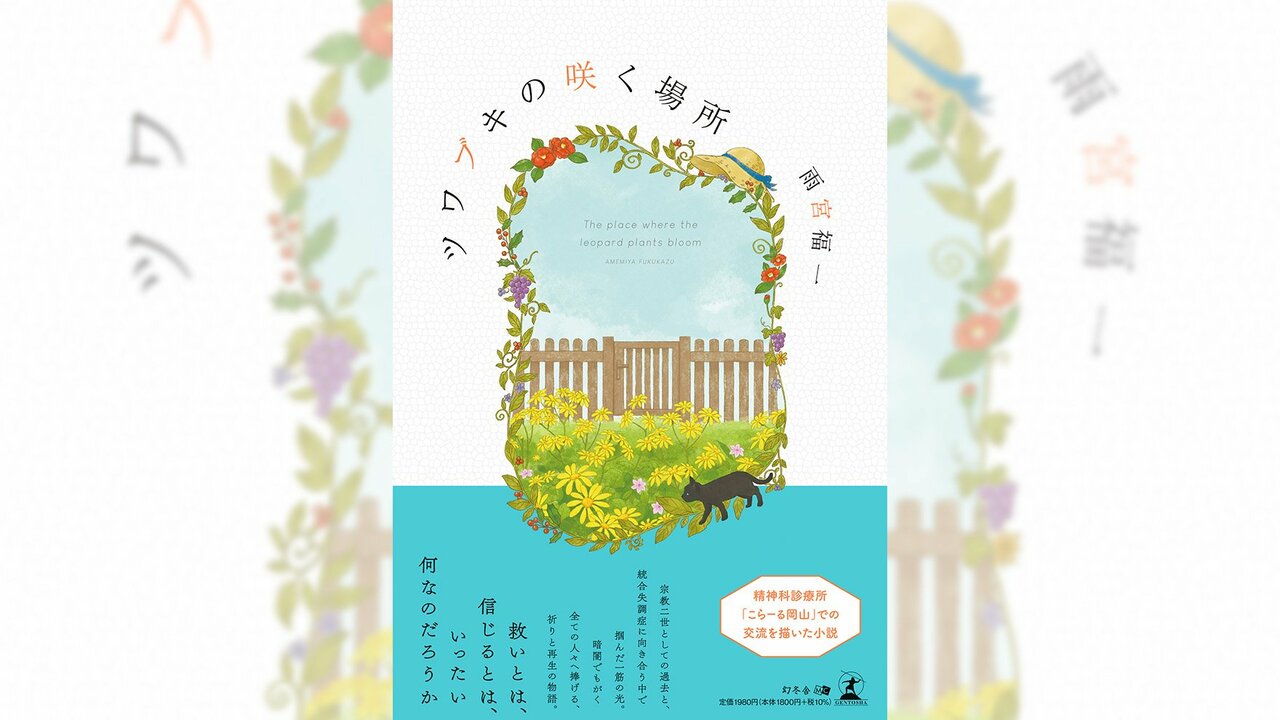【前回の記事を読む】祈ったところで、何になるんだろう…カルト教団に洗脳され、結びついた両親。壇上に立つ老人は救世主でも神様でもなかった。
第一章 靴
【 三】
「ああ。あのホールへもこの喫煙所にも、菅野と来たよ。洗礼を受けたのもここだ。そうだ、洗礼って知っているか?」
「いや、よく分からないよ」
「洗礼というのは、キリスト教徒になるとき、誰もが受ける儀式なんだよ。儀式の様子は、宗派でいろいろと違っていて同じじゃないんだが、イエス・キリストに生涯を捧げること、生き方のすべてをイエス・キリストへ委ねること、いのちの書に名を刻むことで……何て言えば良いのか。まだまだ俺も勉強の途上だ。うまく、言えないや」
そう言う永ちゃんのかたわらで、私は思案していた。生涯を捧げる。生き方を委ねる。いのちの書に名を刻む。いずれも、目には見えない、教えの中に息づくイエス・キリストへの信仰を意味している。
それは一体全体、どのような感覚なのだろう。
言葉を押し出そうとして、言葉が見つからなくて、息だけが出たというような音である。父母が昔、韓国で信じ切っていた救世主を騙る老人は、自分を信じることこそが真の信仰であり、救いはその信仰がもたらす恩恵だと説いていた。しかし、私たち家族は、それで救われるどころか、塗炭(とたん)の苦しみを舐めた。
(救いとは、信仰とは、なんだろう……)
昨日の晩から抱きしめるようにして持っていた聖書は、体温を宿して温まっていた。
「永ちゃん。私は、生まれ変わりたいと思っているかもしれない」
ぽつり。自然と口からこぼれた言葉に、永ちゃんからの返事はなかった。でも、私が言ったことを否定しないで、ただただ聞いてくれただけで十分だった。
永ちゃんは私と並んで、それはもう、大変に眩しいものを見つめるかのように、路傍に咲くタンポポたちを眺めているのであった。
それからしばらくの間、私は教会へ通うようになった。本格的な春に向けての移ろいが、例年よりも新鮮なものに感じられるようであった。
それから数ヶ月経ったある日のこと、永ちゃんと一緒に教会から家へ帰るまでの道すがら、車の窓越しに商店街の風景が流れてゆく。
永ちゃんは、交差点を右へ曲がる様子である。カッチ、カッチと音を立てて点滅するウインカーをよそに、永ちゃんは話しかけてきた。
「ちょっと寄り道をしよう」
車が停まったのは、靴屋の店先であった。
「永ちゃん?何か、買い物が?」
「ああ。スニーカーを買おうと思った」
「そっか」