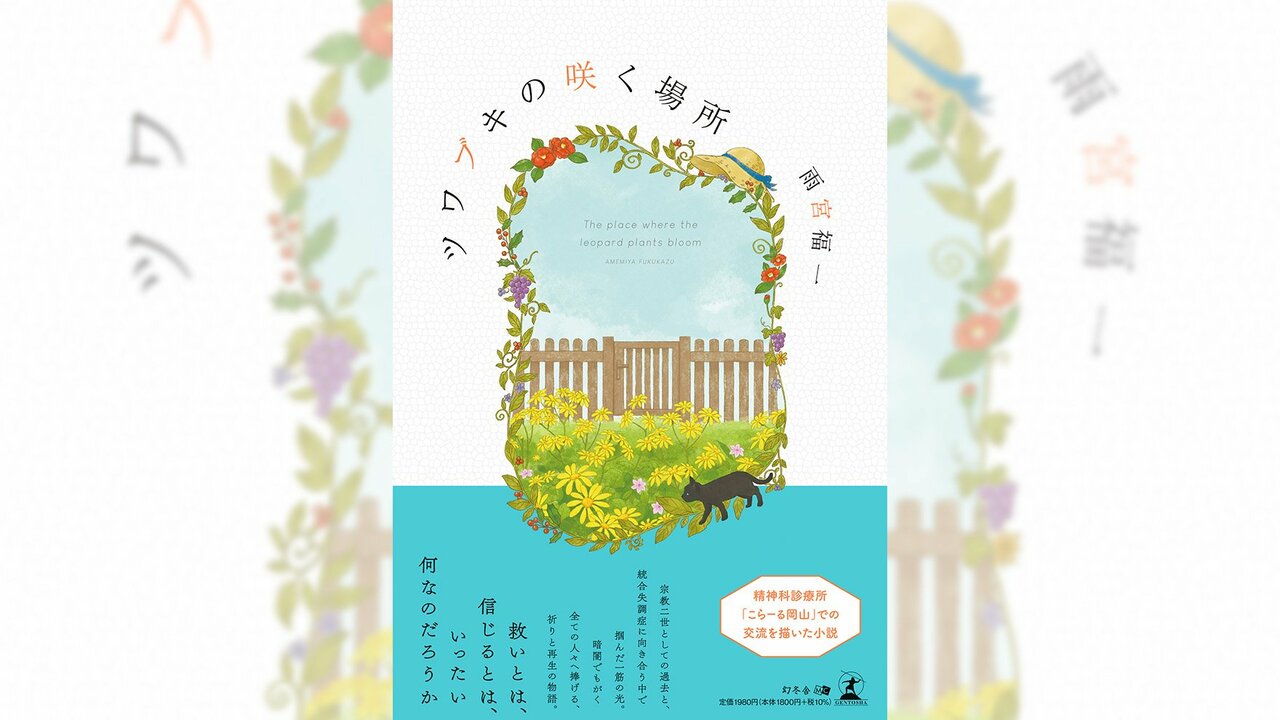【前回の記事を読む】「ぼろぼろのその靴がお前の人となり、だなんて俺には到底思えない」彼の手のぬくもりは、言葉よりも遥かに雄弁だった。
第一章 靴
【 三】
永ちゃんの手がそっと離れる。
「そんな……」
思わず目を伏せると、白い紙袋が車の床に落ちていることに気付く。薬が処方されるときによく使われる、薬の名前や飲み方を記した小型の紙袋である。薬が中に入ってるのか、少し膨らんでいる。
「あっ! ごっ、ごめん。永ちゃん、うっかり踏んじゃうところだった」急いで拾い上げたら、永ちゃんの腕がさっと伸びてきた。
「わるい、わるい。風邪の薬を置きっ放しにしちまったんだな。いやあ、全くうっかりしてた」
ばつが悪そうに笑いながら、永ちゃんは、紙袋の表を見せないようにして、自分のポケットへねじ込んだ。風邪をひいてたなんて、聞いていなかったけれど、……何の薬だったんだろう。熱冷ましかな。
永ちゃんが車のドアロックを解除する。
いくらかの不安な気持ちを残したまま、私はゆっくりと車から降りることにした。庭の雑草をしっかりと踏みしめながら。
「永ちゃん。……あの。な、何でも相談してくれよ? 僕にできることなら、協力するからさ」
「おう、ちゃんと頼るとも。じゃあな! がんばれよ」
がんばれ、という言葉を素直に受け止めることができたのは、いつ以来のことだろう。ぐっと背中を押してくれるようなあたたかさがある、永ちゃんの「がんばれ」。私は、靴入りの袋を抱えたまま、鮮やかな手振りで庭から出て行く永ちゃんの後ろ姿を見送る。
「ありがとう!」
大きな声で礼を言った。去りゆく車の窓から手のひらをのぞけ、少しだけ手を振って、お別れをした。
私は一つ、二つ、呼吸を整えた。頭の中の不安な気持ちを、今日の大空に向けてかろやかに解き放つように。
「よしっ。大切に使おう」
大切に、大切に。頂いたスニーカーを、私は靴箱へしまった。