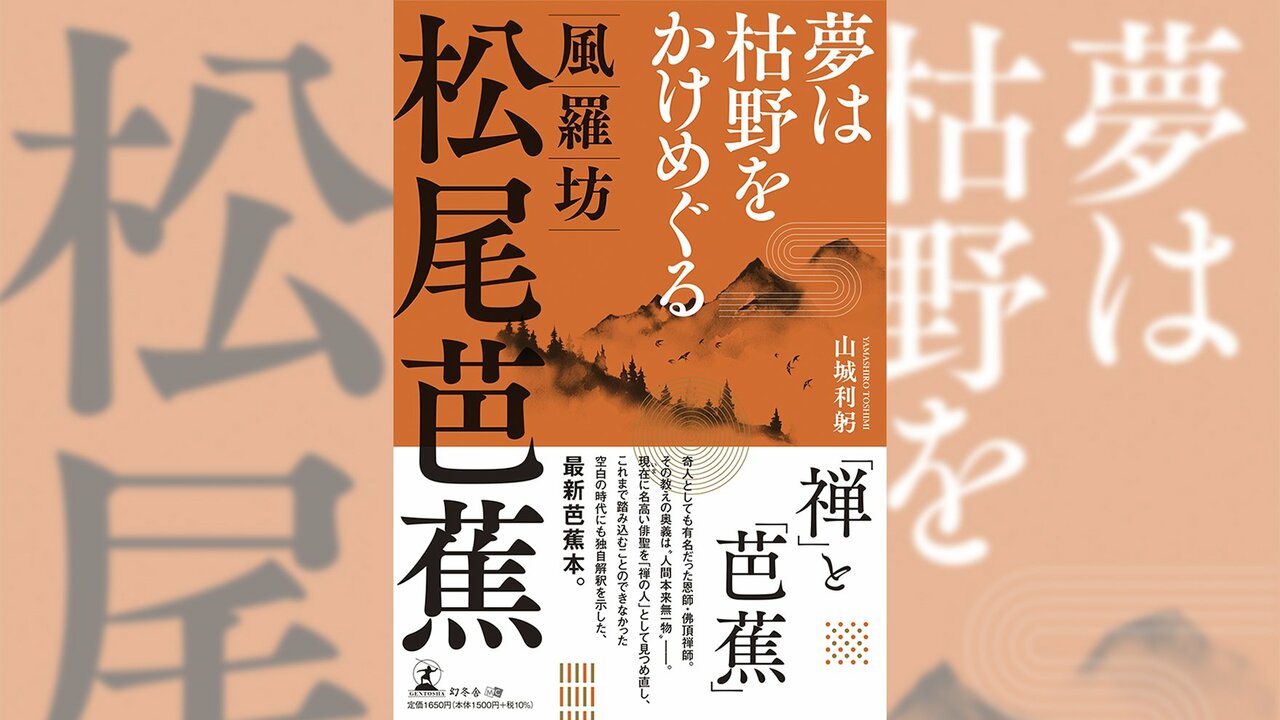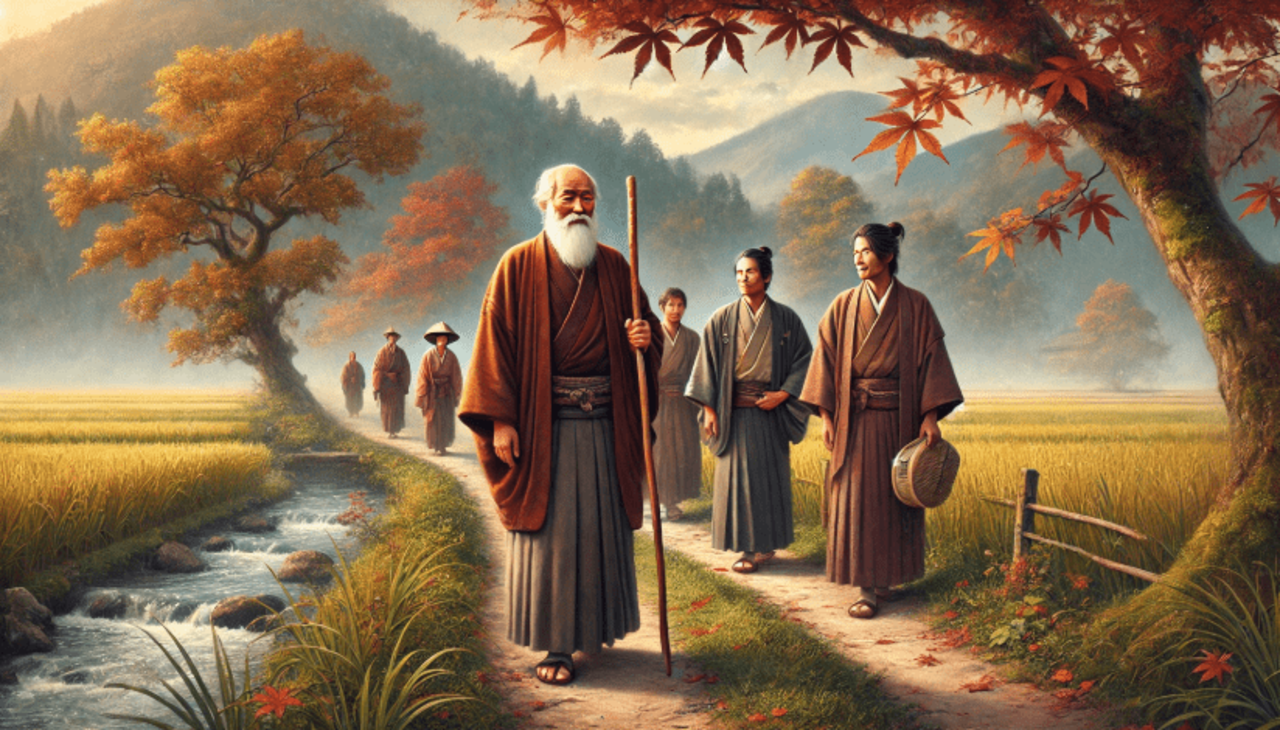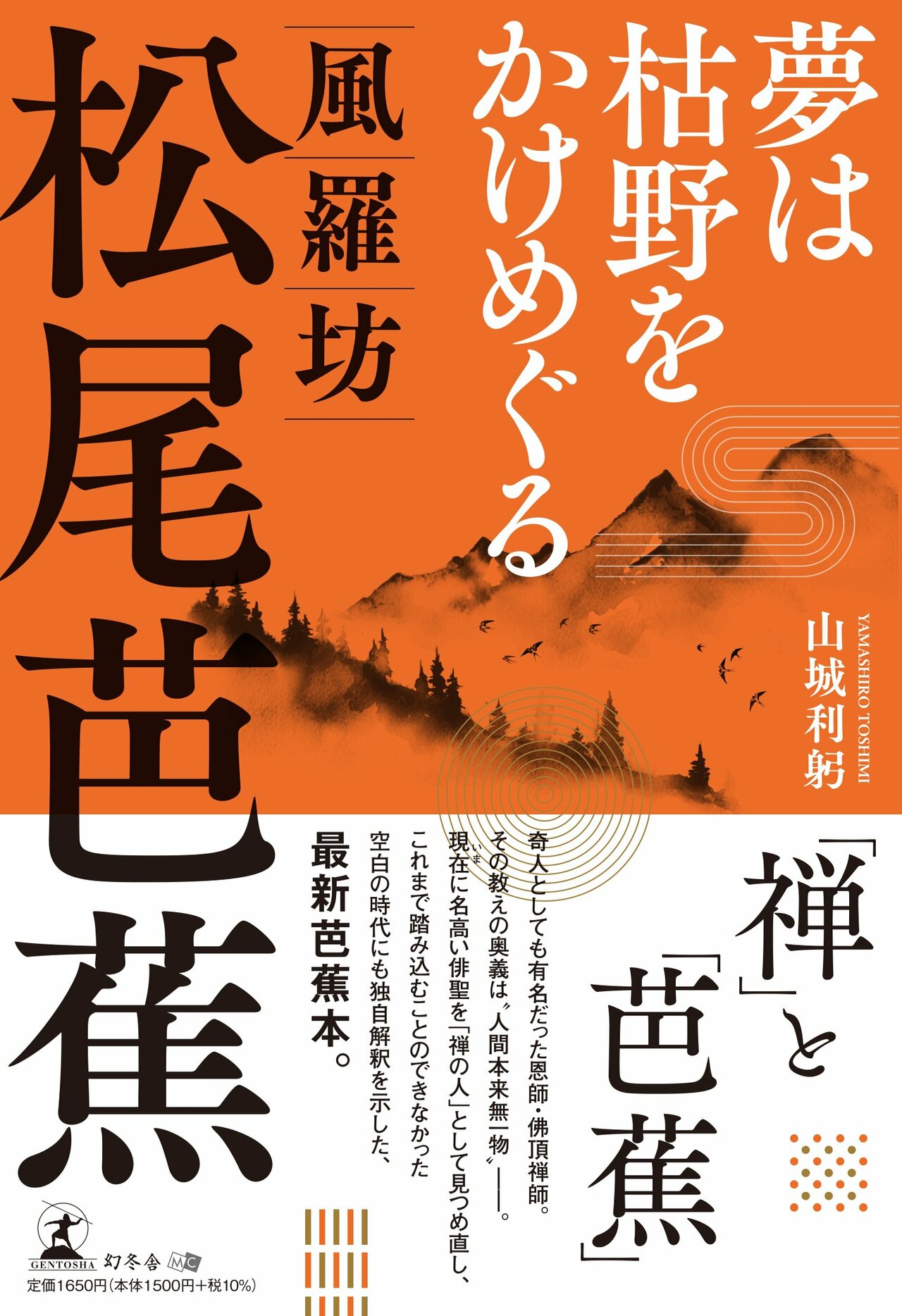【前回の記事を読む】【松尾芭蕉】「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」の句は、生涯を肯定した句ではないか? [肉体の旅路は終わるとしても……]
第一部 夢は枯野をかけめぐる
後記
芭蕉が俳聖と言われるようになったのは、没後百年(百回忌)頃からです。芭蕉の死後、談林派俳句は急速に衰え、ただ面白いことが好まれ、季語の縛りもなくなり、川柳風の流行になって行く。
そんな流れの中で立ち上ったのが蕉風復古です。その旗振りが、芭蕉の弟子の更に弟子の、与謝蕪村であり、大島蓼太です。〝かるみ〟と〝あたらしみ〟の工夫が見事な人達です。
しかしこの流れも、幕末から明治維新にかけての、動乱の世相に踏みにじられて行きます。正岡子規が拾い上げるまで。俳句が盛んであることは、世の中が平和である証です。
「猿蓑」を立ち上げた頃に入門し、編集に参加しながら天才的な成長をみせた凡兆がいます。現代の俳句界にも通用する〝かるみ〟〝あたらしみ〟の成果を見せながら、残念なことに、猿蓑発行後、仲間と諍い、舞台から消えてしまったのです。
句文集「猿蓑」は蕉門が旗揚げ提唱した、新しい俳句の提唱であると同時に、まだ勢力を失っていなかった旧俳諧連中との軋轢の始まりでもあった。
「おくのほそ道」の旅で芭蕉が確信した新しい作句理念の提唱に、ついて来れない人も多数いた。反発する人も。
第二部より、蕉門十哲といわれる人達の猿蓑の句と、猿蓑以降に育ち〝かるみ〟路線展開に功績のあった人達について述べてみたい。