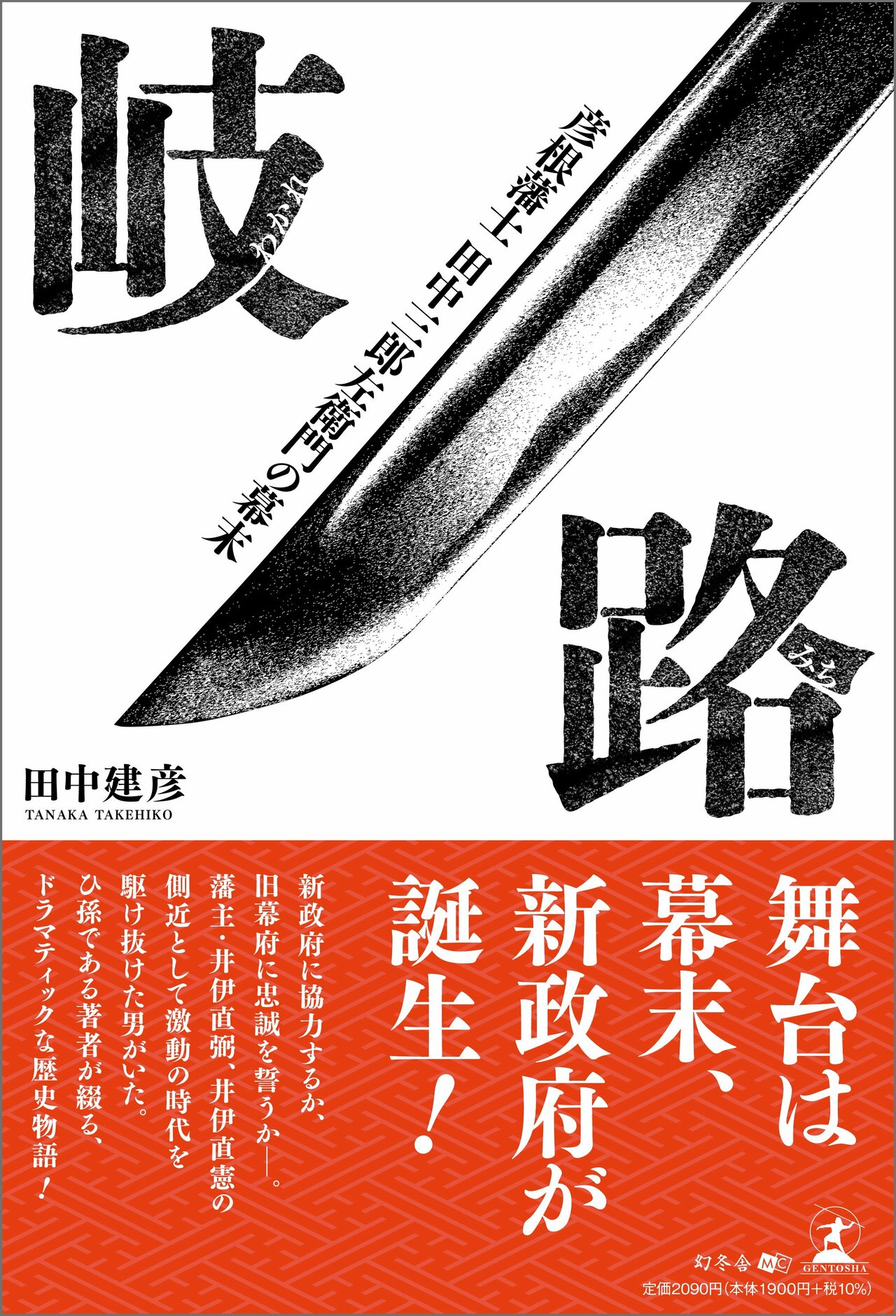側役として藩主の相談にあずかってきた彼も今やそれしか道はないと信じていた。藩が生き残り井伊家が存続するためには、この道しかないと彼は思っていた。
直接に彼は藩主を説得したわけではなく、それは最終的には藩主自身の決断ではあったが、それ以前に藩主の下問に答えて彼が説明した情勢分析には彼自身の意見が反映されないでは済まない。
それが藩主の最終的な決心への道筋をつけたであろうことを思うと、彼はこの裏切りが自分の責任であると感じていた。それは藩主にとっても彼にとっても苦渋の決断だった。
昨夜の集会での一幕を思い出しながら彼はしばらく天井を凝視していた。なんでこんなことになったのだろうと振り返りながら、彼は藩主直憲の年齢が同じころの自分を思い出していた。
その頃は幕府もどっしりと安定しているように見えたし、藩もゆるぎない幕藩体制のもとで安定していた。
一 初出仕
琵琶湖の湖面を縫って城下町に吹きぬける風は冷たく、彦根の冬の寒さは格別だった。天保十一年(一八四〇年)二月になったばかりのこの日は特に寒さが身にしみた。
田中徳三郎はその寒風の中を、弘道館での稽古を終えて竹刀と防具を肩に担ぎ石ヶ崎の我が家に戻って来ると、門前に父の供をして江戸にいたはずの中間(ちゅうげん)の芳蔵が待っていた。
「おや、芳蔵、どうした。父上がお戻りになられたのか」
「いえ、若様、私一人で戻りました。御父上様からの御用でございます。御用の筋は後ほど母上様からお聞きください。まずは汗をお流しなさいませ」
「わかった。で、父上はお元気か?」
「はい、大変お元気で、仕事に励んでおられます」
徳三郎は、芳蔵の声を背に聞きながら井戸に向かうと、真冬にもかかわらず上半身裸になり、濡れ手ぬぐいで体を拭き、自室に戻って衣服を改め、母のもとに行った。
【イチオシ記事】朝起きると、背中の激痛と大量の汗。循環器科、消化器内科で検査を受けても病名が確定しない... 一体この病気とは...