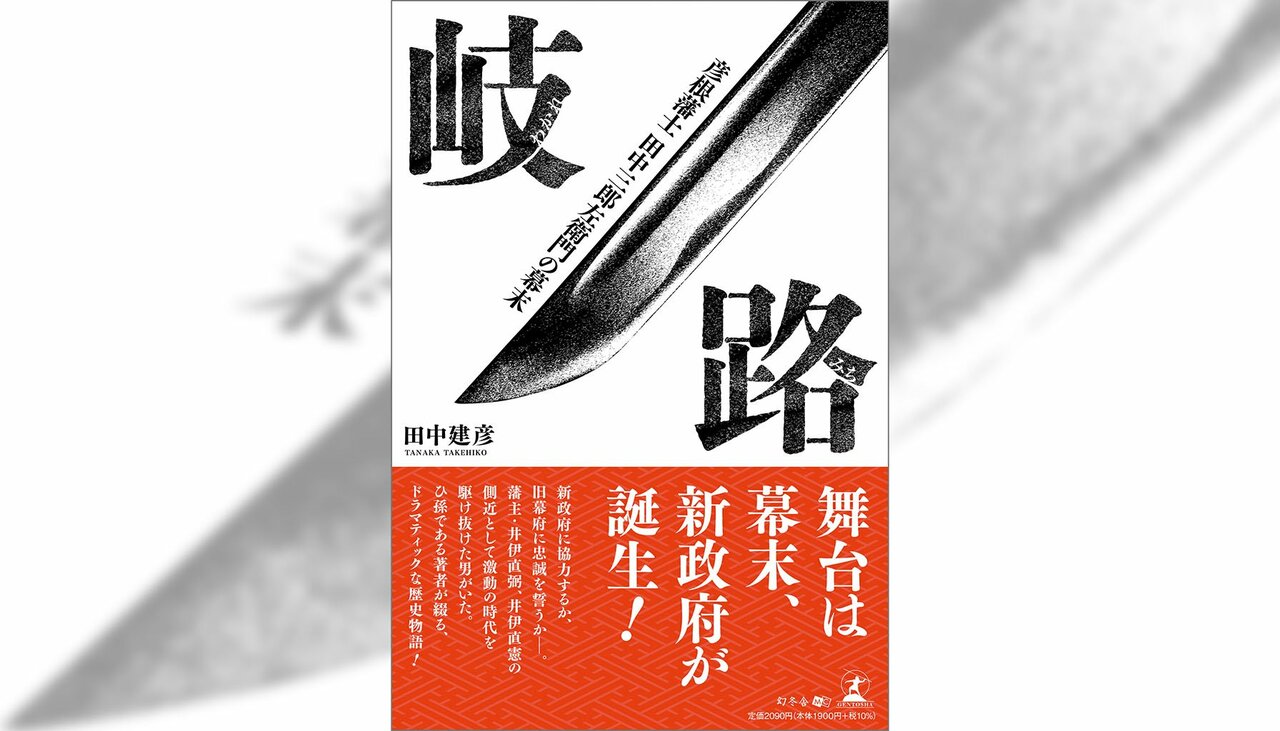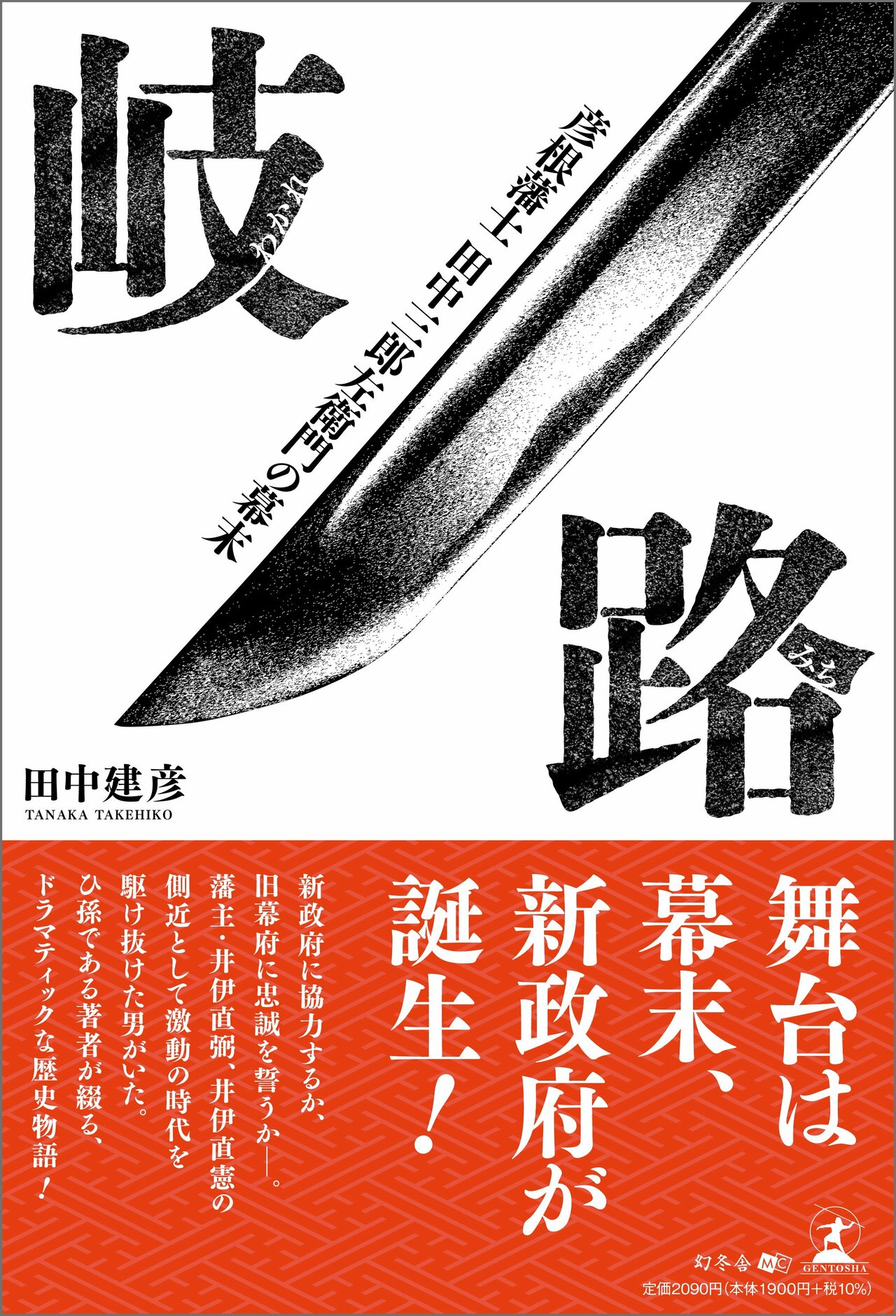【前回の記事を読む】「この野郎!」――彼の手が何か異様なものに触れた。荒ててそれをつかみあげると、それは他人の手だった。
一 初出仕
「構うな。放っておけ」
あと四、五日で江戸である。早く江戸に着きたい、という思いの方が強かった。
にぎやかな軽井沢宿を過ぎると、道は碓氷峠の坂道に差し掛かった。うっそうと茂った木々の中を走る山道を登りきると、なだらかな尾根道に出た。そこには何軒かの茶屋が立っていて、すでにあちこちの茶屋には旅人が餅や団子を食べながら休んでいる。
「若様、一休みして、団子でも食べませんか」
芳蔵の言葉を待つまでもなく、徳三郎は遠くに茶屋を見かけた時からすでにそうする気でいたので、二つ返事で一軒の茶屋に向かった。天気も良く、長い登りの後で汗ばんでいたので、中に入らず店先の縁台に腰を掛けて、みたらし団子と餅を注文した。
腰の曲がった老婆が持ってきた団子を食べながら、徳三郎は遠く眼下に見える坂本宿をぼんやりと眺めていた。
「旦那、お願えです」
という声が突然聞こえて、びっくりして横を向くと、そこにはあの巾着切りが両手をついて彼の方を見上げていた。完全に油断していた。昨日の恨みから彼を狙っていたとしたら、襲われていたであろうが、巾着切りの顔にはそのような様子はなかった。
「こ、この野郎!」
あわてて立ち上がって身構えた芳蔵にちらと目をやると、その男はまた徳三郎に目を移し、頭を下げて言った。
「本来ならばお手打ちになっても仕方ねえところをお許しくださりありがとうごぜえやした。この稼業に手を染めてから三十年、今まで一度も失敗したことはごぜえませんでしたが、何気ない様子をしながら、あっしの動きをちゃんと見ておいでとは、お若いのによほどの遣い手のお武家様とお見受けいたしやした。
それにもかかわらず、お許しくださるそのご器量に、熊吉あまりのありがたさに心がとろけてしまいました。本来ならあの時にあっしの生涯は終わっておりやす」
「お前、そんな礼を言うためにわざわざ後を追ってきたのか」
「はい、いえ、そればかりではありません。あの時にこれまでの熊吉は死にやした。許された残りの命を若様のためにおささげしたいと決心いたしやして、後をついてまいりやしたので」
「よせよ、そんな勝手な決心をされても私には迷惑なだけだ。それにな、熊吉といったな。私は剣客でも何でもない。たまたまあの時、胸がかゆくてそこを掻こうとして懐に手を入れたらお前の手がそこにあったというだけだ。偶然だよ」
「またまた。奥ゆかしい。お武家様とも思えぬ、その謙虚で優しいお姿に熊吉は惚れやした。お願えでごぜえやす。飯炊きでも何でもいたしやすから、あっしを使ってやっておくんなさい。救っていただいた命を懸けて一生懸命お仕えいたしやす」