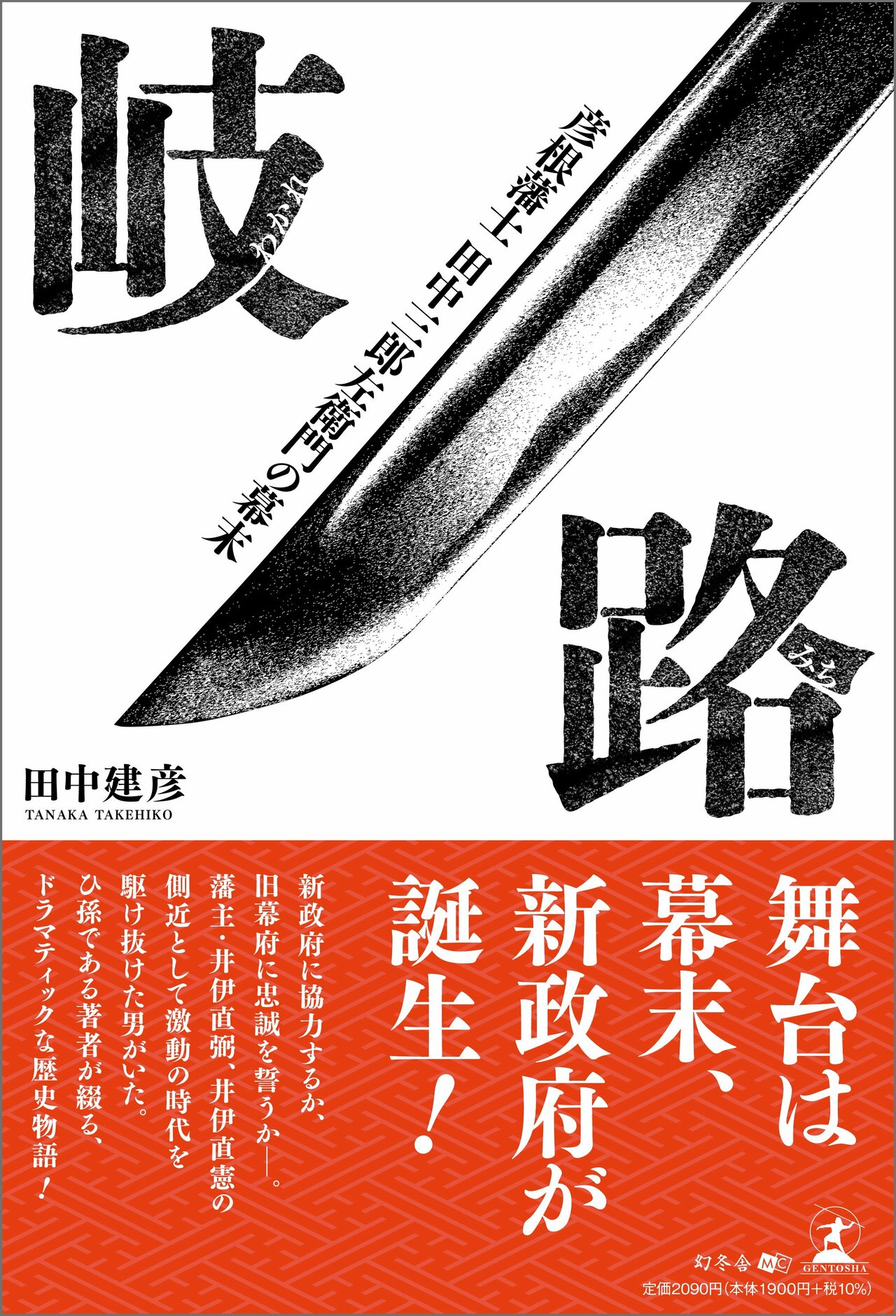「冗談じゃない、お前みたいなぶっそうな……いや悪かった。だが、どっちにしても、私の方にはその必要はない。それほどの決心なら、これまでの稼業からきっぱりと足を洗い、まっとうな仕事について精を出すことだな」
熊吉はなお、くどくどと徳三郎にお願いを繰り返したが、彼は少々もてあまして、残りの団子を口の中にほうり込んで、立ち上がった。
「お前、腹がすいているだろう。この餅、私はもういらないから、食ってくれ」
徳三郎は押し付けるように餅の入った皿を熊吉に渡すと、勘定を済ませてさっさと先へ急いだ。隣の縁台で商人風の旅人が興味深げに様子を見ている。
「お武家様、若様」 と声を上げながら、押し付けられた餅の皿を持って、熊吉は餅を食べるか、徳三郎の後を追うか迷ってうろたえている様子だった。
出発して十日目、彼らは桶川に着いた。その間、後ろを振り返るたびに、熊吉が後をついてきているのがわかった。
「しつこい奴だな。妙なやつに取りつかれてしまった。少々薄気味悪いぐらいだ」
「懐を狙っておいて若様にお仕えしたいなどと、途方もないことを言いやがって。図々しいだけでなく、頭の方も少々おかしいのではないでしょうか」
「恨みに思って付け狙っているとしたら、碓氷峠で私は討たれていた。そうでなかったとしても、あれほどの執念だ、恨まれていたら私はいつか、彼の手にかかって死ぬかもしれないな。それが許されたお礼に奉公したい、というのだから……それにしてもこれほどしつこくついてこられては迷惑だ。芳蔵、何とかならないか」
「はて、どうしたらよいのやら」
そんな会話をしながら、夕食を済ませると、二人はその夜は早々と床に就いた。どのくらい眠っていたのだろう。徳三郎はふと目を覚ますと、彼の顔を覗き込んでいる熊吉の顔が目の前にあった。
「な、なんだ」
驚いて飛び起きて枕元の刀をつかむと、その時には熊吉はすっと後ろに下がって頭を畳に擦り付けていた。「お、お前か。熊吉、たしか熊吉といったな。いつ、どうやって入ってきた」
「へえ、こんな稼業をやっておりますので、このくらいのことは……」