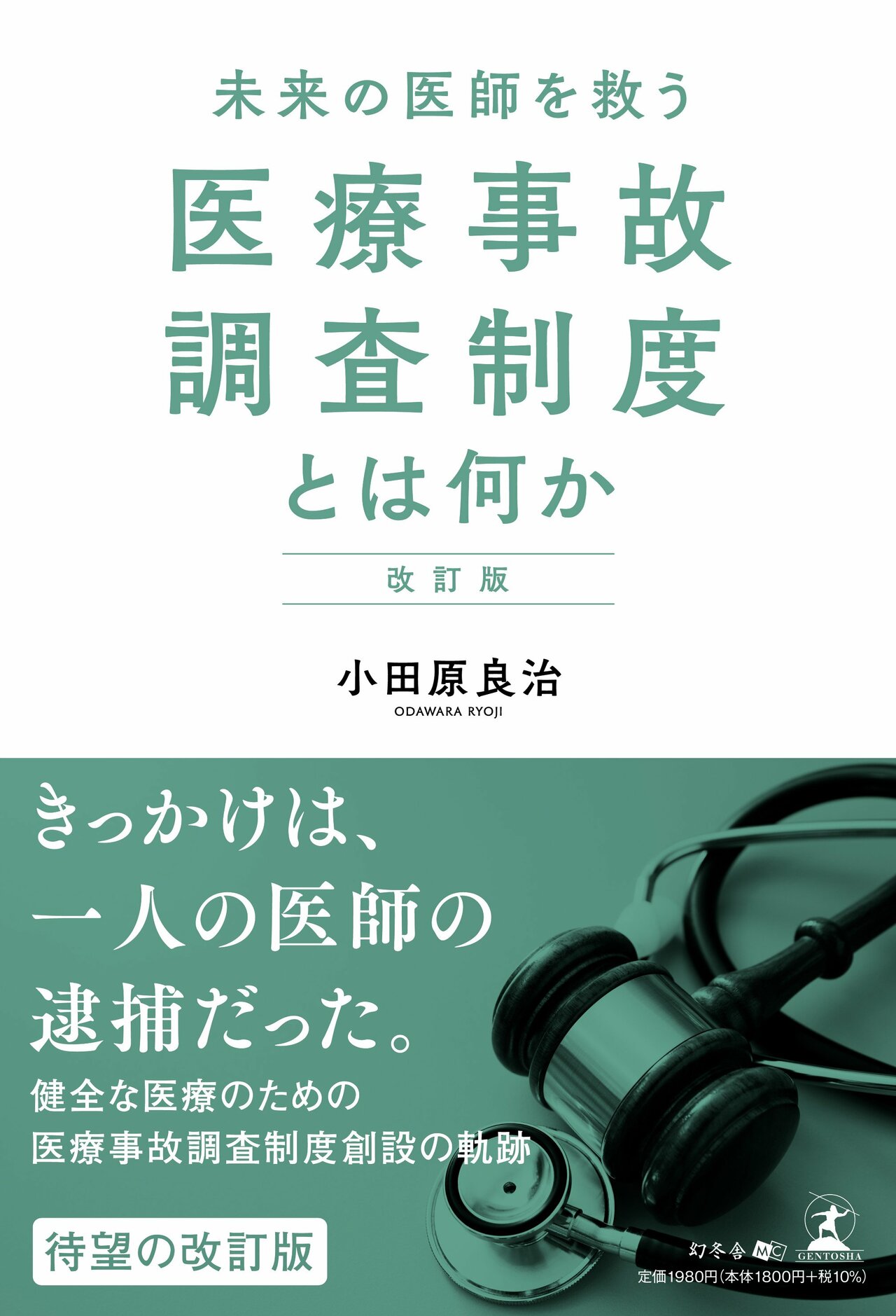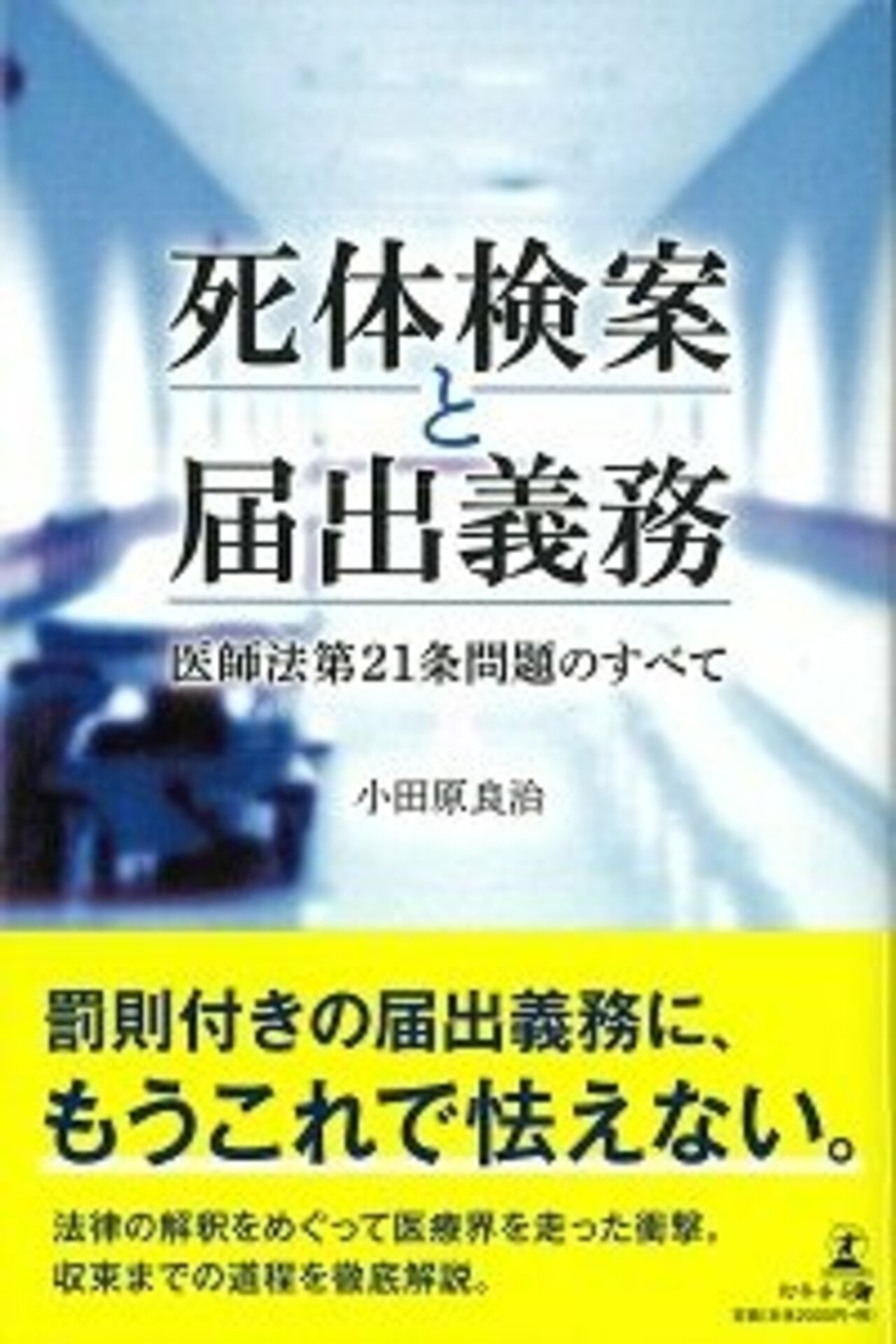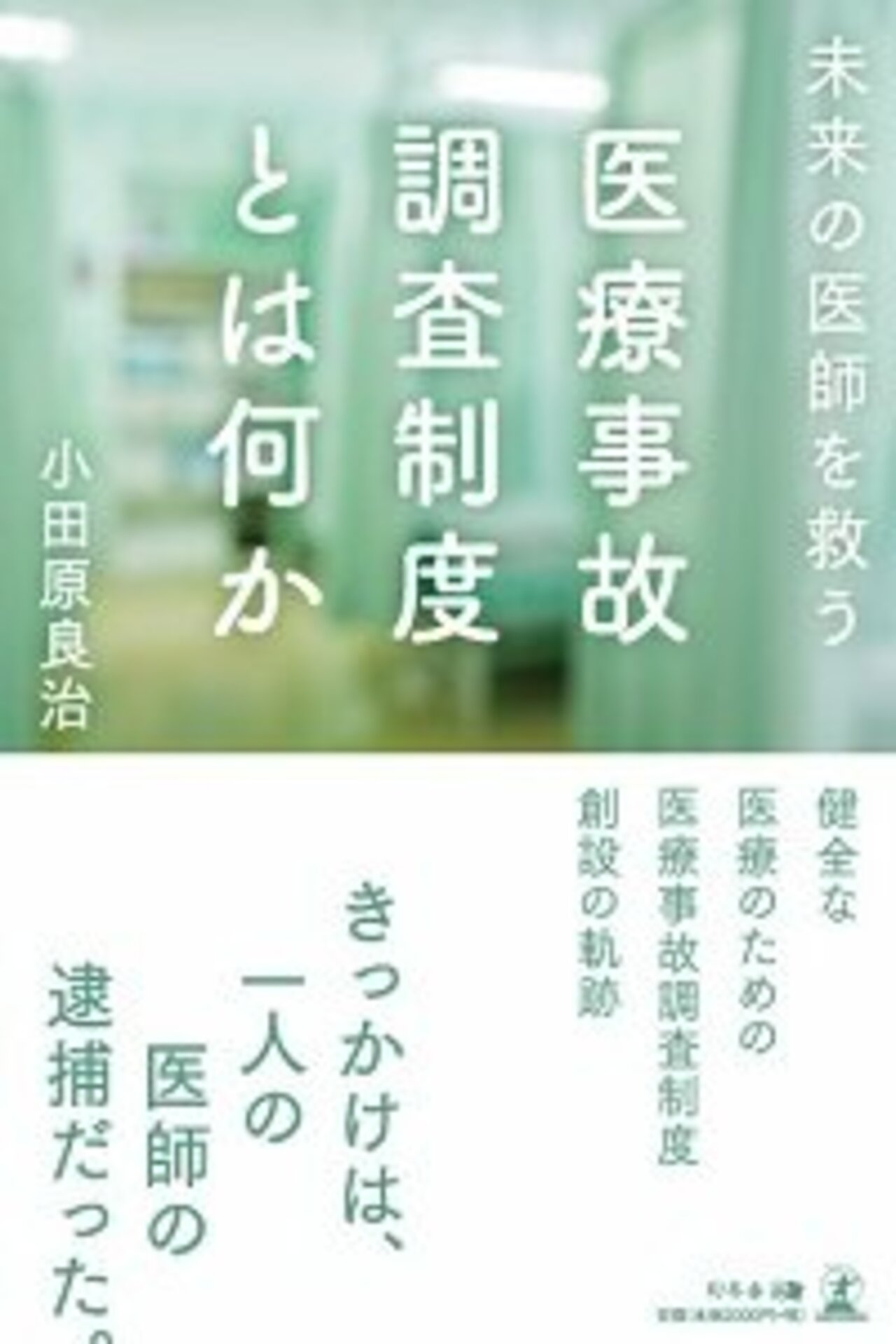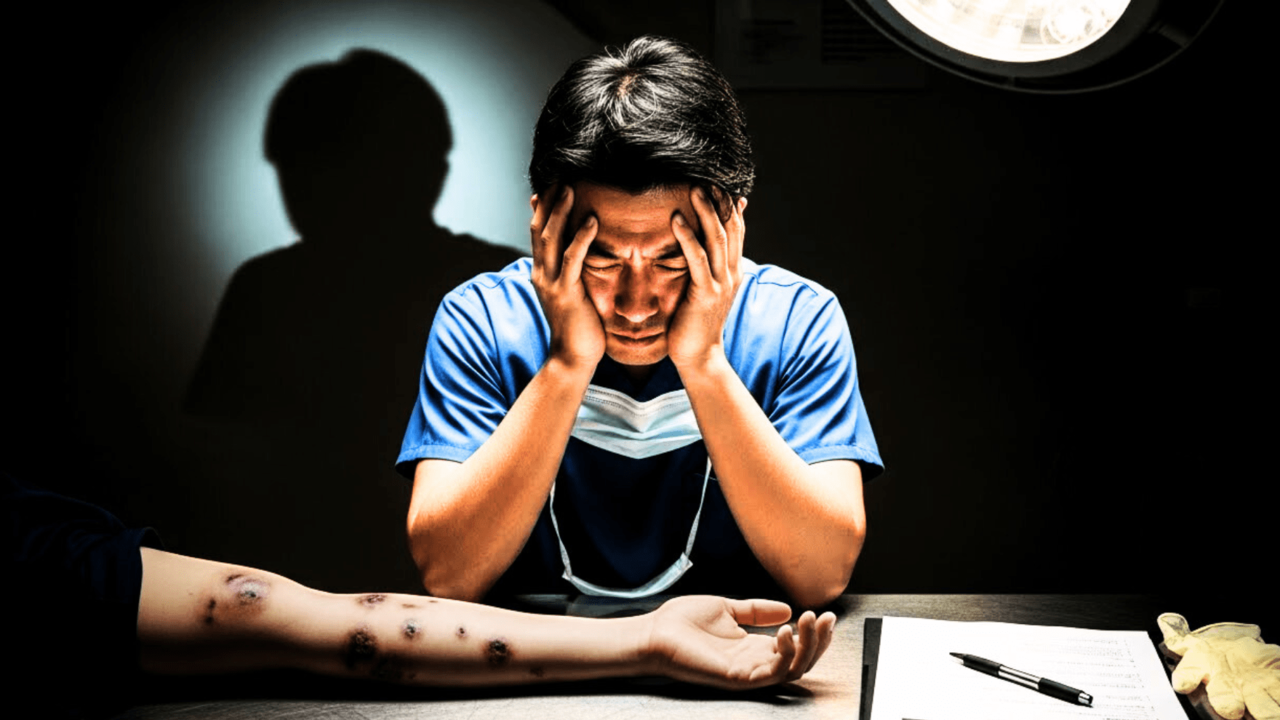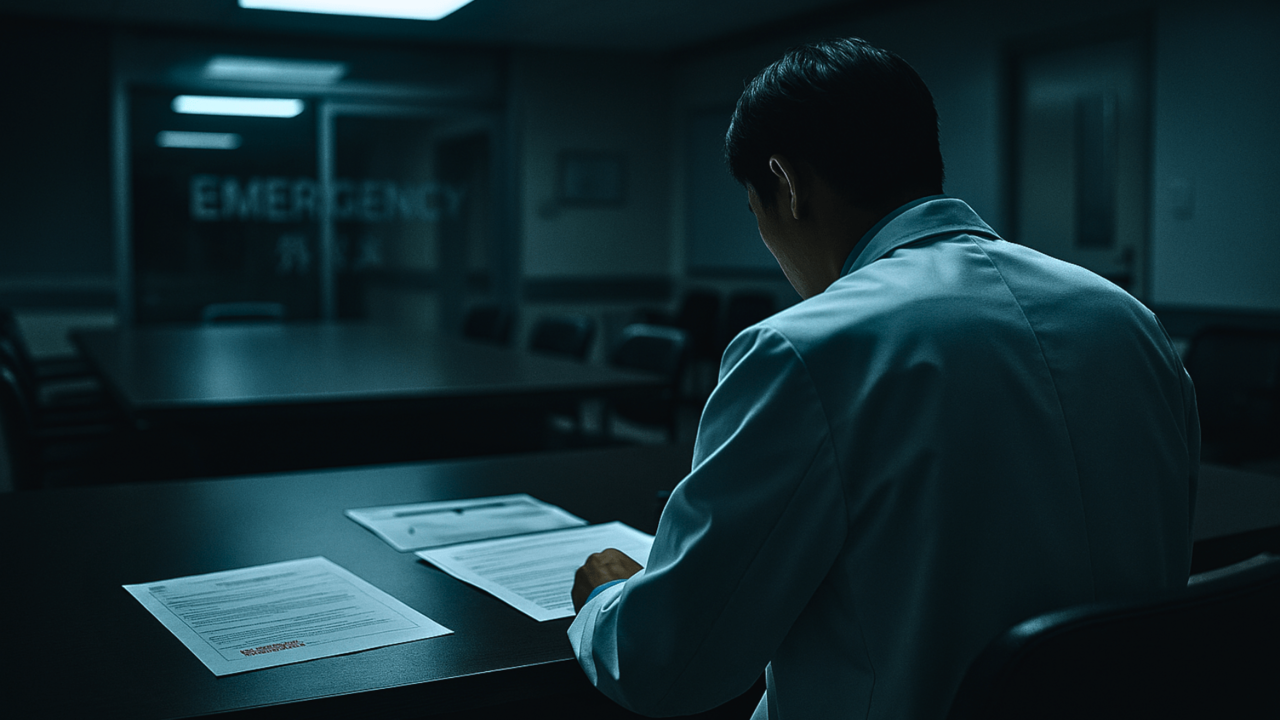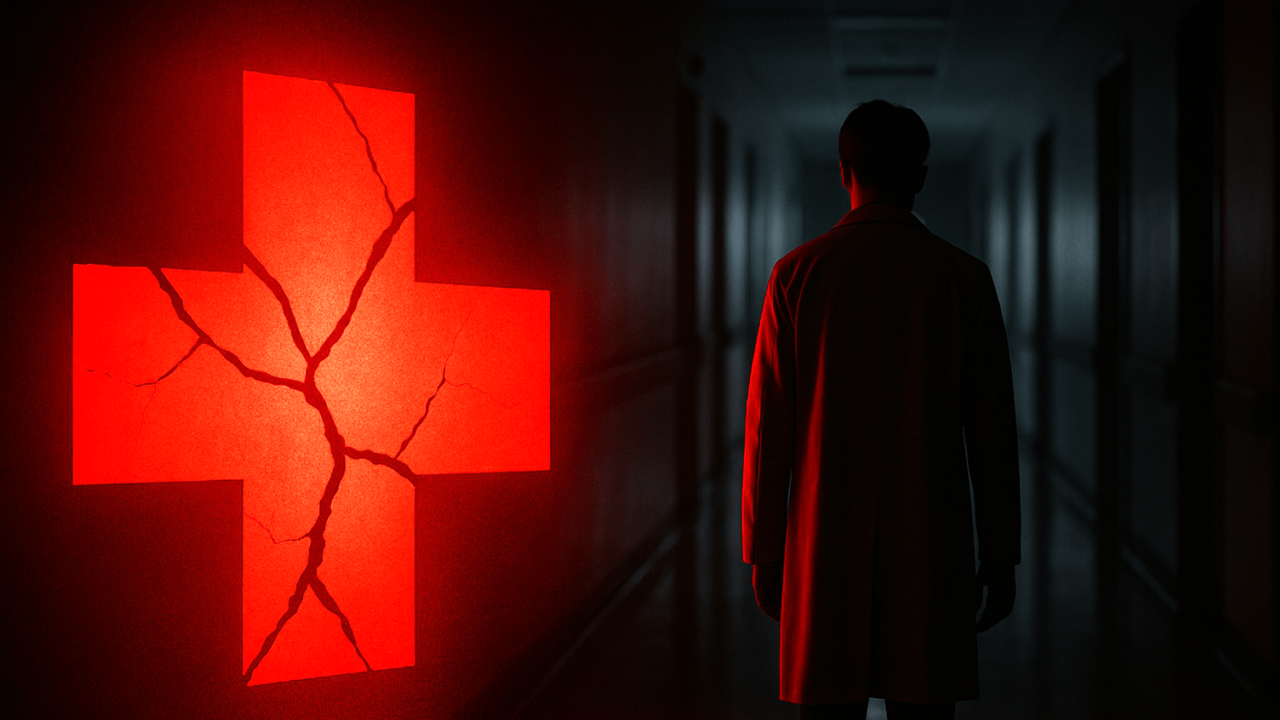筆者らが反対した第3次試案・大綱案は、政権交代とともに店晒しとなっていたが、2012年(平成24年)2月、民主党政権下にて、「医療事故調査・あり方検討部会」として再浮上してくるのである。
そして同年5月、四面楚歌のなか、筆者が日本医療法人協会医療安全調査部会長に就任することとなる。これは孤軍の舵取りを任されたものであり、敗戦処理投手のような立場であった。筆者はショートリリーフのつもりで引き受けたのであるが、これが、想定外の長い厳しいバトルの始まりであった。
行きがかり上、筆者は法律の教科書を読んだ。しかし、素人は素人である。終始、顧問の井上清成弁護士と協議しながら進むことを心がけた。お互い日程的な問題もあったが、事前あるいは事後にメールで協議を行うようにした。
このようにして、日本医療法人協会案をベースとして、2013年(平成25年)1月23日には四病協(四病院団体連絡協議会)合意、2月22日には日病協(日本病院団体協議会)合意に至るのである。
これで、筆者の仕事は終わったと思ったのも束の間、厚労省が強引に「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的あり方」をとりまとめたのをきっかけに、厚労省との長くハードな協議に入るのである。
厚労省との協議には必ず井上清成弁護士と同席することとした。生兵法は怪我の基である。大丈夫と思われる些細なことにも可能な限り二人で臨んだ。一区切り、一区切り、先が見えた時点で日野頌三会長(当時)に報告した。微妙なやりとりが多かっただけに、ほとんどが事後報告となった。黙って任せてくれた日野頌三会長(当時)あったればこその成果であったと思っている。
厚労省に二川一男医政局長(当時)、土生栄二総務課長(当時)、大坪寛子医療安全推進室長(当時)の方々が存在したことも医療事故調査制度の創設に欠かせなかった。さらにメーリングリスト等を通じて、陰ながら支えてくれた全国の心ある人々のおかげで、なんとか走り切ることができた。
また、医療事故調査制度論議の過程での大きな成果は、医師法第21条が「外表異状」で確定したことである。2012年(平成24年)10月26日の田原克志医事課長(当時)発言、2014年(平成26年)3月8日の大坪寛子医療安全推進室長(当時)発言、さらに同年 6月10日の田村憲久厚労大臣(当時)発言で「外表異状」が確定的となったのである。
田邉昇医師・弁護士、佐藤一樹医師の全面的協力によることは言うまでもない。東京保険医協会の協力も大きなものがあった。幸運にも、ここに書き尽くせないいろいろな人々との出会いがあったおかげで、職責を果たし得たと思っている。
【イチオシ記事】朝起きると、背中の激痛と大量の汗。循環器科、消化器内科で検査を受けても病名が確定しない... 一体この病気とは...