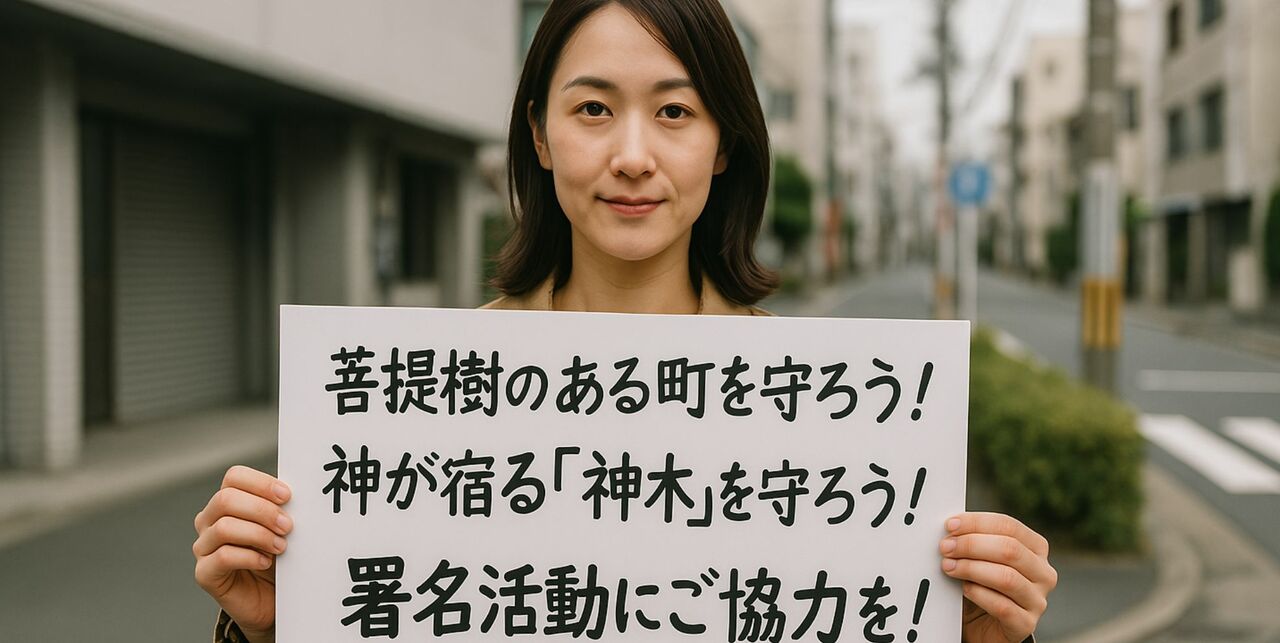【前回の記事を読む】娘が「王妃の椅子」と呼んでいた真っ白なラダーバックの椅子を譲り受け、大紅しだれ桜の下に置く
薄紅色のいのちを抱いて
桜紅葉(さくらもみじ)
夕方、夕子は残り紅葉を惜しんで大紅しだれ桜の下へ行った。
純白の椅子はポツンと置かれている。寂しそうや。山田が運んでくれた純白の椅子に座ってみる。夕子は一つしかない椅子なのに悠輔と一緒に座っているつもりになっていた。
大紅しだれ桜の残った葉は夕日に映えている。緋が夕日にさらなる緋に染まっていた。夕子の心のなかも悠輔へのおもいでさらに温かい緋に染まる。
夕子は純白の椅子に押しつけられ、悠輔の重みを感じていた。あの初夜の、かぎりなく降りしきる花吹雪の中にいるような気になる。慣れぬ喘ぎに痛さと心地良さと激しさとが綯(な)い交ぜになった心のうちが残り紅葉の真紅に染まっていくのを意識していた。
夕子は悠輔が逝ってしまってから一年、その隙間を埋めることも繕うこともできずにいた。ただ、桜の園で彼のやっていたことを無我夢中で踏襲してきたに過ぎない。
それは、まるで悠輔に抱かれているときに、彼のすべてを一滴たりとも決して逃すまいとする夕子の必死なおもいに似ていた。夕子は古稀を過ぎたというのに、未だ枯れない自身が恨めしかった。
枯れればこの人恋しさは薄れるはずなのにとおもう。
それでもこの寂しさがいつの間にか少しずつ薄れ始めていることに気づいた。夕子はその薄情さに愕然とした。ときとして孤独は心地よく、ときとして寂しかった。夕子は自分の気持ちの身勝手さにあきれた。
桜は年々歳々、忘れることなく去年より今年は、と美しさに撚りをかけてあたかも永遠に美しさが続くようにおもっているかのようだ。それが自然の強さなのかもしれない。
しかし、人間とは薄情を通り越し、薄れゆく記憶にかこつけて忘却しなければ生きていけない生き物でしかないのかもしれない。