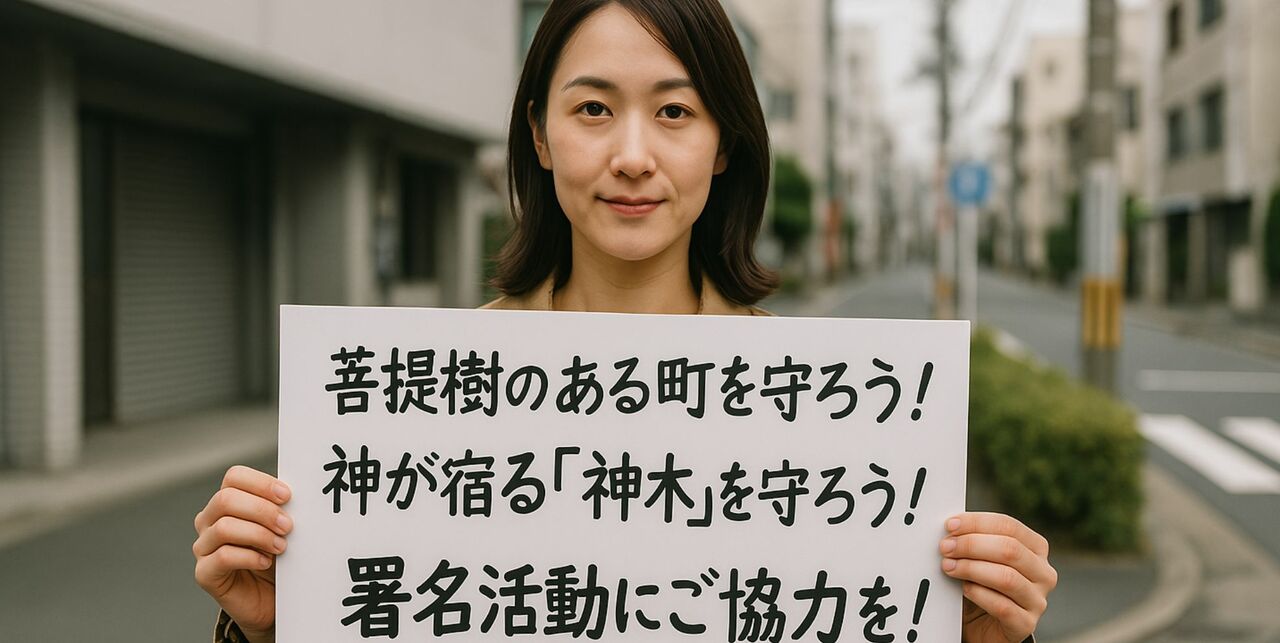【前回の記事を読む】大島桜の葉を摘みながら、ふと、手を休めて青い空を見上げると目に光が飛び込んできて…意識を失い、視界は突如闇に包まれた
薄紅色のいのちを抱いて
大島桜
保育園で誰かに言われているのかもしれない。麻美は、夕子を唯一安心して高飛車にものが言える人とおもっているのだろうか。しかし、言葉に麻美なりの心配が込められているようにおもえた。
「そやし、もう歳やさかい……ウチに来たらええんや」
「いやや、ウチはここが終の棲家とおもうとる」
「そないなこと言うてもな、身体きかんようになったら、どないしはるつもりえ。ウチの人も承知え」
「前にも言うたが、ウチはおとうはんと造った桜ん園を守って死ぬんが本望え」
(ほんまに山田が承知かわからへん。桜子に迷惑かけたらあかへん)
夕子はそんなおもいを胸に秘め、眉間に力を込めた。
「こんな広いトコ、かあさん独りや手におえへんえ」
「気張るさかい、どないかなりますやろ」
救急車の音が身近に迫った。夕子は桜子に付き添われ病院に一泊した。疲労回復の点滴がよく効いていくのがわかった。
麻美は父親の山田が迎えに来てくれることになったが、到着まで桜の園で独りぼっちなのが、夕子には心配だった。
「だいじょうぶえ、麻美、パパが来るまで留守番しとくさかい」
その大人びたしっかりした声に励まされて夕子はようやく目を閉じた。