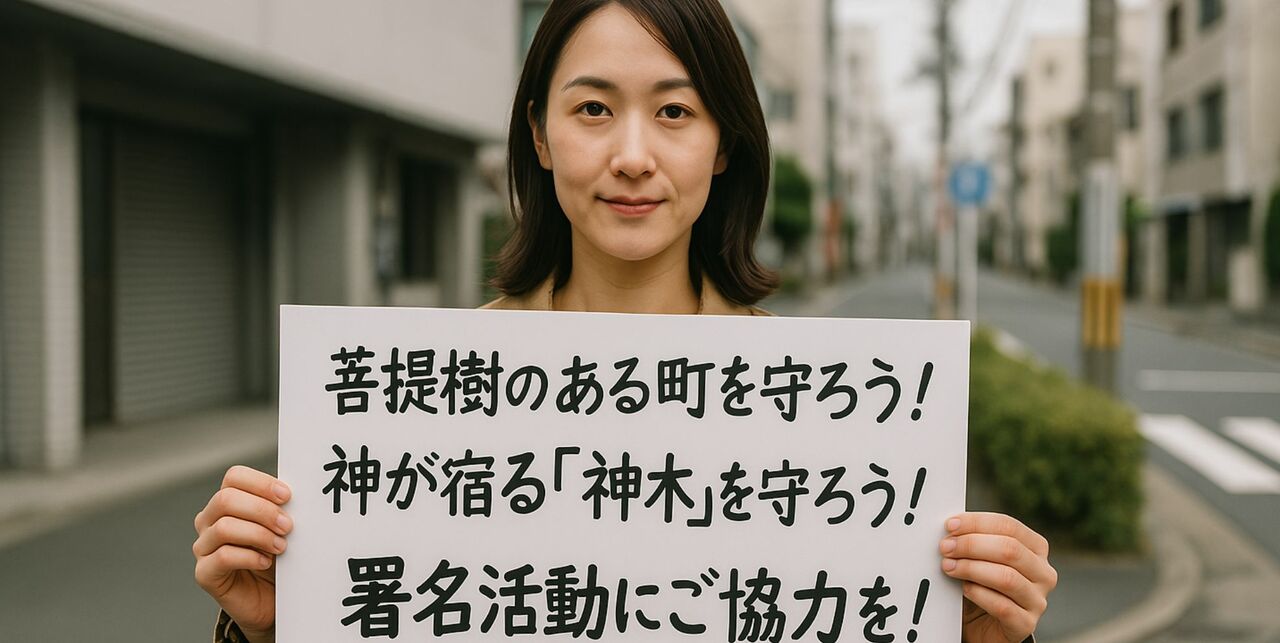少しまどろんだようだ。
夕子は起き出して、これからの桜の園の経営を考える。奥の苗畑の山桜は出荷寸前の大きさに育っている。取引先は大体、把握していたが、今のところまだ、新しい注文は来ていない。
毎年取引しているプラントハンターから来年二月に早咲きの彼岸桜の注文が来ている。夕子も悠輔も人工的開花を促すのは自然の摂理に合わないので好きではなかった。
だが昔、桜の園が細菌の大きなダメージを受けたとき、やむを得ず園全体を徹底的に消毒したことがあった。その手助けをしてくれたのが彼らのチームだった。
相身互いとその恩に報いるため、悠輔と夕子は東北の寒村にある桜村と連携を図ってきた。
「毎年のことですが、いつもみたいに彼岸桜を大きい成木で五本お願いしおす」
デパート一階の春バーゲンセールのディスプレーに使うらしい。一足早い春を演出したいという。しかし、自然に逆らった注文とわかっているから、夕子の声は小さくなる。
「待っていだす。村全体で去年の分ぐらいなんとか出荷できすよ」
元気な秋田弁が返ってきた。
数日経つと、気分はさらに良くなり、身体の奥のほうから力が湧いてくるみたいな感覚が強くなる。
夕子は朝から起き出して桜餅を作り始めた。早く悠輔の待つ仏壇に旬の桜餅を供えたかった。
冷蔵庫に保管されていた塩漬けの大島桜の葉を容器から取り出し、キッチンペーパーの間に挟んで水分を取ると、辺りに大島桜の葉の香りが満ち、夕子の心の奥に沈殿していた澱(おり)みたいなものも溶け出していくようにおもえた。
次回更新は3月29日(土)、22時の予定です。
【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…
【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...