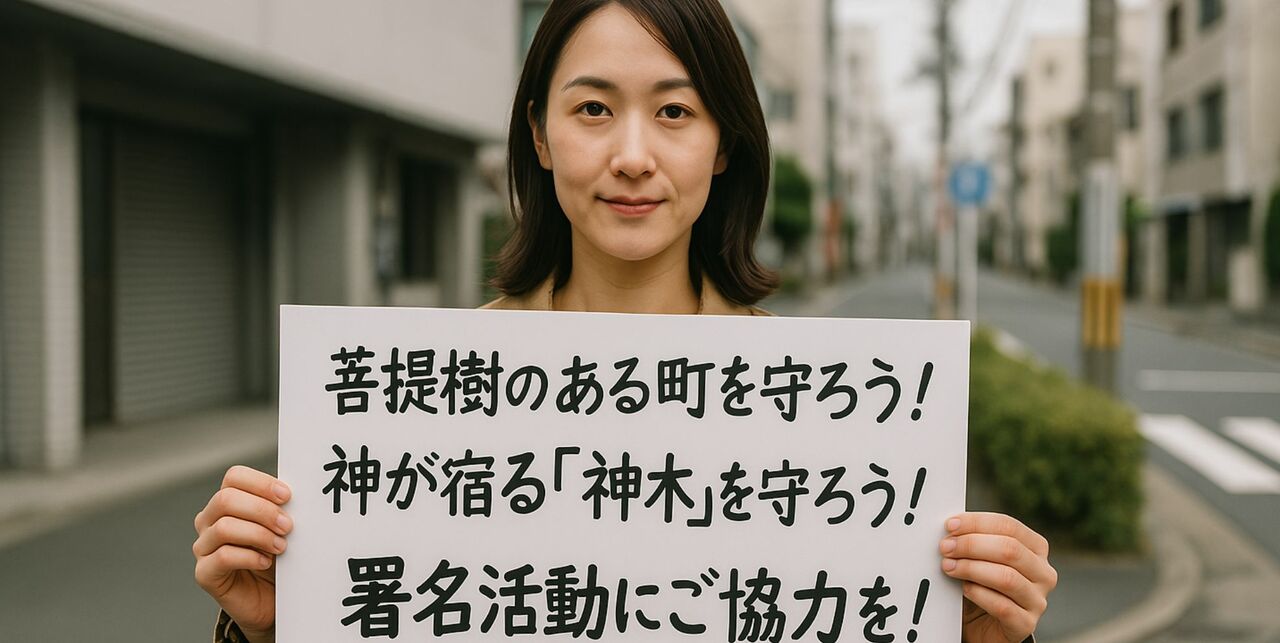【前回の記事を読む】夫の待つ仏壇に旬の桜餅を供えようと朝から桜餅を作り始める――まるで心の奥に沈殿していた澱みたいなものも溶け出していくよう
薄紅色のいのちを抱いて
葉桜
桜の園はもちろんのこと川向こうに見える丘陵も山桜が満開を競い、山が笑うとか、歌うとか、踊るとか表現される季節は過ぎていった。
「酒に酔い、肴を食らい、放歌する花見は嫌いです、花見は静かにするもんですなあ」
これは悠輔と夕子の一致した考え方だった。だから花の季節でも桜の園は静かであった。まして葉桜の季節になるとなお一層、静かになった。
悠輔は葉桜が好きというより、葉陰にできる小さな果実をいつも気にしていた。
「あんなあ、あの山桜は早咲きやけど、花色が淡すぎるよってもっと薄紅色にでけへんかなあ」
悠輔は隣で作業している夕子に呟くことがたびたびだった。
「交配して種とっておみやす。ええんが生まれるかもしれまへんえ」
夕子は悠輔の顔を覗き込んだのを覚えている。
「ほな、やってみるわ」
また幻の声が夕子には聞こえる。彼女は悠輔を超えられないのだろうか? 彼女自身独りでやれるか、自信はない。しかし、どうにかしてこの桜の園の桜守になりたい。
女桜守がいてもええのや。
あそこに行きなさったら、桜のことはすべてわかるさかい、と言われるようになりたかった。夕子は中学までしか出ていないけれど、男はんには負けしまへんえ、という密かなおもいがあった。陰でできるかぎり桜の文献を読み、研鑽を積んでいた。
雨が降り続いている。
今日でもう一週間、太陽の光を見ていない。