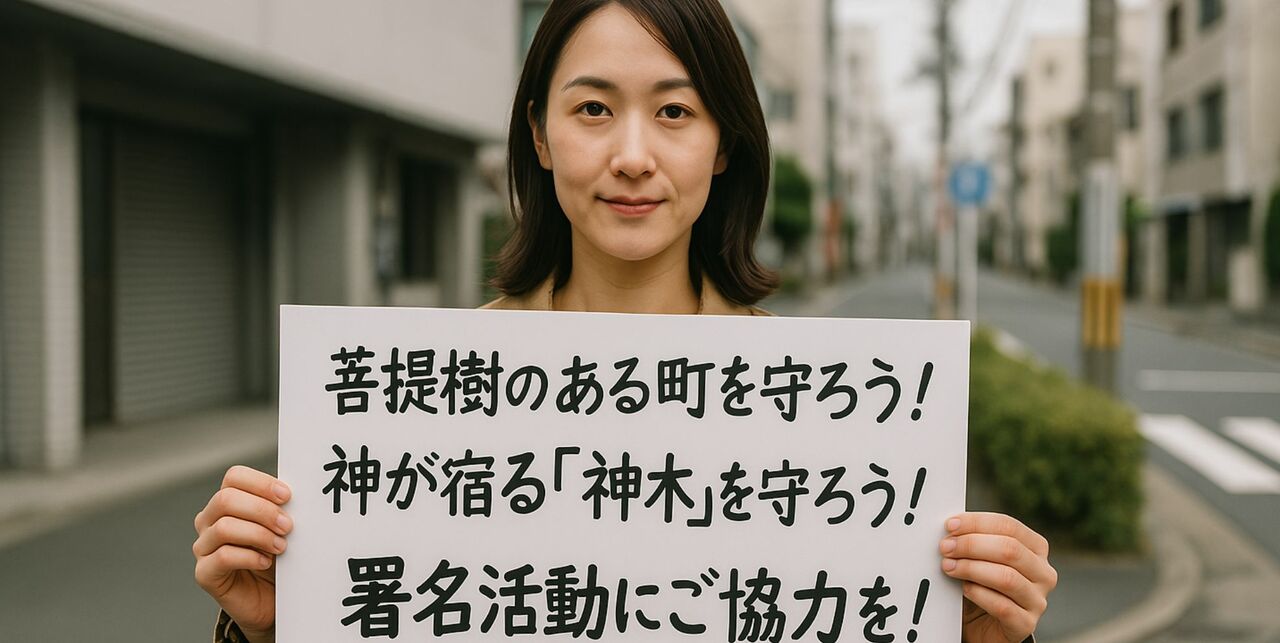落葉してすぐの秋か、花の咲く春前に出荷予定の苗木の手入れをしようとおもったが、滞っている。雨が降り続くと、病原菌が繁殖して病気に罹る苗木も出てくる。そうなると売り物にならない。
挿し穂だって腐ってしまうものもでてきたら始末が悪い。桜は病気と虫害に弱いから心配だった。
できれば、消毒薬は使いたくない。一番、効果のある消毒薬はやはり、太陽の光なのだ。桜の園の北側を東から西へ流れる川の水かさも増しつつある。このまま降り続けば、堤防が決壊するかもしれない。
夕子は悠輔から引き継いだ桜の園を水浸しにすることは忍びない。あの大紅しだれ桜の枝を支える支柱に悠輔が手斧で刻んだ傷がある。約半世紀ぐらい前、川が氾濫したときの水位を記録した印だ。五十年に一回ぐらいしか来ない豪雨だったという。ちょうど夕子が嫁いで間もないころだった。
ふたりとも若かった。毎日堆積した土砂を猫車に載せて川下の広場に運んだのを覚えている。現在でも時どき、桜の園を耕していると、五十センチ大の岩が出てくることもある。
昔の川は堤防などなかった。人が堤を造り、川の流れを強引に決めたから必要になった。だから川は大雨が降り洪水になると、元の流れを覚えていて幻の川を流れる。桜の園もかつてはこの川の氾濫原だったのだ。氾濫原は山から肥沃な土を運んできた。人は土を耕し、種を蒔き、収穫した。
「今は予測がつかんなあ。百年に一回くらい来ると言われた豪雨が毎年、どこぞにやって来るのや」
雨が降りしきる灰色の空を見上げたとき、また悠輔の声が降ってきた。
「川、氾濫するやろか? とうに危険水位を超えてるえ」