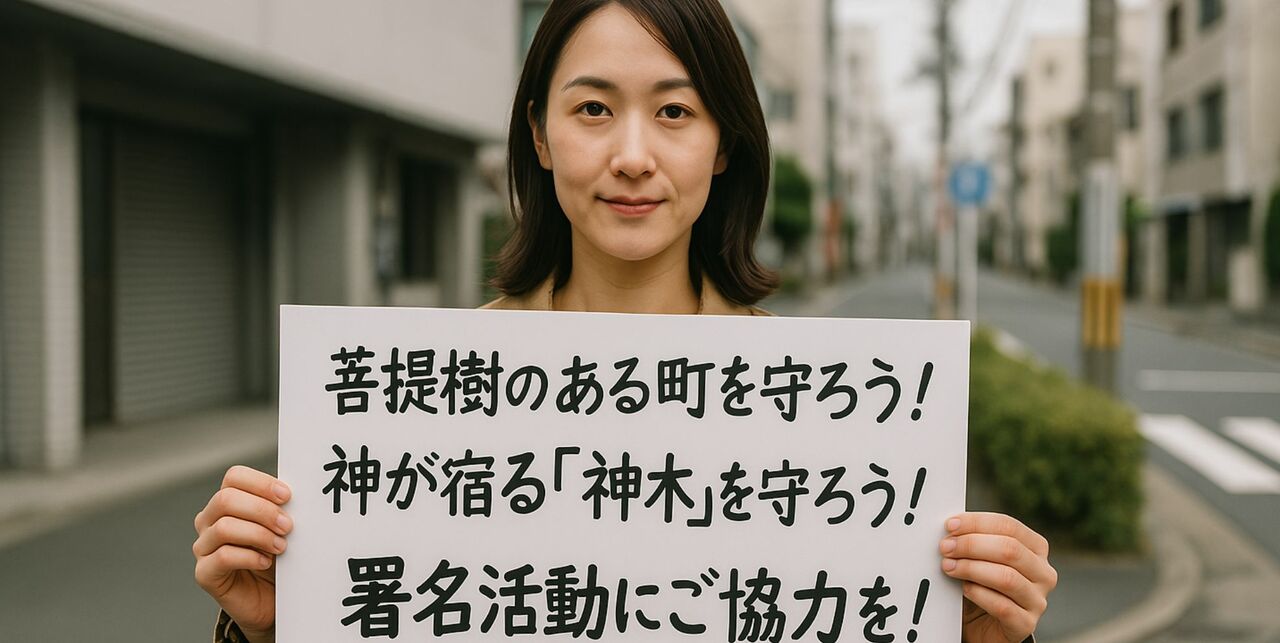【前回の記事を読む】あの日、しだれ桜がしきりに散り降る晩、とうとう夫は帰ってこなかった…よりによってその日は結婚記念日だった
薄紅色のいのちを抱いて
満開そして散り桜
夕子にとって悠輔は初めで最後の男だった。
満開のしだれ桜の樹の下での初夜。目眩くとは言えなかったが、十七歳の夕子は初めて男のぬくもりと激しさを知った。
桜の樹の下の褥(しとね)。それは中世ヨーロッパのレースの天蓋付きベッドのようだった。
ふっと、悠輔の全身が脱力したとき、夕子が薄目で見た天蓋は桜鼠 (さくらねずみ)色を闇がさらに薄めた薄紅色だった。
なぜか涙が溢れた。
大紅しだれは濃い紅色から次第に白さを増し、やがてはらはらと散る。
初夜から何日か経った。
大紅しだれ桜は散る。夕子と悠輔は月事(げつじ)がくるまで昼夜わかたず睦み続けた。
はらはら、ひっきりなしに降る花びら。地面の土色はどこにも見えない。夕子は敷き詰められた花びらの上を歩くのが忍びなかった。夕子が歩くと、花びらの褥が赤く染まるような気がしたからだった。
立ち尽くして息を飲んでいると、いつの間にか頭の黒髪も色白の夕子が似合う黒いカーデガンも薄紅色に染まり、花びらは夕子のスニーカーを半ばまで埋めた。
散る花びらに誘われたのか、そよ風が吹き始める。花びらは舞う。ひらひらと、はらはらと、そしてゆらりと。
「この桜、樹冠が弱っとったけど、おまえの手入れで治ったようやなあ」