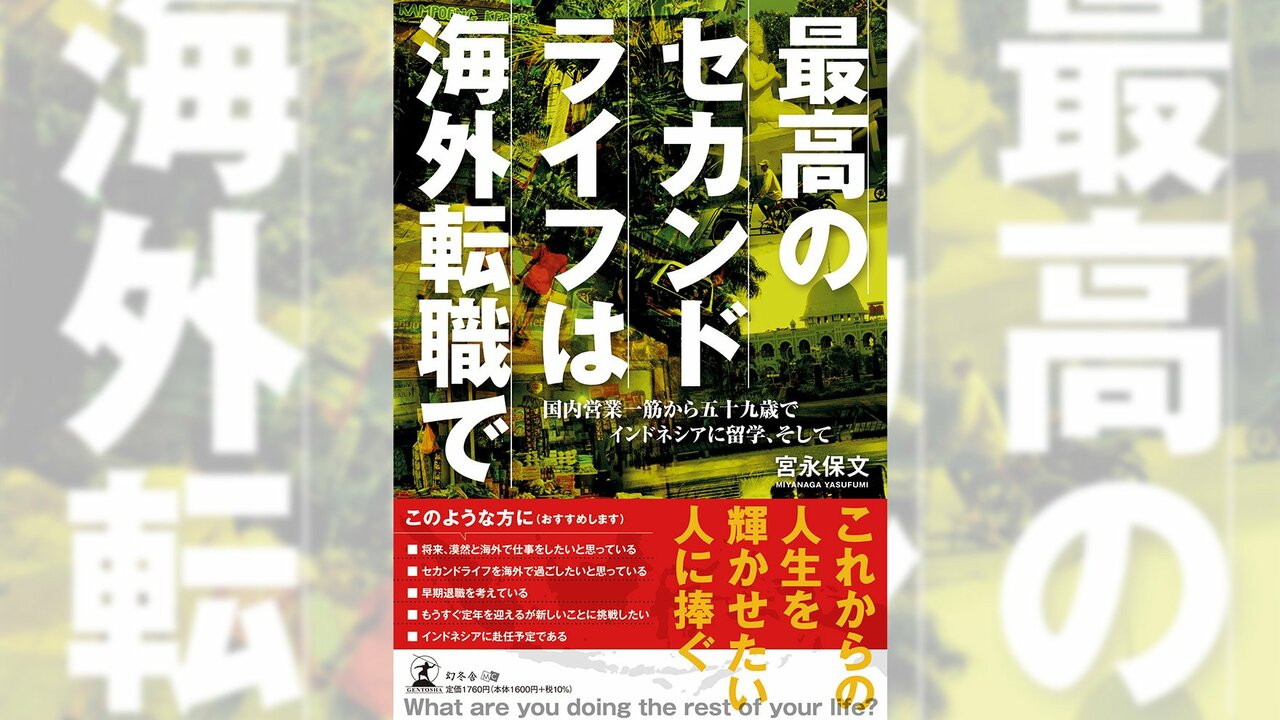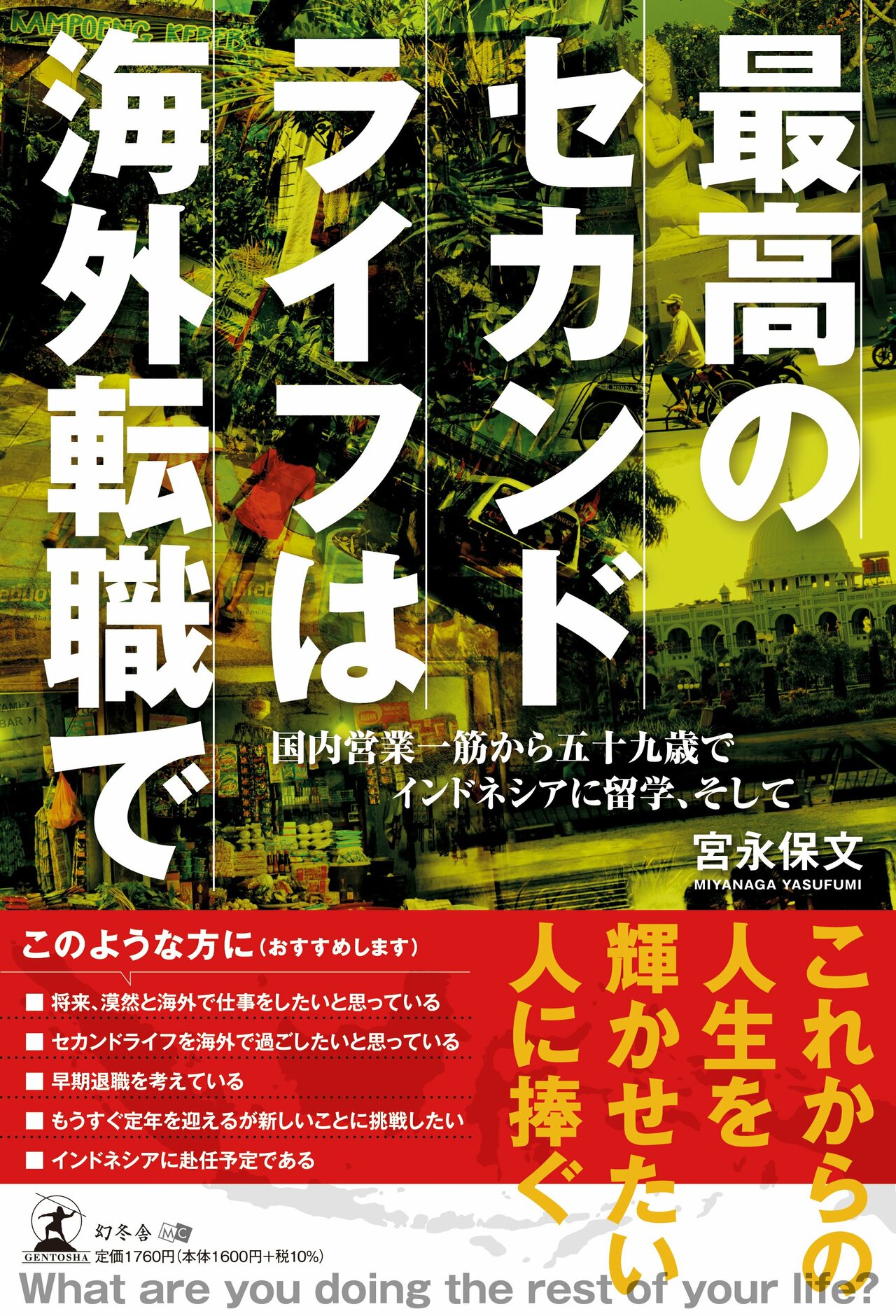【前回の記事を読む】工場には約百六十名のインドネシア人が勤務。日本人は私一人だけで通訳もいない。前工場長はすでに退職していて連絡が取れず…
第三章 還暦前の初転職
六十歳からの挑戦
要求された仕様で化粧箱と説明書の概算見積もりを提出したところ、早速、工場や設備の改造・更新を要求され、医薬品業界が守らなければならないGMP(Good Manufacturing Practice)とGDP(Good Documentation Practice)に関する研修を受けることになった。
今後の受注規模の見通し及び要求されている改善事項とそれを実現するために必要な概算投資額を日本の本社に報告したところ、日本の本社から必ず受注するようにとの指示が来た。しかし、そのためには監査に合格しなければならない。
医薬品関連の生産の場合、非常に厳しい生産環境と品質を要求されるが、勤務していた工場は医薬品のパーツを製造することが想定されていなかった。そのため、防虫、防塵対策など建物自体の大幅改修、機械・設備の新規購入、品質管理のやり方、文書管理の変更まで必要であった。
入社して間もなく、大変な難題を背負い込むこととなった。このような状況に対して、日本の本社も全面的に応援してくれ、日本から医薬品の印刷経験者、ジャカルタから日本人の品質保証責任者を長期にわたって派遣してくれた。
二〇一三年四月第一回の監査はその医薬品メーカーのシンガポールの監査チームに所属するインド人女性によってISO9001に則って行われた。しかし、私自身が品質管理の基本的なことを全くわかっていなかったので、本社の応援むなしく不合格であった。
そのあと彼女から要改善点のリストが送られてきて、それをもとにそれぞれの改善点をいつまでに完了するかの業務計画書の提出を求められた。さらに電話で進捗状況をチェックされ、できていない場合はいつまでに完了するかコミットメントを要求された。
第二回の監査はその年の六月に同じ監査チームに所属する中国人女性によって行われた。しかしcalibration(測定機器の校正)について質問されたが、情けないことに私自身がcalibrationを「銃の口径」の意味しか知らなかったため、質問が理解できず、うまく答えることができなかった。
そのうえ、抜き取り検査のサンプリング方法やチェックリストの記入方法が基準を満たしていなかった。さらに万全を期したはずの5Sでも天井の壁の隅に蜘蛛の巣が見つかったり、監査中に工場の中に蠅が入ってきたりで、散々な結果となってしまった。