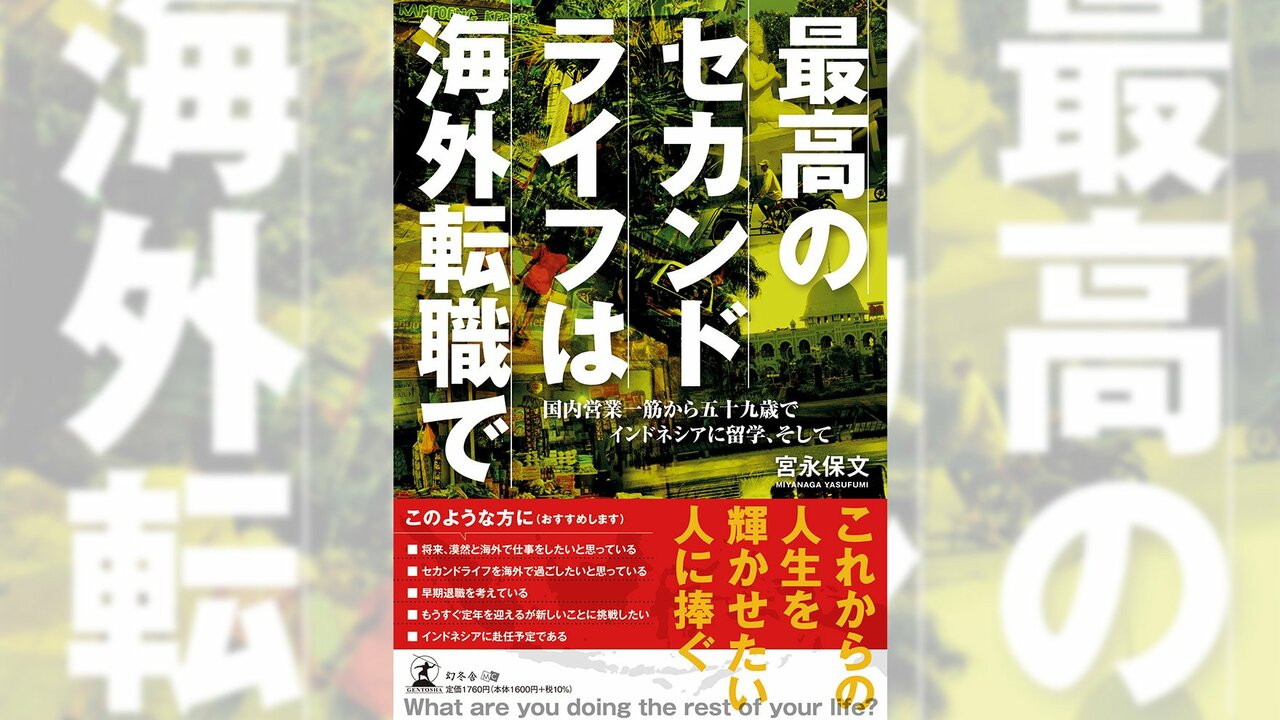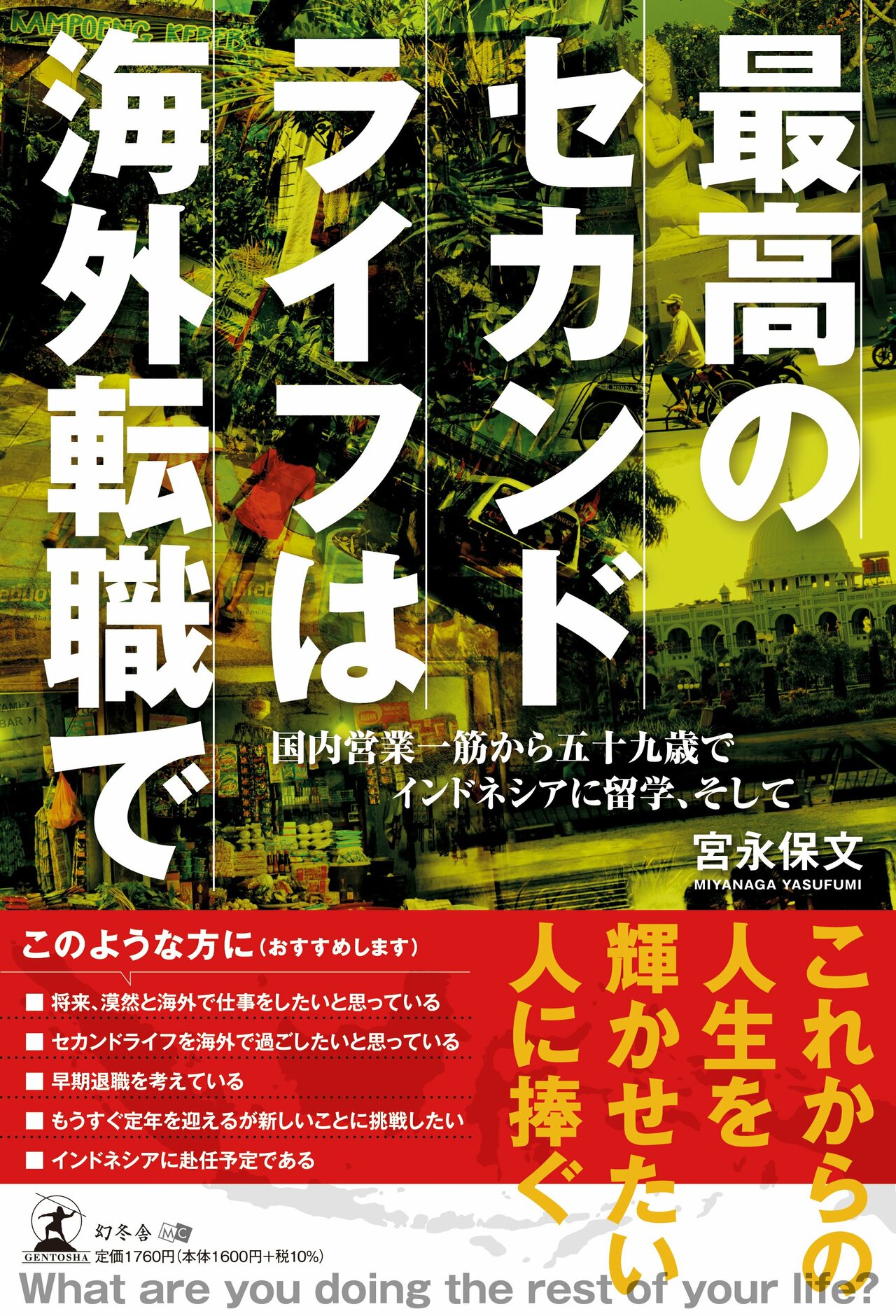【前回の記事を読む】医薬品メーカーから新しい仕事の打診でGMPとGDPに関する研修を受け監査へ。第一回と第二回は不合格。最終となる第三回を迎え…
第三章 還暦前の初転職
先鋭化する労働組合と急激な賃金上昇
私の勤務していた時期、二〇一二年から二〇一六年にかけて、インドネシアでは大幅に賃金が上昇した。特に私が勤務していた工場があるパスルアン市では、生産性の上昇を無視して毎年最低賃金が二十~四十パーセントずつ上昇し、さらに、地方条例で業種別賃金の上乗せがあった。
その結果、勤務していた四年間で最低賃金は実に二・五倍になった。他の社員もある程度最低賃金に連動して賃上げせざるを得ないため、労務費は最低賃金にほぼ比例して上昇した。
当時、インドネシアでは、金属労協を中心に労働組合が先鋭化して、大幅な賃上げを求め、大規模なストライキやスウィーピングというデモやストライキへの参加強要が発生するようになった。自治体も人気取りのためか大幅賃上げを認め、さらに当時のユドヨノ大統領もそれを容認する方針であった。
また、工業団地内では今まで組合がなかった日系の工場まで次々と組合が結成され、デモやストライキが頻繁に発生した。
二〇一六年、ジョコ・ウィドド大統領は、このまま労働組合の要求通り大幅な賃上げが続いていけば、経済的に大きなダメージを受けると判断し、物価上昇率をベースにした賃上げガイドラインを発表し、地方自治体に協力を求めた。その結果、二〇一七年度は常識的な十パーセント強の賃金上昇に落ち着いた。
しかし、賃金がすでに高水準となったうえ、就労ビザの要件も頻繁に変更され、一時のような外資企業の進出ラッシュはなくなり、パスルアンの工業団地でも新たに進出してくる工場もあったが、撤退する工場もあり、売れ残った状態が続いた。
わが工場との取引額が上位の日系企業の得意先も、インドネシア現地法人の大規模なリストラにより取引額が十分の一以下となった。もし、外資系医薬品メーカーの受注を取れていなければ、わが工場も大変なことになっていた。新しい顧客を獲得するのは多くの時間とエネルギーがかかるが、失うのは一瞬である。