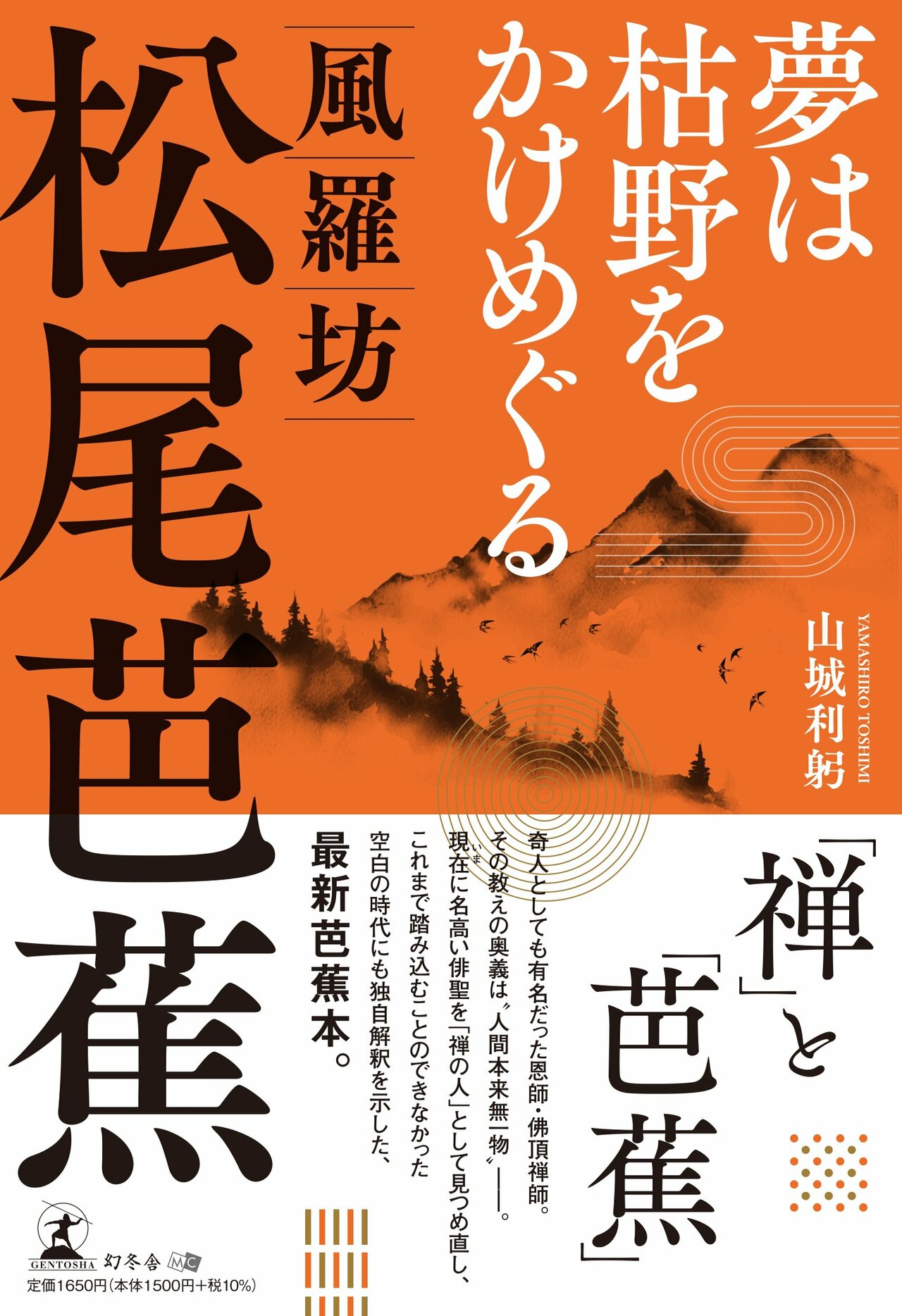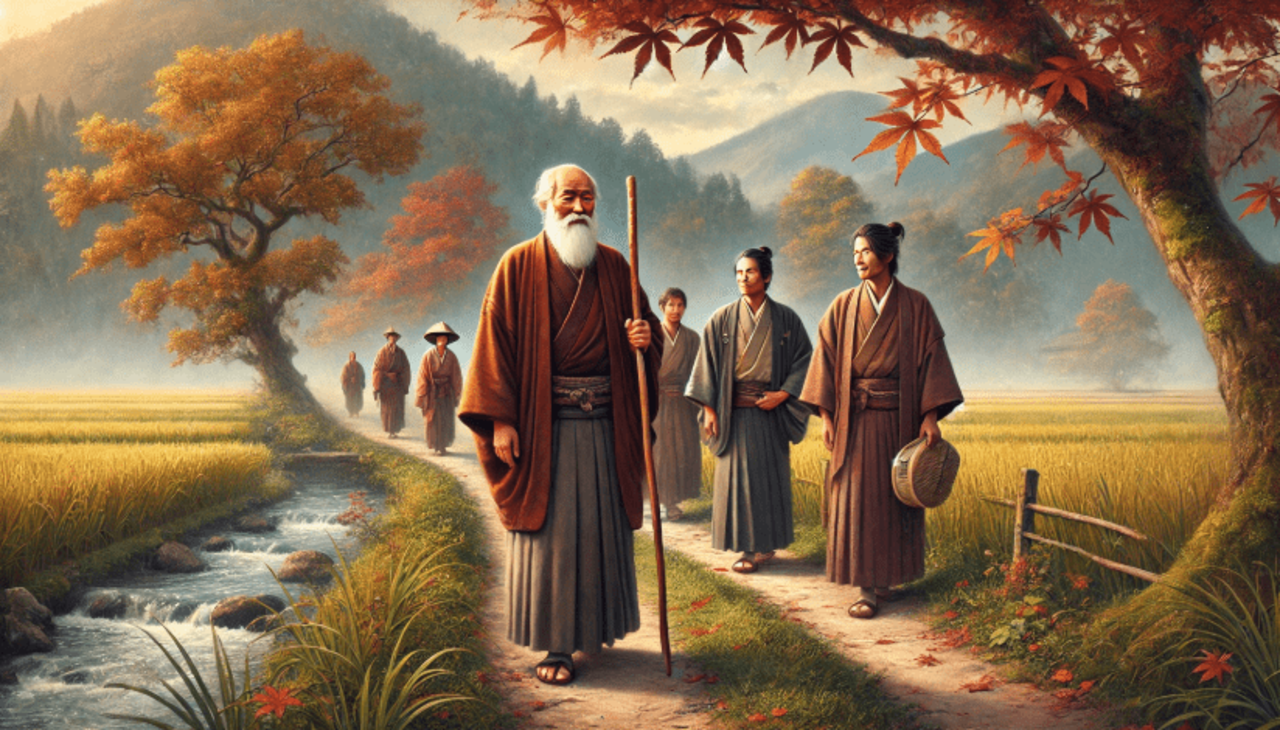後記
松尾芭蕉の生涯を追いかけていて、その経歴に、特に四十歳以前のことで、不明な点が多い。個人的な事柄については、固く口を閉ざしていたとすら思える。私は、不正確を恐れながらも、前後の事実から類推して、自分で納得できるストーリーで繋いでみました。
藤堂蝉吟との関係は、事実からそれほど離れてはいないと思っています。一番のクライマックスは、深川芭蕉庵へ転居して、「野ざらし紀行」の旅に出る五年間に、芭蕉の内面に何が起こったかという事です。
和歌における西行、連歌における宗祇のように、俳句の世界を古典文芸共通の価値観〝わび・さび〟の世界まで昇華させることを目指しながら、現実には、日常の風景に沿った俳句作りをする。自らは、一風羅坊として生涯を貫く。
「野ざらし紀行」から始まる、旅の風雨に身をさらし、その中で新しい俳句の世界を確かめ歩くときの、あの雲水に似たスタイルは、行雲流水に修行中という、自らに課した理念ではないかと思います。
四十歳前後の芭蕉に一大決心をさせ、それ以降〝行脚餓死は本懐〟の境地にまで心を導いたものは何か。これは禅宗の基本理念に見られるとおもいますが、〝人間本来無一物〟の悟りかと思います。芭蕉は見事、俳句以外は一切放下をつらぬきます。食がなければ死んで結構。この気構えが人格的に多くの人に尊敬される要因の一つになっています。
【イチオシ記事】ずぶ濡れのまま仁王立ちしている少女――「しずく」…今にも消えそうな声でそう少女は言った
【注目記事】マッチングアプリで出会った男性と初めてのデート。食事が終わったタイミングで「じゃあ行こうか。部屋を取ってある」と言われ…
【人気記事】「また明日も来るからね」と、握っていた夫の手を離した…。その日が、最後の日になった。面会を始めて4日目のことだった。