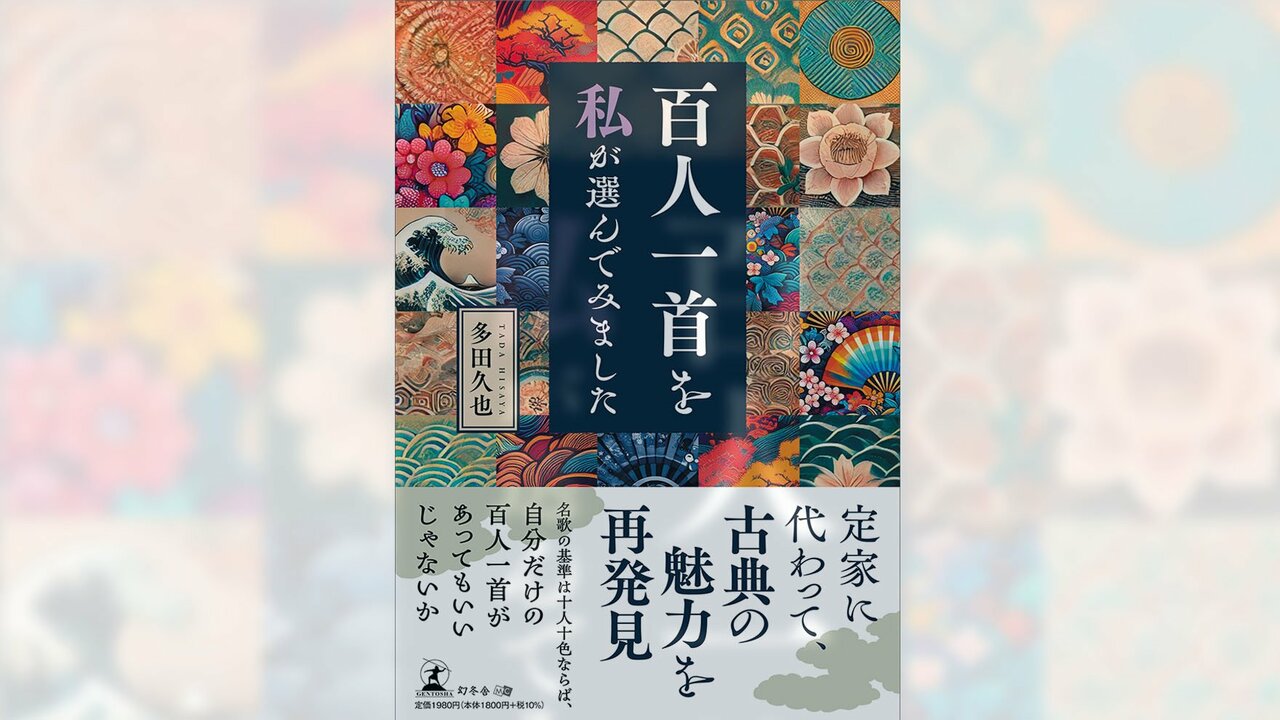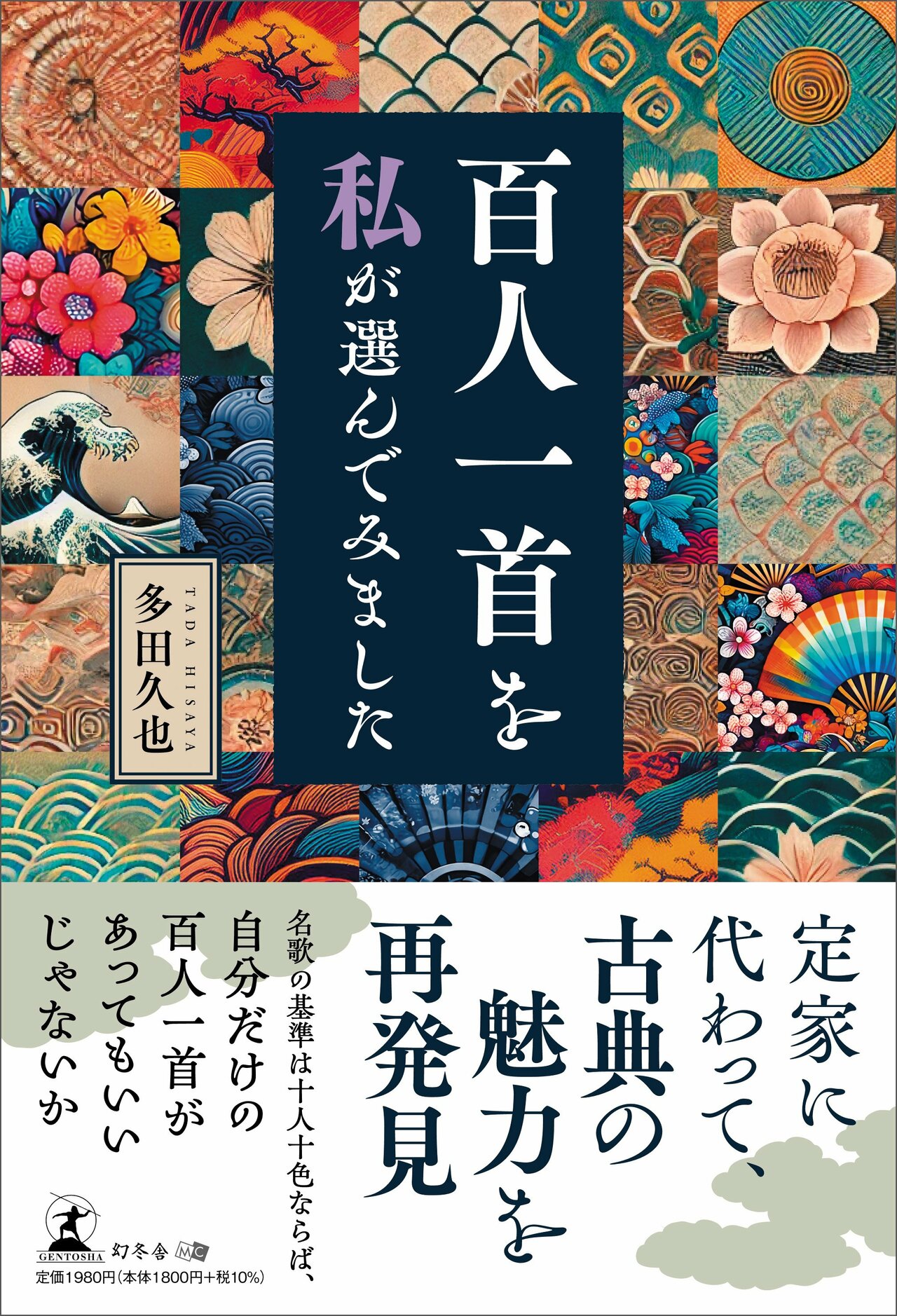2 持統天皇 (六四六~七〇二)
北山にたなびく雲の青雲(あをくも)の星離れ行き月を離れて
持統天皇は天智天皇の第二皇女で、十三歳の時、天智天皇の弟、つまり自分の叔父にあたる大海人皇子(後の天武天皇)に嫁いだ。
天智天皇崩御後、夫とともに吉野へ逃れ、壬申(じんしん)の乱で大友皇子に勝利した夫が即位してからは、常に天皇を助け政事について助言した。壬申の乱も持統天皇こそが首謀者であるという説もあるほど、性格は男まさりで非情冷徹であったらしい。まさにこの二人は史上最強の夫婦といってもよい。
天武天皇崩御のすぐ後に、わが子草壁皇子のライバルで異腹の兄弟・大津皇子を誅殺(ちゅうさつ)している。しかし、頼みにしていた草壁皇子はすぐに亡くなってしまい、四十六歳の時自ら皇位を継承し女帝として君臨、六九四年、飛鳥から藤原京へ遷都した。
持統天皇は大宝律令を編纂させ、律令制度を確立し、暦を制定するなどの大きな業績を残している。六九六年、孫の文武天皇に譲位し、史上初の太上(だじょう)天皇となる。持統天皇の時代にはじめて「日本」という国号が正式に発令され、「愛国」という言葉も使われたという。
これは、いわゆるナショナリズムのことで、ヨーロッパでは十九世紀以降の現象であるから、古代の日本はいかに先進的であったかと驚くばかりだ。また、現代でも続いている伊勢神宮の式年遷宮は、持統朝のときに始められた儀式である。このような偉大なる女帝が、普通のひとりの未亡人として、夫を失った悲しみを涙しつつ詠いあげたのがこの哀傷歌なのである。
持統天皇の御製は四首残されている。
飛ぶ鳥の明日香の里を置きて去(い)なば君があたりは見えずかもあらむ
(明日香の里をあとにして藤原京へ行ったならば、亡き天武天皇が埋葬されている大内陵(おおうちのみささぎ)を見ないで過ごすことになるのであろうか)
藤原京遷都の際、途中で神輿を停めて儀礼が行われたときに詠んだ御製である。これもまた、亡き夫を偲ぶ内容になっている。究極の夫婦愛を見る思いがする。
小倉百人一首
春すぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山
(春が過ぎ去り、夏が来たらしい。民が白い衣を干すという天の香具山が見える)