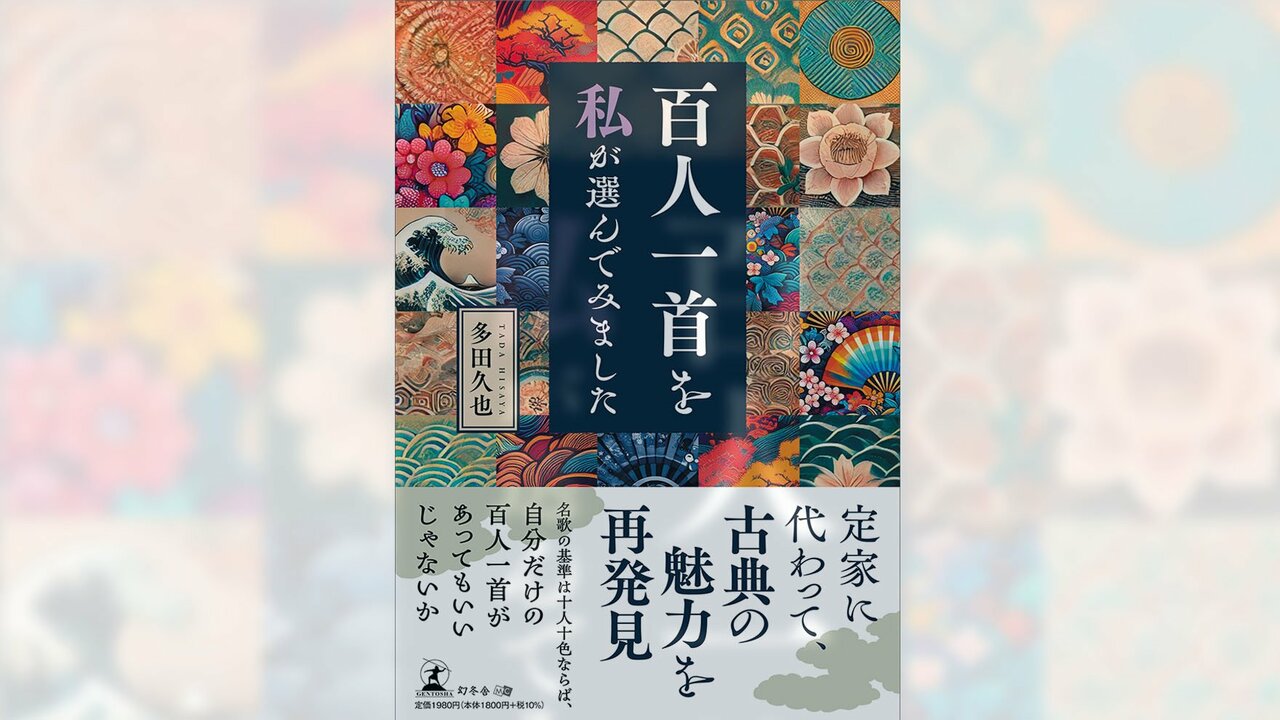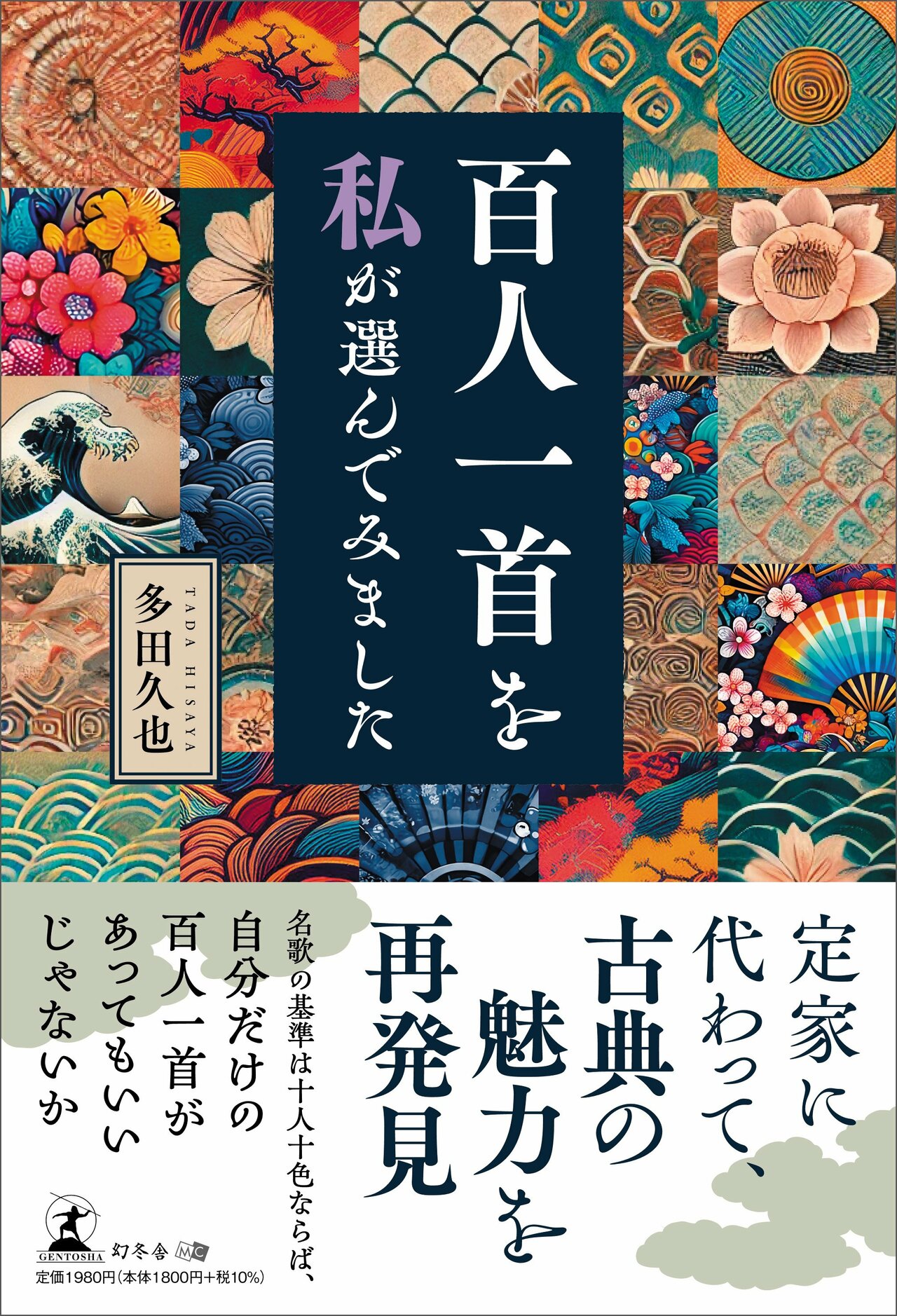【前回記事を読む】万葉集に秘められた歴史と歌の真実──人麻呂の死刑説と志貴皇子の清冽な歌に込められた深層を探る
6 山部赤人(生没年不詳)
若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴(たず)鳴き渡る
(若の浦に潮が満ちてくると干潟がなくなるので、葦の生えている岸辺を目指して鶴が鳴き渡っている)
聖武天皇が紀の国に行幸したときの歌である。
若浦とは和歌浦のこと。ひたひたと満ちてくる波の音を聞きながら向こうの方を眺めると葦の原が拡がっている。そこへ、鶴の群れがしきりに鳴きながら渡ってくるのである。目の前の風景をそのまま詠ったような感じだが、なぜか心に沁みる。人麻呂の歌と同様、思わず口に出して詠んでみたくなる歌だ。
赤人の経歴は全く不明だが、聖武天皇の行幸にお供して歌を詠ずる宮廷歌人であったと考えられている。
赤人は人麻呂と並び称された歌仙である。たとえば、紀貫之が書いた『古今和歌集』仮名序には、人麻呂と赤人は甲乙つけがたいと記されている。大歌人の大伴家持でさえ、自らの歌才が「山柿の門」に到達できないとまで書いている。ここでの柿は人麻呂、山は赤人を指している。
赤人の個性は人麻呂とは全く異なる。人麻呂は雄大に情念を吹き出して人の心を揺さぶるが、赤人は美しい自然の事象を清らかに歌い上げることが多く、清澄で透明感のある歌が特徴だ。赤人の湧き上がった感情はむしろ、己の心の内へ内へと向かうようである。
清川妙は「彼の歌は小さな物へと目をとめ、かぎりない愛をそそぐ。彼はなつかしさをたたえた人である」と評している。勅撰入集は五十首ほどある。
次の二首も赤人らしい歌だ。
ぬば玉の夜の更けゆけば久木生ふる清き川原に千鳥しば鳴く
(夜がしんしんと更けるにつれて、久木の生い茂る清らかな川原で千鳥がしきりに鳴いている)
これも聖武天皇の吉野離宮行幸にお供した折献上した歌である。「久木(ひさぎ)」は赤芽柏(あかめがしわ)とも、きささげともいわれる。