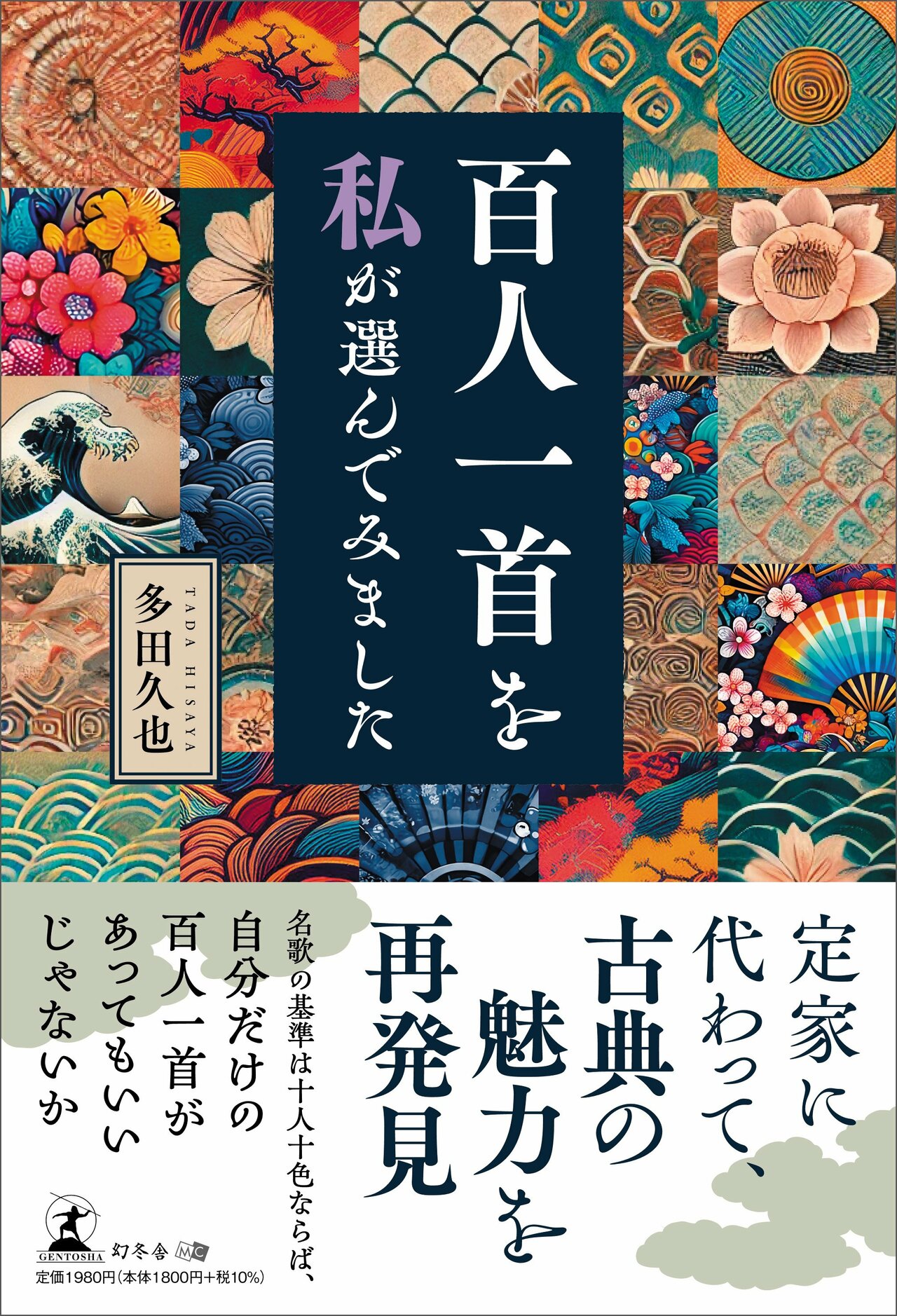春の野にすみれ摘みにと来し我れぞ野をなつかしみ一夜寝にける
(春の野にすみれの花を摘もうとやってきた私は、野辺の美しさに心引かれて、ここでつい一夜を明かしてしまった)
すみれの花は摘み取るとすぐ萎えてしまうので、古人は、花の生命力が摘み取った人の魂に移ると考えていたという。この歌に関して、斎藤茂吉は、すみれを摘み取るのはほかの若草と共に食用とするためだった、と述べている。
一方、すみれを薬草として食べていたとする説もある。すみれにはルチンが含まれており、止血剤にもなるが、高血圧にも効果があったという。もし、赤人という名前が、文字通り紅い顔をしていたことからつけられたならば、なるほど赤人は高血圧だったのかもしれない。
小倉百人一首
田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ
(田子の浦に出てみたら、真っ白な富士山の高嶺に、しきりに雪が降り続いているよ)
7 大伴旅人 (六六五~七三一)
我が園に梅の花散るひさかたの天(あめ)より雪の流れ来るかも
(このわが園に梅の花がしきりに降る。その白い花びらは天から流れてくる雪であろうかと思われるばかりに)
天平二(七三〇)年正月十三日、大宰帥(だざいのそち)大伴旅人邸の梅園で梅花の宴が催された。公式行事の後の和やかな酒宴であった。
招かれたのは大宰府の官人、遠国の出張役人、山上憶良・沙弥満誓らの友人など三十二名で、宴席では三十七首の歌が詠まれた(『万葉集』八一五~八五二番)。
掲出歌は八二二番、大宰府長官自ら詠ったもので、白い梅の花びらが天より雪のように流れてくると表現している。雪のように「降ってくる」でもなく「落ちてくる」でもなく、「流れてくる」としたところに旅人らしい歌才が表れている。
正月十三日は、梅が散るにはやや早いという厳しい指摘も見られるが、旅人が見た幻想と思えば、さらに歌の魅力は増す。