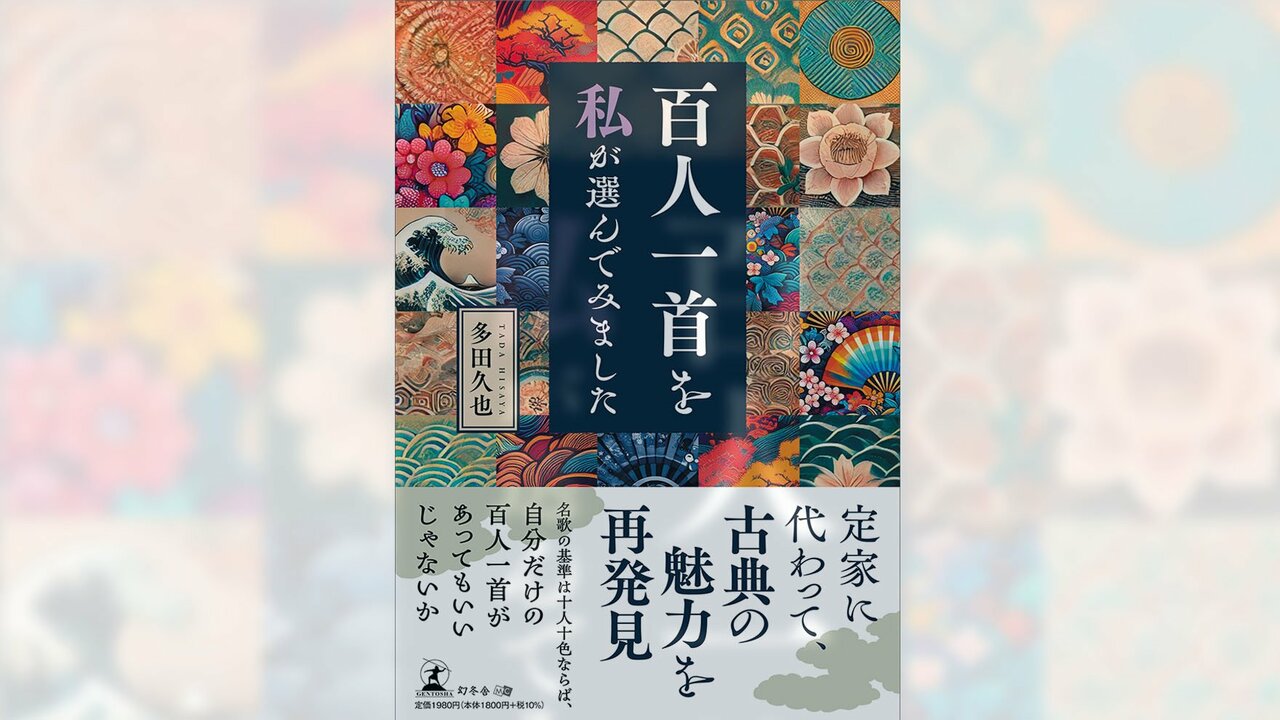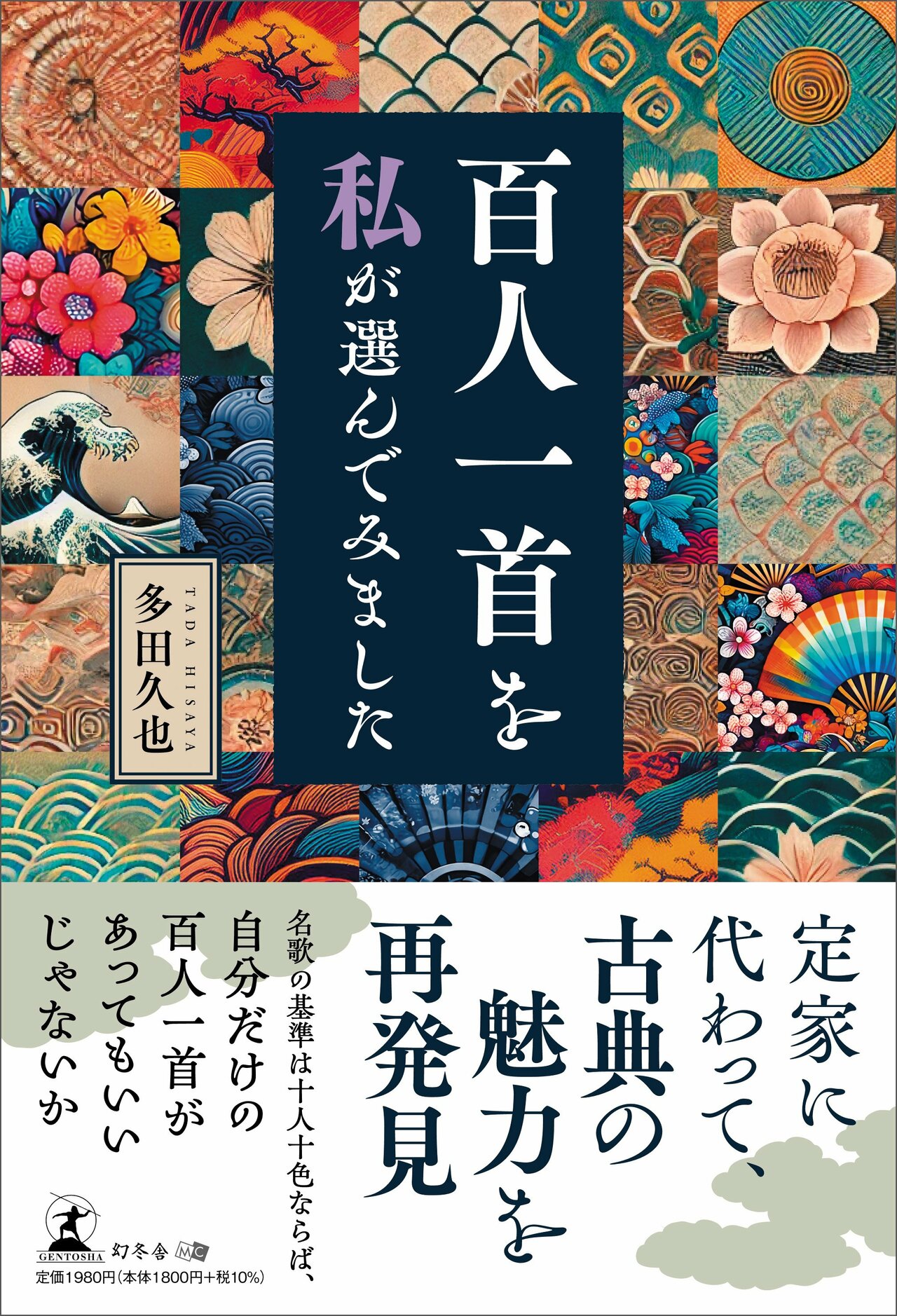【前回記事を読む】兄、天智天皇に引き裂かれた二人の恋人たち。冷めぬ愛は偽装され、歌となって思いを届ける。
4 柿本人麻呂 (生没年不詳)
これに対し、梅原猛は『水底の歌――柿本人麿論』で大胆な論考を行っている。人麻呂は高官であったが政争に巻き込まれ、島根県益田市(旧・石見国)の沖合で死刑に処されたとする「人麻呂流人刑死説」を唱えた。
また、人麻呂が、伝説的歌人・猿丸大夫(さるまるのたいふ)と同一人物であることも指摘した。著者である梅原猛の論理が極めて明快なので、私はこの説に納得した。
梅原猛は斎藤茂吉が提唱した人麻呂終焉の地を舌鋒鋭く否定し、茂吉に対しても仇敵を罵倒するかのごとく激しい批判を加えていたことに驚いた。歴史ミステリーとして読んでも面白い本である。
小倉百人一首
あしひきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む
(夜になると雄と雌が離れて寝るという山鳥だが、その山鳥の長く垂れ下がった尾のように長い夜を、私もまたひとり寝ることになるのだろうか)
5 志貴皇子(生年不詳~七一六)
石走(いはばし)る水垂(たるみ)の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも
(岩にぶつかってしぶきをあげる滝のほとりのわらび、今こそそのわらびが芽吹く春になったのだ)
春の到来の喜びを詠った歌である。「石走る」は「垂水」の枕詞で、「垂水」は滝のことだが、それほど大きい滝ではないような感じがする。
石の上を流れる清々しい水も、滝の音も、水しぶきに濡れる緑のさわらびも、春の到来にふさわしい情景である。上句の「垂水の上のさわらびの」の、「の」の音の重複が気持ちよいリズム感作っている。
下句は大らかなたっぷりとした詠いぶりで、皇子にふさわしい品格が感じられる。なお、さわらびは初春ではなく仲春になって生えるので、春の到来の喜びとは多少時期的にずれているかもしれない。
ところで、山形県の田舎に育った私は、わらびのおひたしや味噌汁が好物なのだが、わらび採り名人に話を聞くと、わらびは山の日当たりの良い斜面に生えていて、滝のほとりのような湿地に生えるものではないという。
こういう観点からすると、この歌は写実的に実景を詠んだものではなく、春という主題を観念的に詠んだ歌として捉えるべきと考えられる。