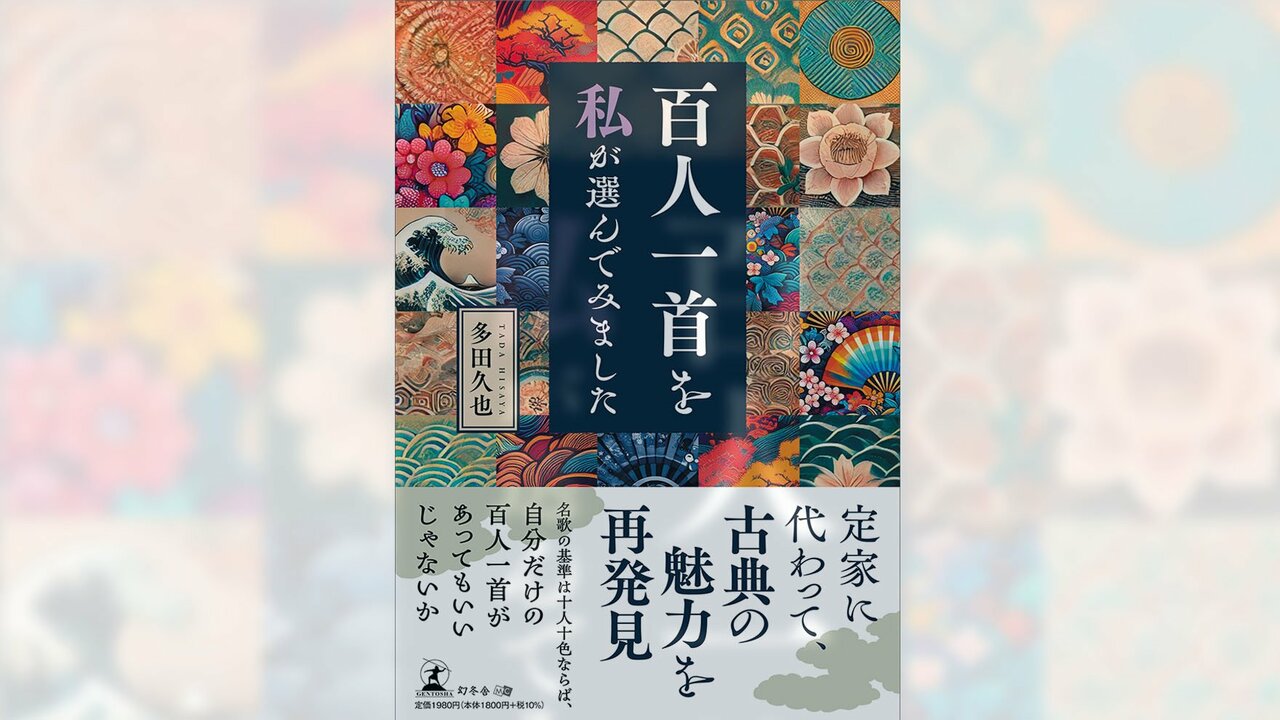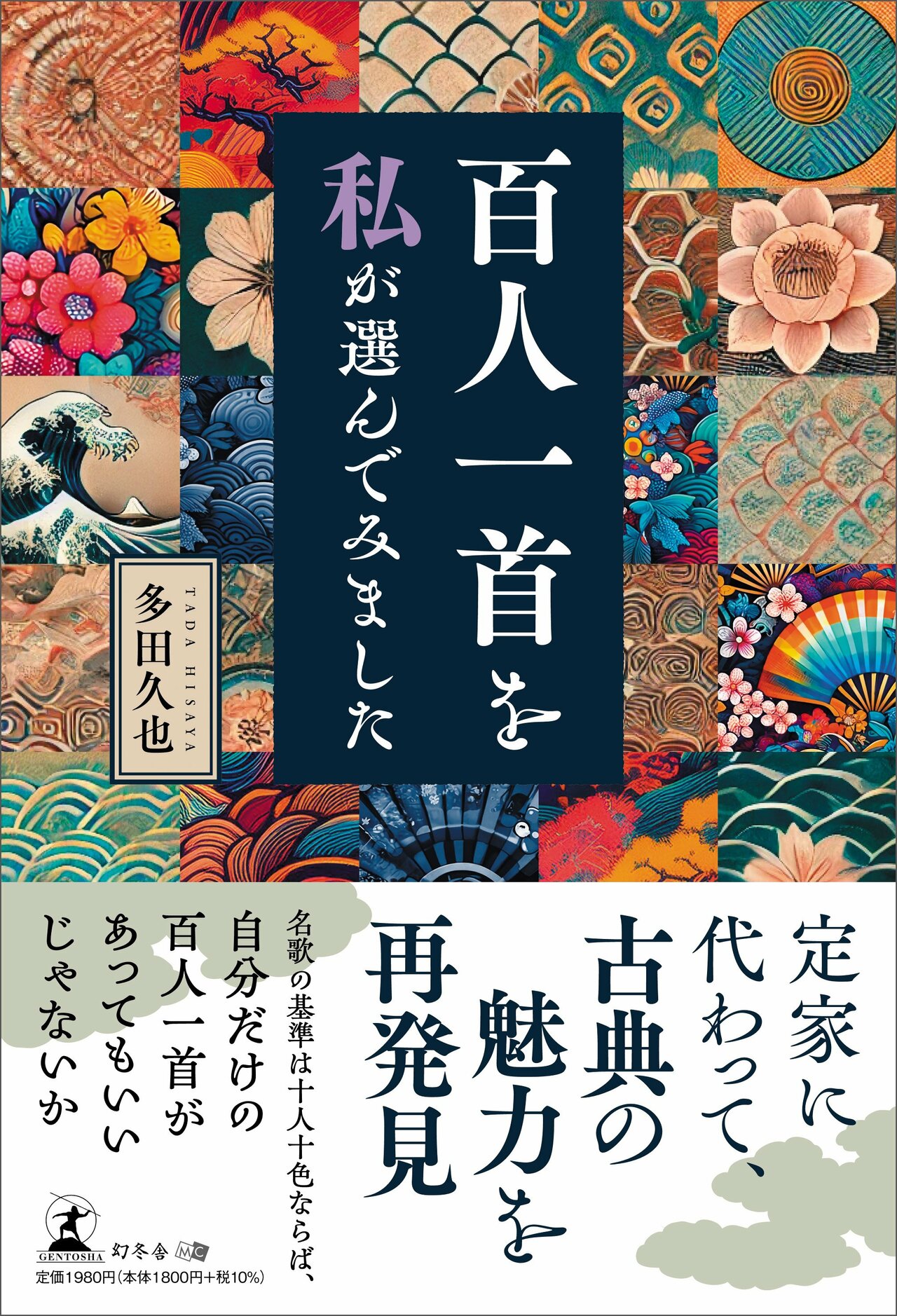【前回記事を読む】「弟の愛した女性を兄が奪い取った」「夫を実の父に殺される」…絶世の美女・額田王と天智天皇、天武天皇の三角関係がもたらした悲劇
3 額田王 (生没年不詳)
大海人皇子はただちに答えた。
紫草(むらさき)のにほへる妹(いも)を憎くあらば人妻ゆえに我(あ)れ恋ひめやも
(むらさきのように美しいあなたが好きでなかったら、人妻と知りながら、私はどうしてあなたに心ひかれたりしようか)
堂々とした返歌だ。しかも、兄の天智天皇に対する宣戦布告のような、実に濃厚な恋歌である。ところが、この贈答歌は『万葉集』の「相聞」ではなく、巻一の公的な場での歌「雑歌」に入れられている。さらに、このとき額田王はもう三十五歳ぐらい、大海人皇子は四十歳ぐらいで、当時としてはもうかなり年配であったらしい。
これらのことから、実際の状況は、濃厚な相聞歌の贈答というよりも、狩りの後のにぎやかな宴席での座興のようなやりとりであったと考えられている。しかし、天智天皇の同座の中で、単なる戯れだけの歌のやりとりだったのだろうか。
私にはそうとは思えない。天智天皇に引き裂かれたかつての恋人同士は、ユーモアで偽装しながらも、この歌で消えやらぬ愛を交わしたのではないだろうか。単なる座興では片づけられない深奥の揺らめきを感じざるを得ないのである。
額田王の『万葉集』初期の代表的な一首、
熟田津(にきたつ)に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな
(熟田津で船出をしようと月の出るのを待っていると、月も出て、潮の具合も良くなった。さあ、今こそ漕ぎ出そう)
百済救援に赴くため、日本国の軍団が伊予の熟田津から筑紫へ船出するとき、船団の出発を宣言した歌である。暗い海に月の光が射し、潮も満ちてきた情景を前に、船団の軍人を高らかに鼓舞した凜々しい響きがある。
作家の井上靖は、額田王を主人公にした小説『額田王』を書いた。その中で、額田王は巫女的な役割をしたと解釈され、神秘的で妖艶な女性として叙情豊かに描かれている。推薦したい一冊だ。
4 柿本人麻呂 (生没年不詳)
近江(あふみ)の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ
(近江の琵琶湖の夕暮れの波間に群れ飛ぶ千鳥よ、鳴かないでおくれ。おまえが鳴くと私の心もしんみりと哀しみにしおれ、遠い昔のことが思われてならない)
ダイナミックで流れるようなリズムに陶然とするばかりである。何度も声に出して読みたくなる歌だ。「近江の海」は琵琶湖のことである。
「夕波千鳥」は人麻呂が造った詞(ことば)で、夕波に群れたわむれる千鳥のことを表している。
昼の輝く潮の光が、夕方になるにつれて弱くなり薄暗くなってくると、波間に漂い遊ぶ千鳥の姿も見えにくくなり、千鳥の声が哀調を帯びて心を揺さぶってくる。そんな情景がありありと目に浮かんでくる。