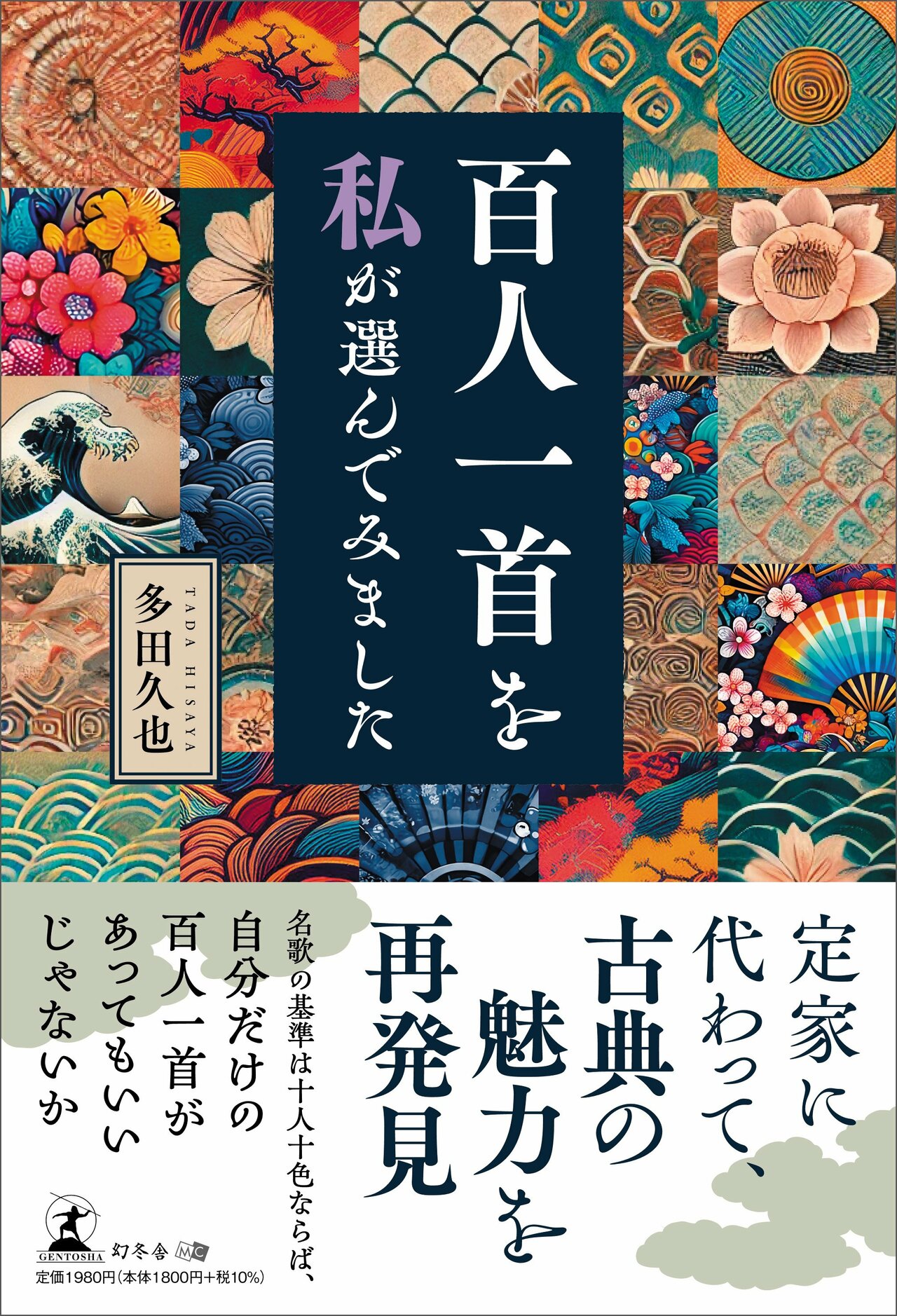持統天皇の時代の都は藤原宮であるが、持統天皇に仕えた人麻呂が天智天皇の近江大津宮を訪れたとき、この旧都は壬申の乱で焼き滅ぼされた荒都であった。下句は、その古の栄えた昔のことが悲しくも懐かしく思い出されるという内容である。
人麻呂は『万葉集』を代表する大歌人である。持統・文武天皇に仕える宮廷歌人として、公的な儀式の歌や皇子らの死を悼む挽歌などを格調高く詠いあげた一方、私的な和歌にも叙情溢れる名歌が多い。
和歌の神として尊崇されており、兵庫県明石市、島根県益田市などには人麻呂を祀る神社まである。勅撰入集は二六〇首ほどある。人麻呂の歌風は一種独特で、豊穣な情感がひた押しに押してくるような迫力と、人の心を揺さぶる雄大な風格を備えている。
東(ひむがし)の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月かたぶきぬ
(東の原野に曙の光がさしそめて、振り返ってみると、月は西空に傾いている)
帝位を踏まずに亡くなった草壁皇子の皇子である軽皇子(後の文武天皇)が、父ゆかりの地へ狩りに出かけたときの歌である。たくましく成長した軽皇子の即位は間近で、持統天皇の長年の悲願はもうすぐ叶うのである。
昇る太陽に軽皇子、沈む月に草壁皇子を喩え、新しい時代への希望と栄光を祈るとともに、無念であった草壁皇子に心を寄せている。歌は一見渾雄(ゆうこん)ですばらしい叙景歌であるが、このような意味が含まれていることを知ると、さらに感動は深まる。
天(あめ)の海に雲の波立ち月の舟星の林に漕ぎ隠るみゆ
(大空の海に雲の波が立って、月の舟が、きらめく星の森の中に漕ぎ隠れてゆく)
この幻想的な歌も好きである。天空を海に、雲をその天の海に立つ波に喩えた。さらに、月を舟に、星の群れを森に喩えている。大空、海、雲、波、月、星、森という大自然の要素をふんだんに使い、天空に一大物語を造り上げたスケールの大きな作である。
人麻呂の出自や官途については不明な点が多い。通説では、役人としての身分は低く、地方役人として赴任中に亡くなったとされている。
【イチオシ記事】3ヶ月前に失踪した女性は死後数日経っていた――いつ殺害され、いつこの場所に遺棄されたのか?