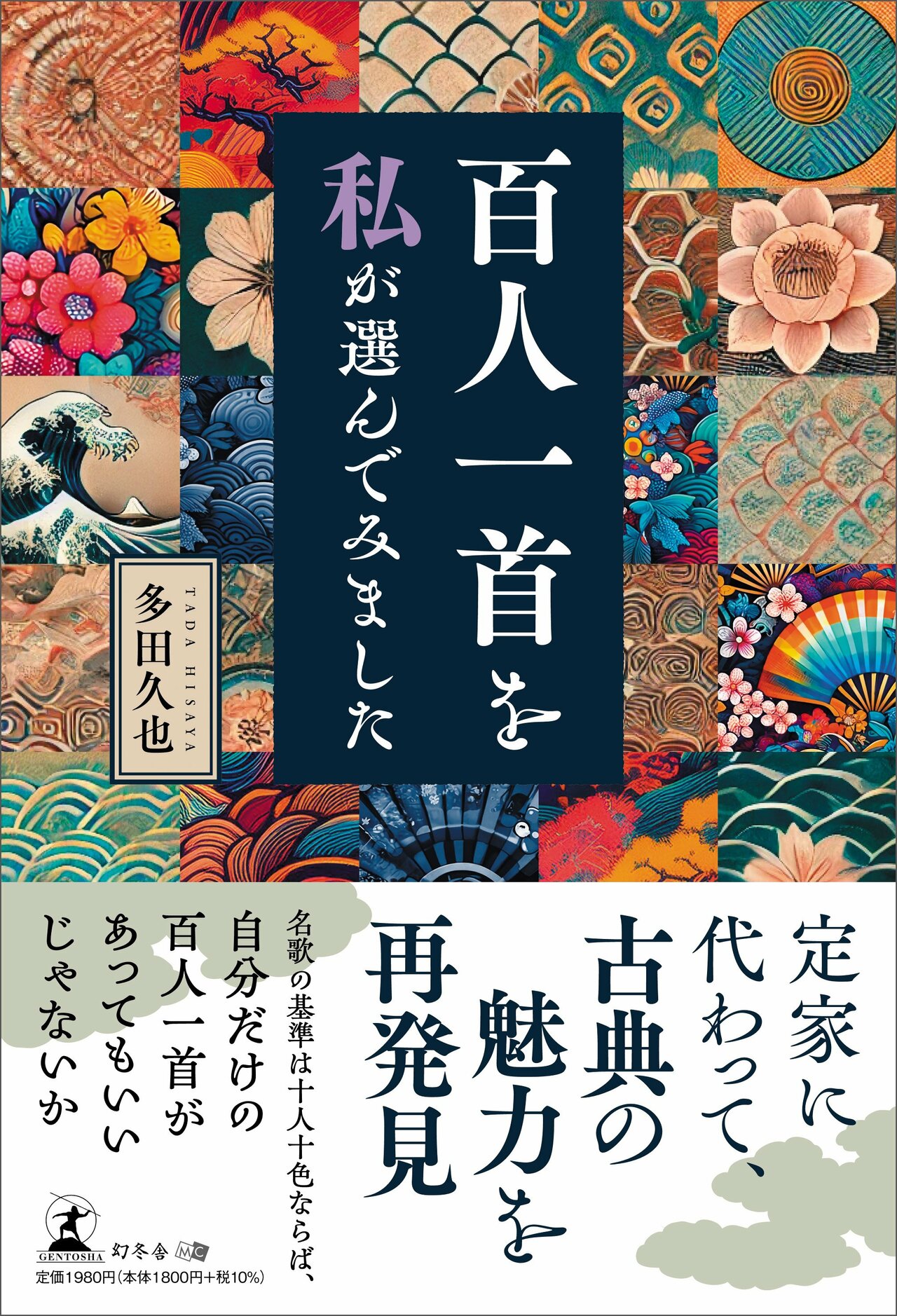旅人が詠んだ次の八五二番歌も好きだ。
梅の花夢(いめ)に語らくみやびたる花と我(あ)れ思(も)ふ酒に浮かべこそ
(梅の花が夢の中でこう語った。「私は風雅な花だと自負しています。どうか酒の上に浮かべてください」と)
「みやびたる」以下が梅の花が言った言葉である。夢に現れたのは梅の花の精で、旅人に語りかける形を取っている。はらはらと舞い散ってきた白梅の花が酒杯に浮かぶ。これを風流と感じる古人の心は、今の現代人にもそのまま伝わっているのである。
なお、これらの歌の序文の中に「時に、初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぐ」(折しも、初春の佳き月で、気は清く澄みわたり風はやわらかにそよいでいる)という文があり、ここから「令和」という年号がとられたのである。
大伴旅人は、大和朝廷以来の武門の家に生まれ、順調に昇進し、大納言に至る。大伴家持、書持(ふみもち)の父で、坂上郎女(さかのうえのいらつめ)の異母兄である。六十歳を過ぎてから大宰帥として筑紫に赴任した。漢詩文に長けた教養人であり、山上憶良とともに筑紫歌壇を形成した。勅撰入集は十三首、『万葉集』には五十首以上収載されている。
筑紫赴任中に妻を喪い、六十五歳の時に帰京。奈良の自宅に帰ってきたときに詠んだのが次の歌だ。
人もなき空しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり
(こうして今帰ってきたもののやっぱり、妻もいないがらんとした家は、旅の苦しさにましてなんとも無性にやるせない)
なんの技巧も飾り気も感じられない平淡な歌であるが、こう詠わずにはいられない旅人の切々たる孤独感が伝わってくる。その翌年の夏、旅人は妻のもとへ旅立った。
【イチオシ記事】「浮気とかしないの?」「試してみますか?」冗談で言ったつもりだったがその後オトコとオンナになった
【注目記事】そっと乱れた毛布を直し、「午後4時38分に亡くなられました」と家族に低い声で告げ、一歩下がって手を合わせ頭を垂たれた