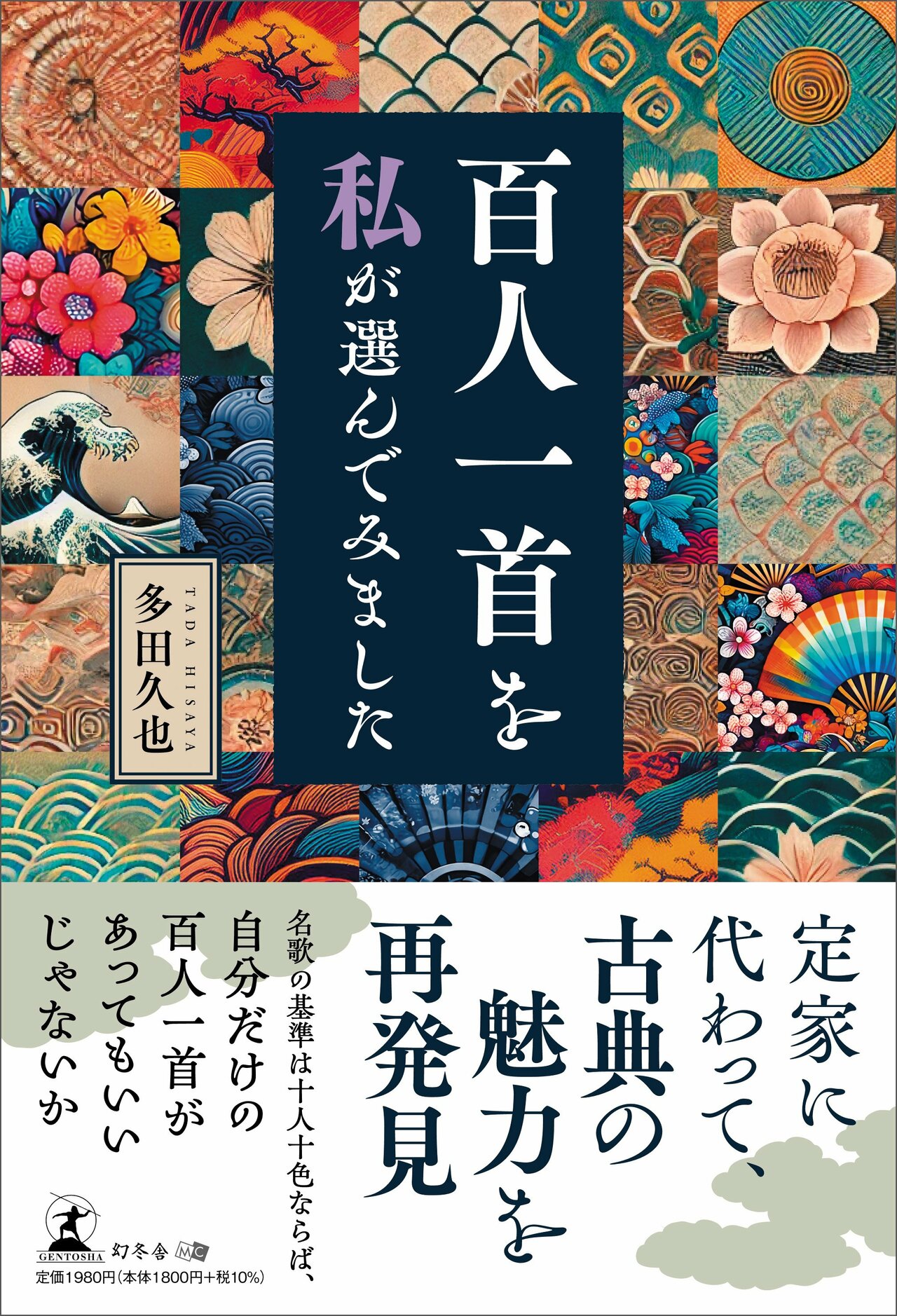3 額田王 (生没年不詳)
君待つと我(あ)が恋ひ居れば我(わ)がやどの簾(すだれ)動かし秋の風吹く
(あの方が早くおいでにならないかと、恋しくお待ちしていると、家の戸口の簾をさやさやと動かして秋風が吹く)
愛しい天智天皇の訪れを待ちわびている額田王。今宵はもう訪れはないのかと半分諦め気分でいると、簾がササッと動く音にハッとして振り返る。しかし、天智天皇の姿は無く、ただ涼しい秋の夜風のみが額田王の頬を通り過ぎていく。
額田王は斉明天皇と天智天皇に仕えた。天皇に代わって儀式のときなどに歌を詠み、戦を前に士気を鼓舞したり高揚感をあおったりする宮廷歌人であった。後の柿本人麻呂や山部赤人のような立場の歌人である。
額田王は絶世の美女といわれている。初めは天智天皇の弟である大海人皇子(後の天武天皇)の愛人となり、二人の間には十市皇女(とおちのひめみこ)が生まれた。その後、経緯は不明だが、天智天皇に召され寵愛された。
つまり、弟の愛した女性を兄が奪い取ったという三角関係にあるわけである。額田王を間に挟んで二人の間には複雑な思いも芽生えたであろう。これが壬申の乱の遠因となったという説もある。天智天皇が崩御した後、跡継ぎをめぐり、天智天皇の皇子である大友皇子に対して、大海人皇子が反乱を起こし滅ぼしたのが壬申の乱だ。
なお、複雑なことに、大友皇子の皇后が、大海人皇子と額田王との間に生まれた十市皇女であるということだ。勝敗がどっちに転んでも悲劇となる展開であったが、十市皇女にとっては夫を実の父に殺されるという結果になってしまった。
額田王と大海人皇子との間にあまりにも有名な相聞歌が残されている。
あかねさす紫野行き標野(しめの)行き野守は見ずや君が袖振る
(まあ、紫草の栽培されている標野を行きながらそんなことをなさって。野守が見るではありませんか、そんなに袖をお振りになったりして)
心がときめくような美しいリズムの歌である。天智天皇が即位した翌年に、琵琶湖湖畔の蒲生野(がもうの)という宮廷の薬草園で薬草狩を催した際に詠んだものだ。袖を振るのは、あなたを愛しているというジェスチャーである。
かつての愛人の額田王を見つけた大海人皇子が大きく袖を振って合図する。それを見た額田王は「人前でそんな大胆なことをすると野守に見つかってしまいますよ」と心配しながらも皇子を諫める、という歌である。この野守こそ天智天皇その人を指しているのであろう。
【前回記事を読む】【百人一首】天智天皇なら、「秋の田の かりほの~」よりもこっち!? 隠れた秀歌を紹介。古文や日本史の勉強にもなる!
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。
【注目記事】急激に進行する病状。1時間前まで自力でベッドに移れていたのに、両腕はゴムのように手応えがなくなってしまった。