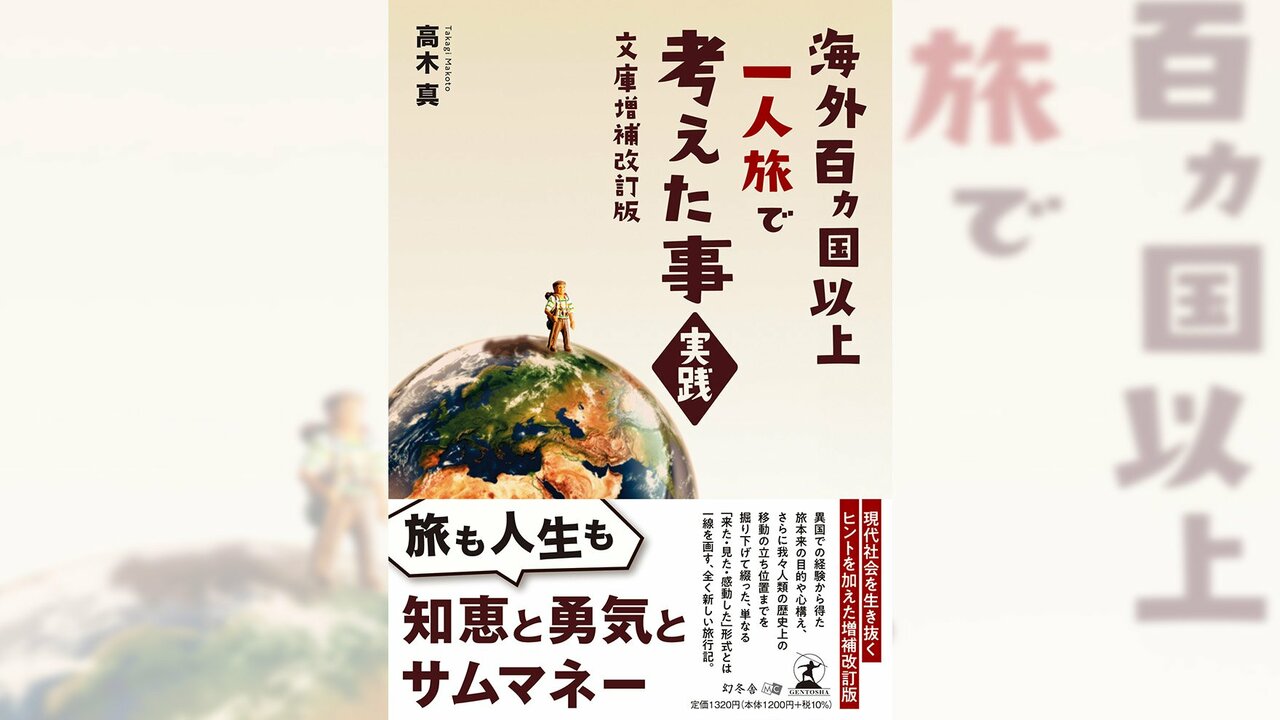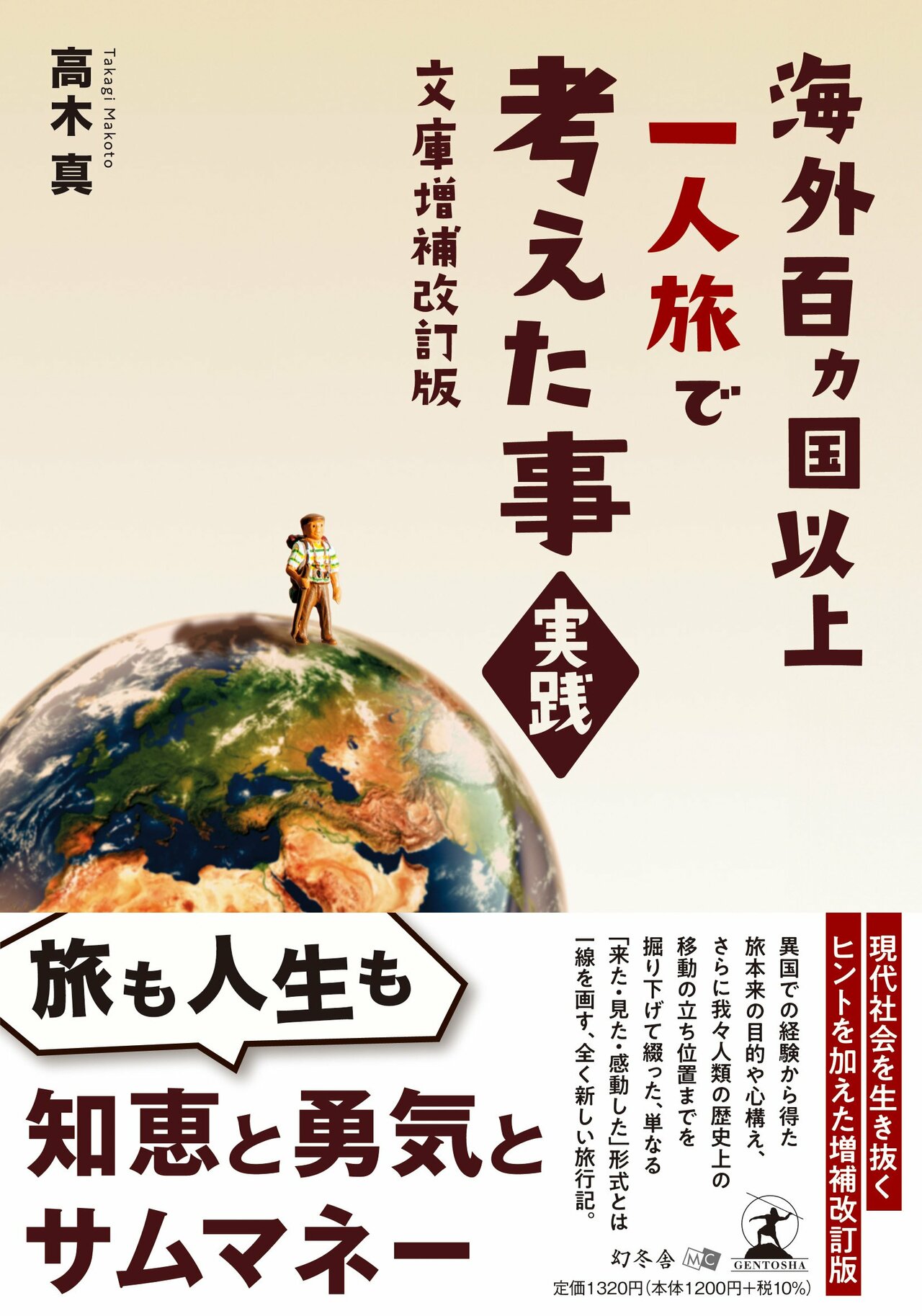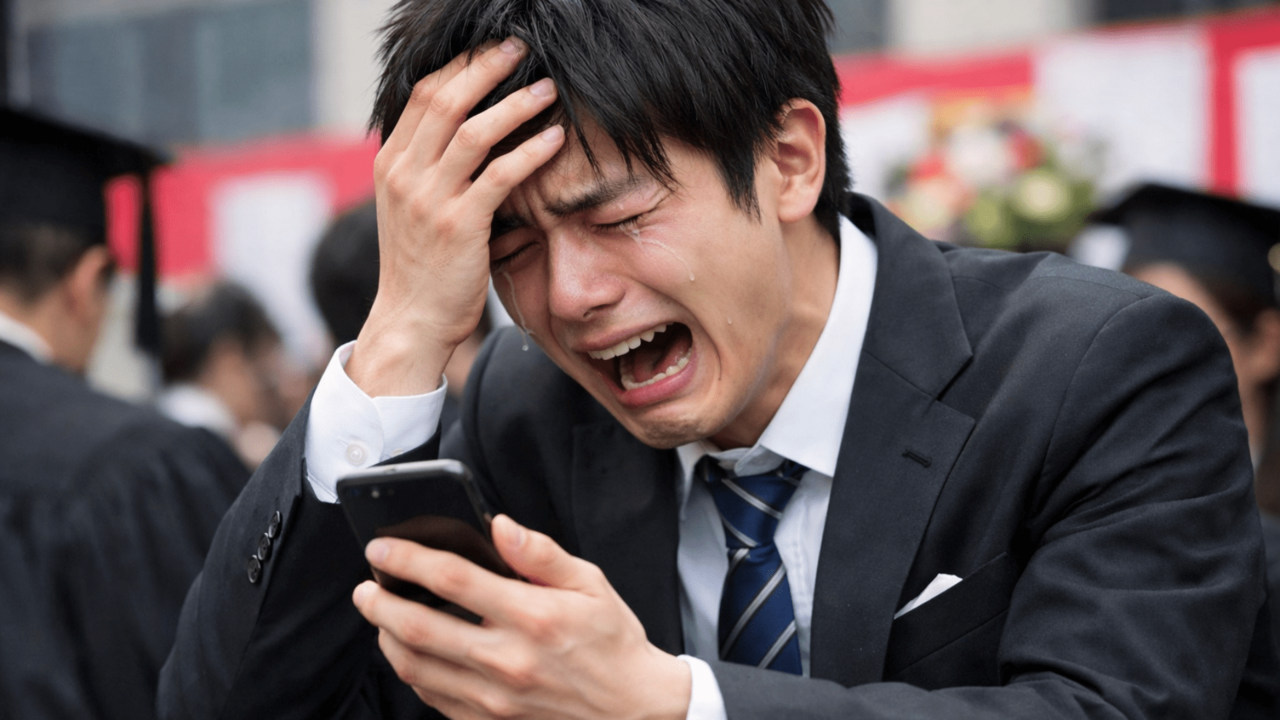私の国内外の旅と旅とは何かについて
旅移動に関する我々の現在の立ち位置
この歴史認識がないと、単に表面的に現在だけを見ても、我々の日本や国際社会での現在の立ち位置が理解出来ないし、判断行動がうまくいかないし、外国の人と共通認識も出来ず国際社会でのコミュニケーションも国際社会理解も出来ない、という事になる。
広く歴史的考察する意味はここにある。歴史的考察は、単に点の丸暗記では足りず、流れとしてそして現在にどのように影響を与えているか理解しないと役に立たない。
そして、多くの日本人が旅移動に関する体系的統一的流れとしての歴史認識を欠いているのではないかと思う。そこで、旅移動に関する歴史を今一度確認する意味で観てみたい。
現代では、居住・移転・職業選択、海外渡航・海外移住の自由は、日本国憲法22条 1 項・ 2 項の憲法保障で、当たり前のように思われていて誰も何の疑問も持たないが、日本の封建時代、特に江戸時代は、農民を土地に縛りつけておく必要上、居住・移転・職業選択の自由はなかったし、関所が置かれ(幕府は、大名の反乱・倒幕を恐れ、特に関所では「入り鉄砲に出女」は厳重に警戒された)、旅行の自由はなかった(農業生産が日本の主要産業だった封建時代、土地と農民はセットで農民の農地からの逃亡(欠落・走り)は重罪であった。
江戸時代には仏教と結びつけられ、例外的に無宿人もいたが、宗門人別帳で庶民は建前上皆仏教徒とされ管理された。当然体制崩壊させる危険性のあったキリスト教は認められなかった。武士の場合も、藩に無断で自由に藩外に出る事は出来ず、脱藩する事は、重罪を犯す事となっていた。
脱線であるが、藩に関していえば、日本の行政区画は、3つの変遷をたどっている。
最初の中央集権時代・律令時代の国郡郷里、江戸時代幕藩体制・封建制のもとでの藩、再度の中央集権時代の明治期の版籍奉還・廃藩置県での都道府県である。
3層構造になっているので、現代の視点から日本の行政区画を見ると、旧国名なのか藩名なのか理解しにくく、混乱する。
例えば、幕末明治期の薩長土肥。薩摩・長州・土佐は藩名であるが、肥前は今の長崎佐賀で本来は旧国名である。肥前藩ともいわれるが、正確には藩名は佐賀鍋島藩であろう。ただ鍋島はいいにくいのでこうなったのであろう)。