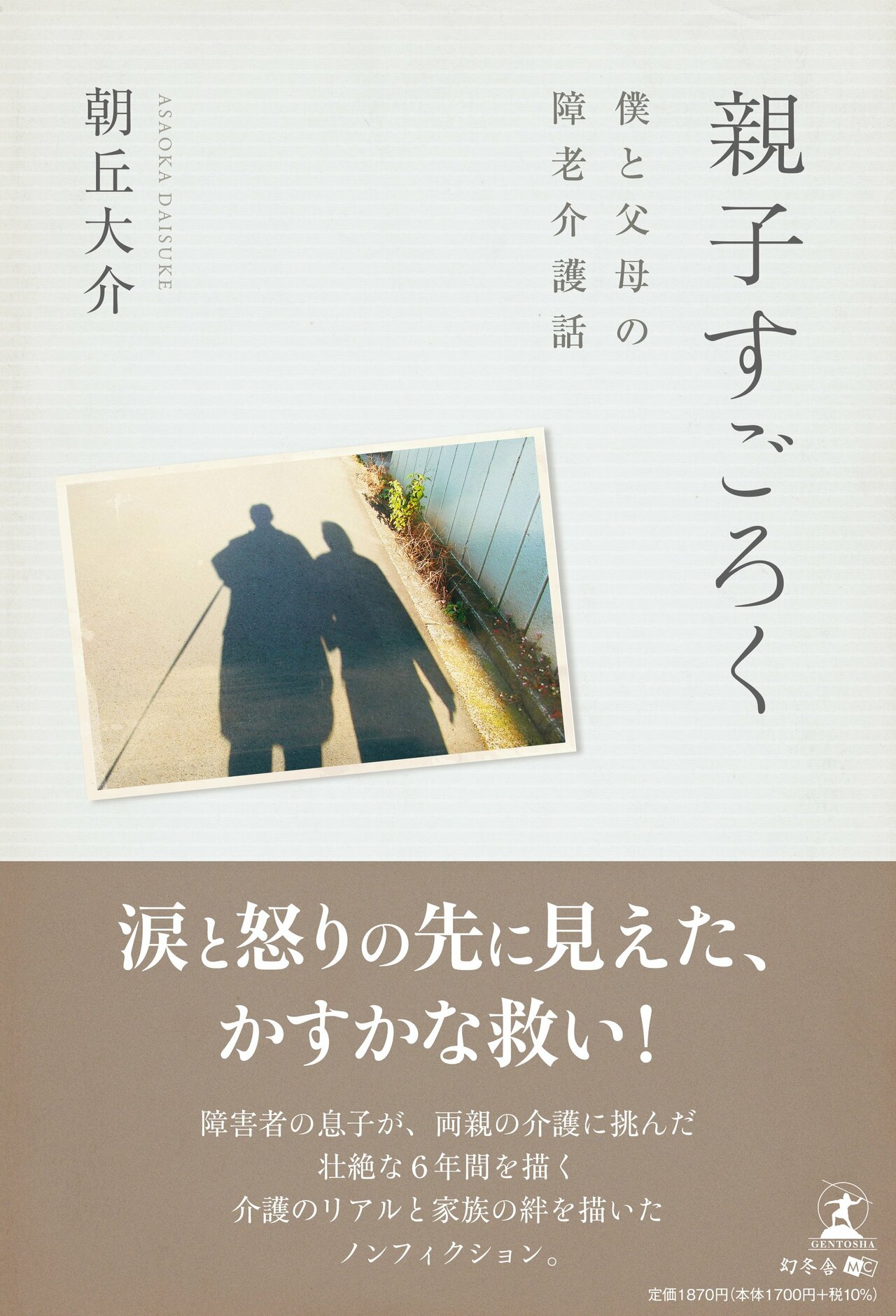「どうして転院になったの?」
「来見谷さんは脳挫傷もありますので、一応脳外科のある所で診てもらうということで」
目を虚空(こくう)に彷徨わせ、動揺した口調で言うと、彼女は一礼してその場を去っていった。ぼんやりと横になっていた僕は、自分の腹部を覆っているタオルケットを見て、はっとした。
股間にしっかりと、テントができあがっていた。
僕は手すりをつかみ、骨折した左足を体重計にのせた。目盛りが二十キロになるまで体重をかけていく。体重の三分の一という感覚を体に覚えこませる。
「どうだ、久しぶりに立った感じは」石橋院長が黒眼鏡越しにたずねる。
「問題ありませんね」
院長はどこからか、手すりが馬蹄型(ばていけい)になっているキャスターつき歩行器を持ってきた。僕は歩行器を引き寄せ、浮き輪のようにしがみつくと、おそるおそる足を前へ出した。
「おいおい、上体が右へ傾いているじゃないか。痛むのか」
「下腿は問題ないです。ただ、肘に針金が入っているから、寄りかかるとそっちのほうが痛くて」
「それならば問題はない。じゃあ、今日からそれで歩いていいから」
「やったー」
「まあ、ゆっくりと練習するんだな」
石橋院長はそのままぷいと去っていった。
薄暗い廊下を前傾姿勢のまま、僕は慎重に歩いた。これで車椅子ともおさらばだ。今までよりも目線が高くなっているのを感じる。この二か月間、ほとんど白い天井しか見ていなかったせいか、歩いていると視界のすべてに白い靄がかかり、やんわりとやさしく見える。背筋に疲労を感じた。