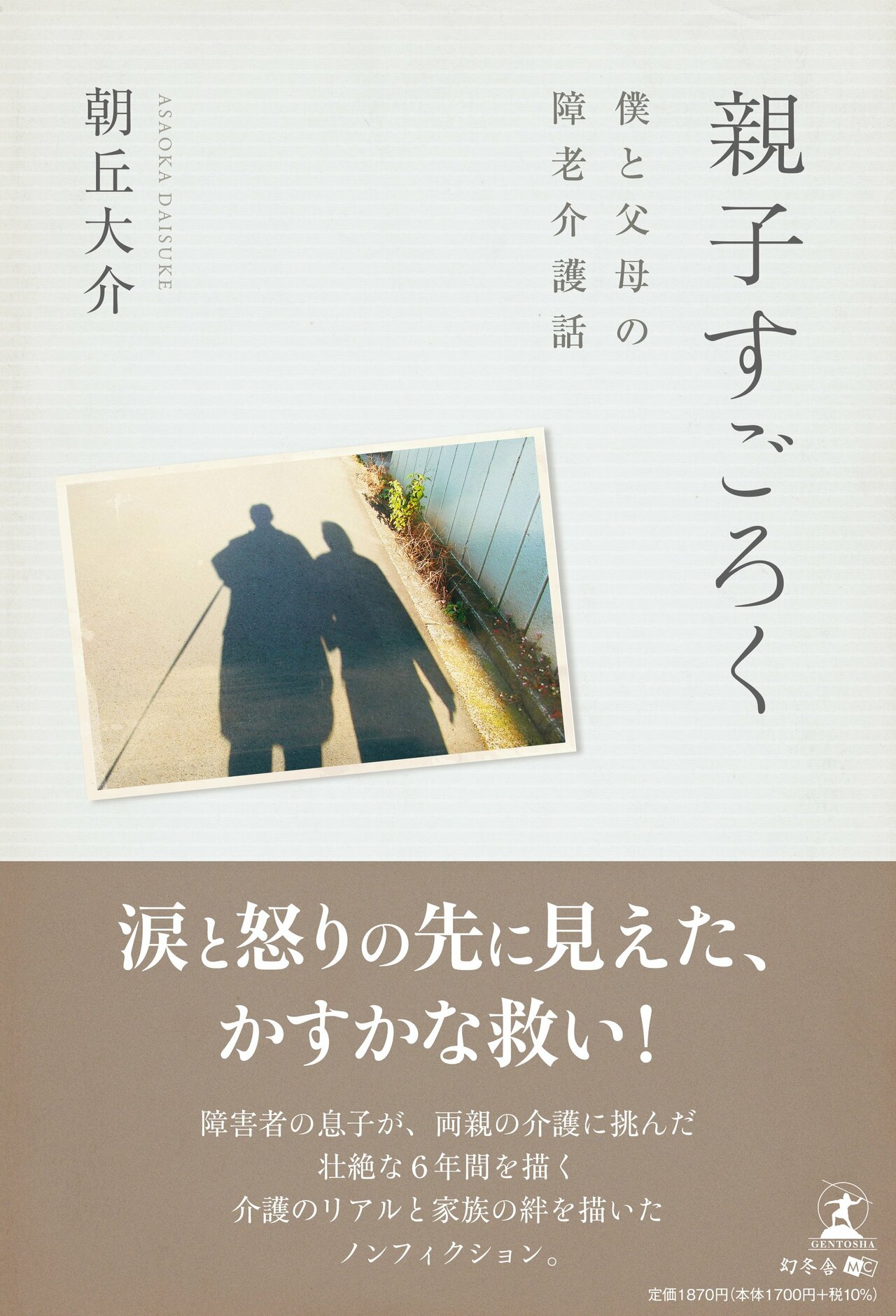僕は一人納得して、うんうんとうなずいた。その後、ひと通り昔話に花を咲かせると、内田が真顔で切りだした。
「ところで弁護士は入れた?」
「いや。叔父の知り合いに弁護士がいるらしいが……必要かな?」
「弁護士は絶対に必要だよ。自賠責保険の等級認定だとか、専門の交通弁護士でないとわからないことってあるし」
「そういえば、ここの医者から、ヘタしたら一生杖かもしれないって言われたよ。でも、弁護士なんて頼んだら、何百万円も取られるからなぁ」
「車の保険で、おれが教えた『弁護士特約認定』は入ってないの?」
「そうか。入ってる。入ってるよ」
「だったら、弁護士費用は心配ない。三百万円までは保険会社が支払ってくれるよ」
「おお! お前に言われたとおり入っといてよかったよ」
「おれ、金はほんとうにふんだくるべきだと思う。轢いた本人の財布は痛まないわけだし」
「向こうの保険会社か」
「いい弁護士がいるから紹介するよ。絶対に、金は絶対に取るべきだ」
「まあ、慰謝料よりも、とりあえず今は、この退屈を埋めてくれるアイテムが欲しいよ」
僕は内田にスポーツ新聞をねだった。内田は裏口から外へ出ていったあと、十分ほどして、はち切れんばかりに膨(ふく)らんだビニール袋を提(さ)げて戻ってきた。
「百メートル先にコンビニがあった」
「そんなのあったか?」
「あそこの橋を渡った所」
内田は、車椅子に座る僕の膝の上に袋をのせた。スポーツ新聞のほかに、漫画の単行本が何冊も入っていた。しばらくは楽しめそうなボリュームだ。
「スポーツ新聞と漫画はわかるけど、この亜鉛はなんなの?」袋の底に、サプリメントの容器が入っていた。
「髪には亜鉛がいいって、女房の弟が言っていたぞ。髪に欠かせないミネラルなんだって」
「よし。試してみよう」
僕はお礼に未使用のテレホンカード三枚を奴に手渡した。別れ際、内田はぽつりとつぶやいた。
【前回の記事を読む】病室の入院患者みんなが一斉にバッシング。看護師の悪口で患者の心がひとつとなる瞬間