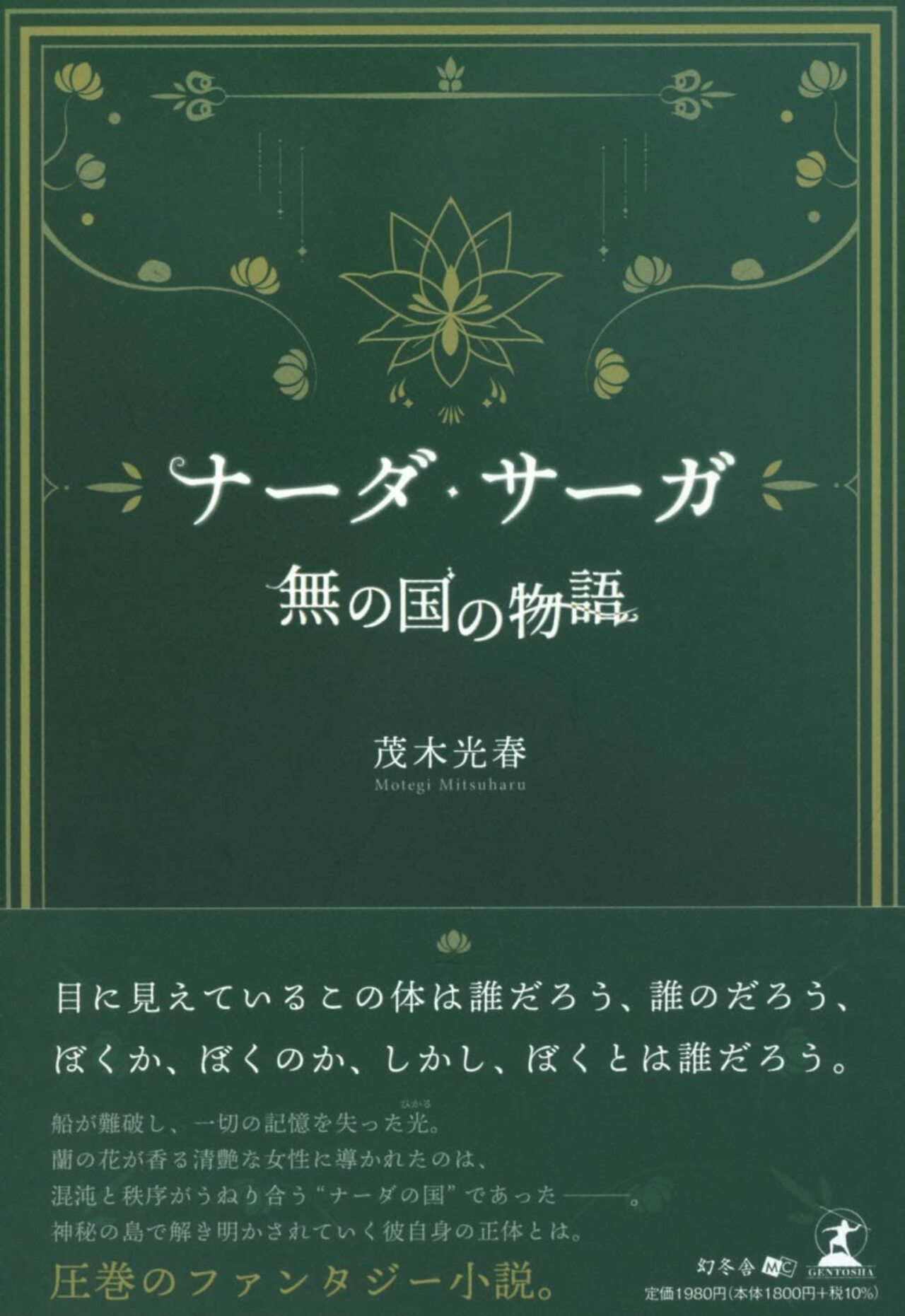不思議な矛盾をいとも無造作に生きている感じなのだ。ぼくは艶やかな磁石に吸い寄せられた鉄くずのように、いとも易々と少女の後に付き従って行った。
巨大な地下空間を思わせるバザーの中を通り過ぎ、一つのアーチ型の入り口を通って、地下階段を、それこそまた延々とそして踊り場を何個も曲がって登って行った果てに、不意と、白い壁のアーチ型にくり抜かれたロマネスク風の回廊に出た。
回廊は中庭を囲んでロの字型に作られ、床はモザイク状の石畳になっていて、すでに何十年何百年人々の足をもって踏みならして来たもののごとく、すべやかに凹みができ、なだらかな凹凸ができ、こちらの足が吸い付けられるような奇妙な感触を受ける。
その回廊をいろんな人が歩いている。いや、むしろ、いろんな女性が歩いていると言う方が正確である。
いや、もっと言えば、その女性たちはほとんどすべて前を行くセイレイ嬢のように、白い半透明の薄物のサーリーを着ていて、言わば、十人のセイレイ嬢が歩いているような風情である。
十人の春の精がふわりと佇立し、そぞろ歩きをしているがごとき風情である。夢幻である。幽玄である。
しかも前を行くセイレイ嬢は回廊を一回りして、ふたたび同じ回廊を巡るがごとくなのである。どこへぼくを連れて行くのであろうか。二回りを歩き始める。夢幻感はいよいよ募る。
何人ものセイレイ嬢が行き交う。何人もの春の精が通り過ぎる。馥郁たる風の中を行くがごとくである。馥郁たる女体の中をよぎるがごとくである。
中庭の四辺には石の長いベンチのごときものがあり、その前の中央には大きな丸い池があって、中心の辺りから、時折、眠りを誘うがごとき緩やかな噴水が、白い水煙を立てながら、何条にも分かたれて立ち昇る。
噴水はたえず落ちて、無数の水滴は池の水面に声にならない音を立てながら、ぴしゃっと飛び跳ねて消えて行く。瞬間の生き物、ホザーナの生き物、この世に現れたとも言えない変幻の生き物。無数の水滴、無数のしずくの音。