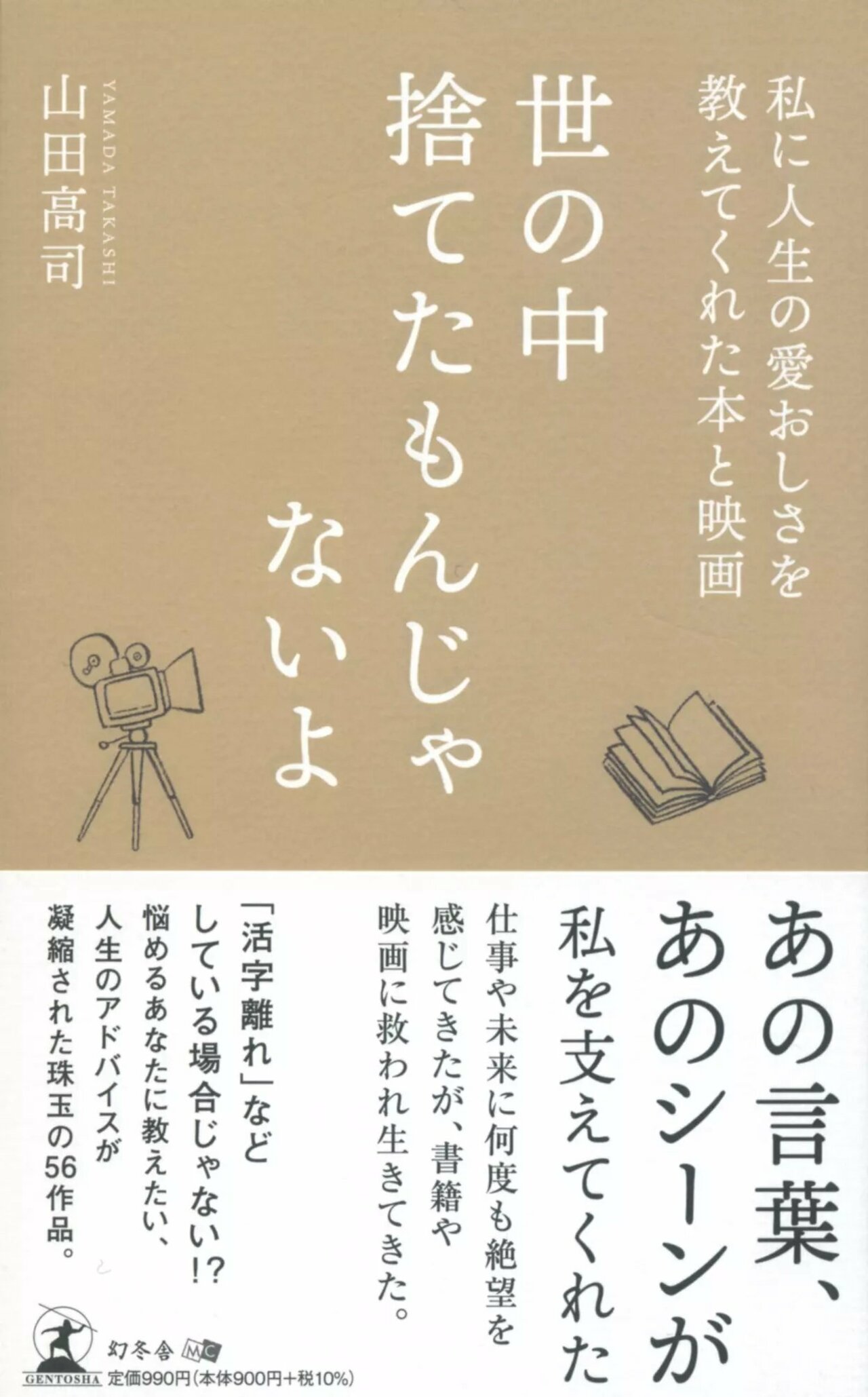第二章 日常を生きぬく事 くじけそうな時は
『ムーン・パレス』P・オースター 柴田元幸 訳 新潮文庫 一九九七年
孤独と闇の中より人生の展望を見出す
第一印象として感じたのがこの物語の底に流れている「締め付けられるような孤独感」が痛々しい。
それを癒してくれたのが、キティ。しかし彼女ともその後別れる運命にある。
前半は自分自身の人生を見つけられないままセントラルパーク周辺を彷徨し、危うく命を落としかける場面。中盤はひょんなことで知り合ったキティと共に暮らしながら、気難しい老人の世話をして生きてゆく日々。
その老人が亡くなった後、老人のただ一人の息子バーバーに会い、老人の足跡を二人でたどることを決めた後に、バーバーが自分の父であることがわかる。
後半は自分の父バーバーと死別した後に祖父の足跡を探す日々。
一九七〇年代の若者の孤独感、人生に対する目的の喪失、人生を見つけるための放浪。これらが濃厚に描かれている小説である。
主人公が一番目的意識を持って人生を送れたのは、祖父(と言っても当時は自分の祖父とは知らずに世話をしていた一人の老人なのだが……)と共にその祖父の死亡記事を書く日々であったのだと思う。