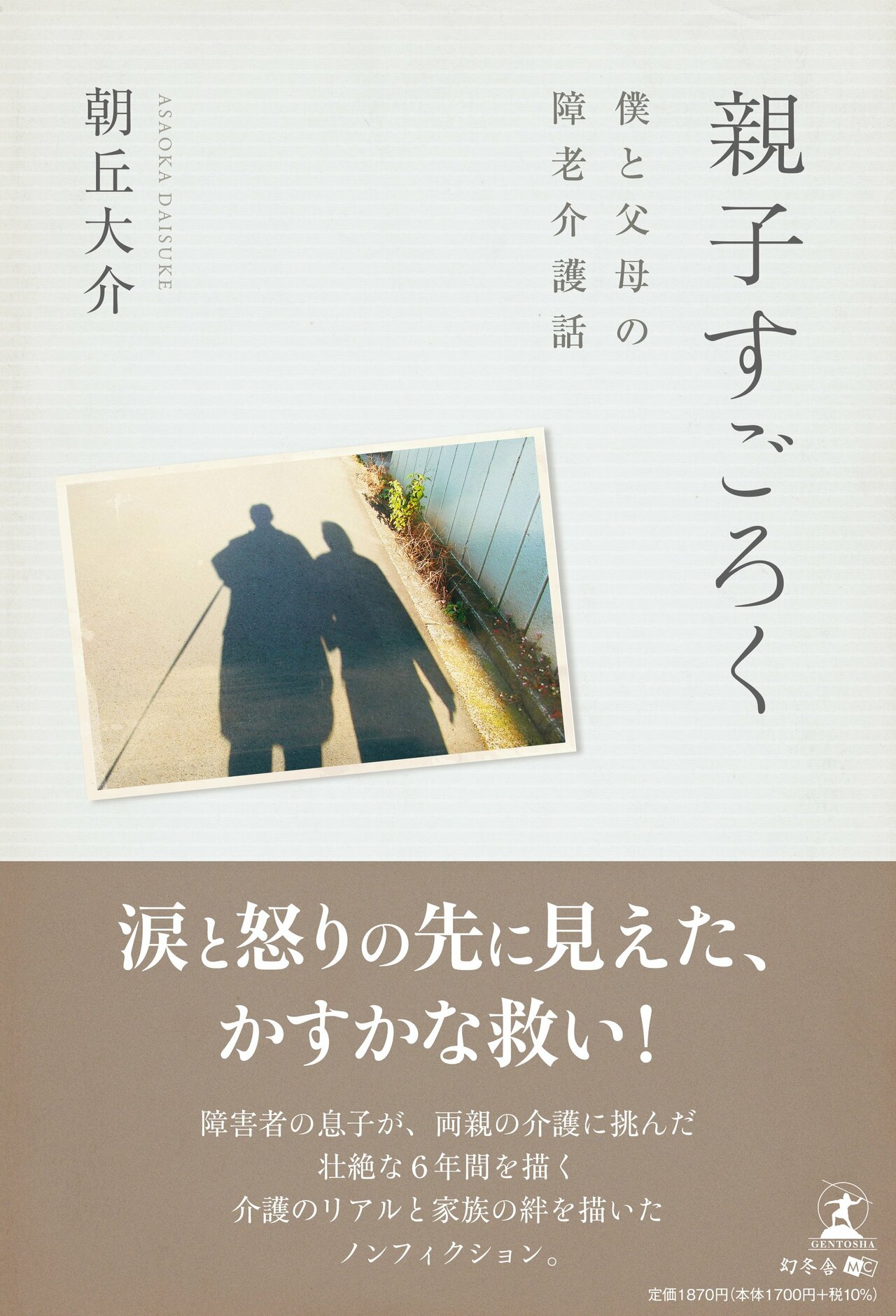昼食後、とろんと横になっていると、誰かが足元を揺さぶった。しばらく無視して目を瞑っていたが、しつこく揺さぶるので薄目を開けてみると、色の浅黒い男がこちらを見ていた。
「お久しぶりー」
四角い顔に銀縁眼鏡。がたいが大きく、どことなく登山家を連想させる。僕はとまどった。どっかで見た覚えのある顔だ。
「はい、これ。お見舞い」
そう言うと男は床頭台に“軽井沢タルト”と花束を置いた。
「コウちゃん!」
思わず声をあげた。
「目、覚めた?」
高校時代の同級生、大林康一だった。高校時代の友人で、彼は寮に入っていたので、土日になるとよく、うちに泊まりにきた。高校を出たあともたまに一緒に遊んだが、就職後、彼が地元に戻ってしまったのを機に、すっかり音信が途絶えていた。現在は軽井沢の実家で手づくりジャムを中心とした土産物屋をやっているらしい。
「どうしてここがわかったの? しかも北海道だよ?」
「いや、内田から連絡があってさ。クルミが交通事故に遭ったって」
「内田か……昔から気のつく奴だ」
「腕も折ったの?」
「あっちこっち痛い」
「大変だ」
「びっくりしたよー。突然現れるもんだから」
「ちょうどこっちに用があってさ。これから商談があるんだ。北海道のバターを食べに来たんだよ。うちの菓子に使えないかと思って」
「店はどうした? 一階が喫茶店になったんだろ?」
「あれ、話したっけ?」
「内田から聞いた。去年結婚したとき、奥さん連れてコウちゃんの所へ行ったって。あいつぼやいてたぞ。せっかく友達がはるばる会いに行ったのに、金取りやがって、って」
「まあ、商売は商売だから」
「しかし、久しぶりだなー。変わってないなー」
「クルミ、ちょっと薄くなったんじゃない?」大林が、僕の頭に目を向けた。
「やっぱりそう思う?」
高校時代、大林のあだ名は“オヤッサン”だった。額も広く、老け顔でクラスメイトからそう呼ばれていた。一方、僕は“ミルク”とか“ミルクちゃん”とか呼ばれていた。だが今は、奴は年齢がルックスに追いついて、こっちは一気に老けこんでしまった感がある。
大林がすこし間を置いてから言った。
「ビタミンを摂れよ」