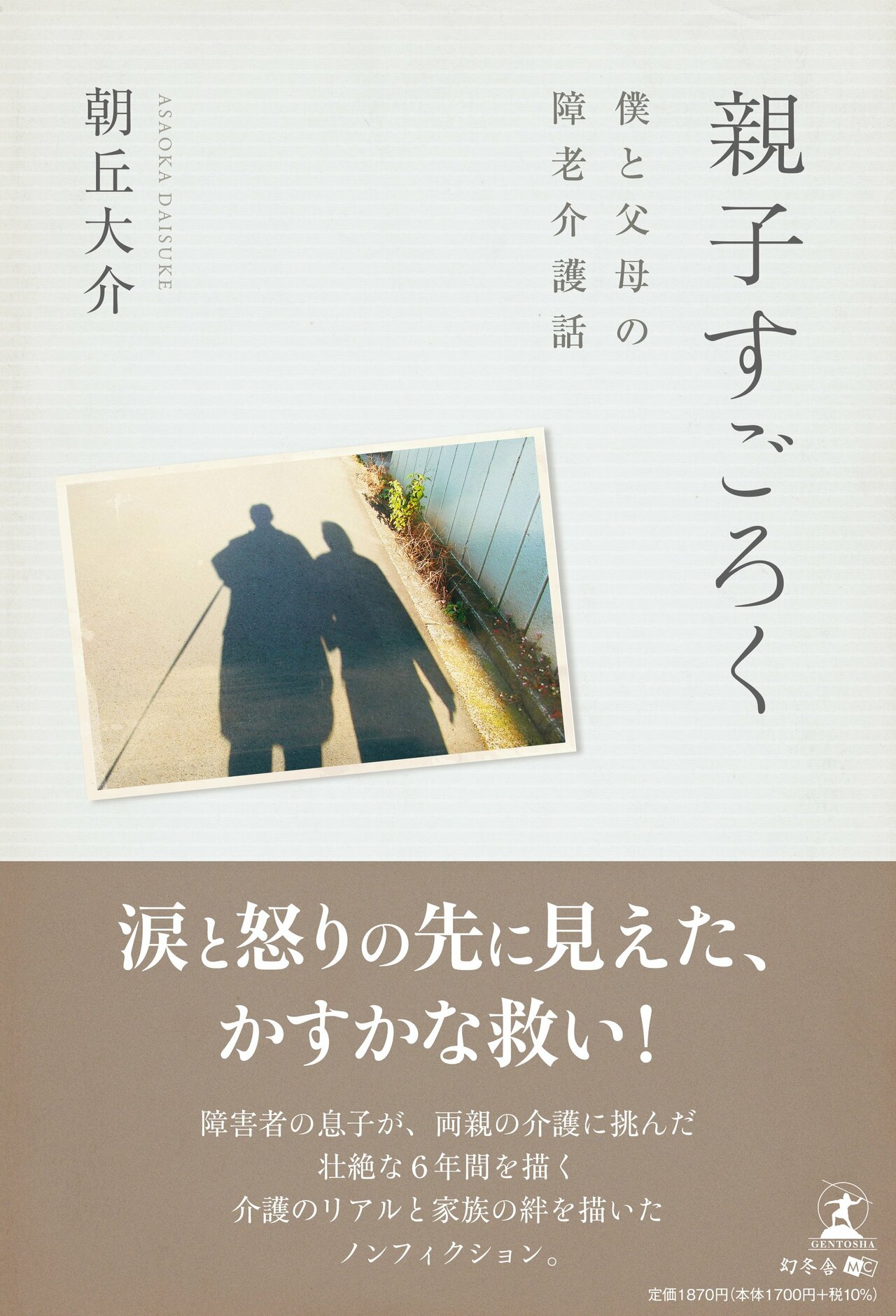「思い出せないです。目が覚める前のこと。……なにか強いショックを頭に受けたのかもぉ~。……どうしましょう、クニクニ先生」
「なんとかしないとね」
「はい」
久仁子は華奢な上半身を反らせた。そして勢いよく、
「とりゃ!」
ゴツッ!
「香澄に頭突きを見舞う。
「いたぁい、クニクニ先生ってば、なにするんですか~!?」
香澄が久仁子の顔でうめいた。
「こうすれば、もとにもどれるかと思って」
「頭突きで入れ替われるのなら、ポメラニアンがいいです」
「犬になってどうするのよ。……でも、困ったわね。ほんと、どうしようかしら」
久仁子は腕を組んで考え込んだあと、頭を上げて言った。
「この病棟の人なら、私たちが意識をなくしたわけを知っているかもね」
「はい。たしかにぃ」
「それなら、私が病棟のナースに、それとなくさぐりを入れてみようか?」
「はい、そしたら、わたしは各診療科の様子を見てきます」
「できる?」
「やってみます」
「心配だなぁ……。気をつけてよ。体が入れ替わったなんて言ったら、その場で精神科行きだからね。“ERの岡本久仁子”として、恥ずかしくない行動をとって。“ドゥ・ザ・ベスト”よ」
「了解しました。では、行ってきます」
久仁子の体に宿った香澄は、かちんこちんに体をこわばらせながら病室を出ていった。
その様子を心配げに見届けた久仁子は、窓の外をながめた。
夜空には月が浮かび、たくさんの星がまたたいていた。