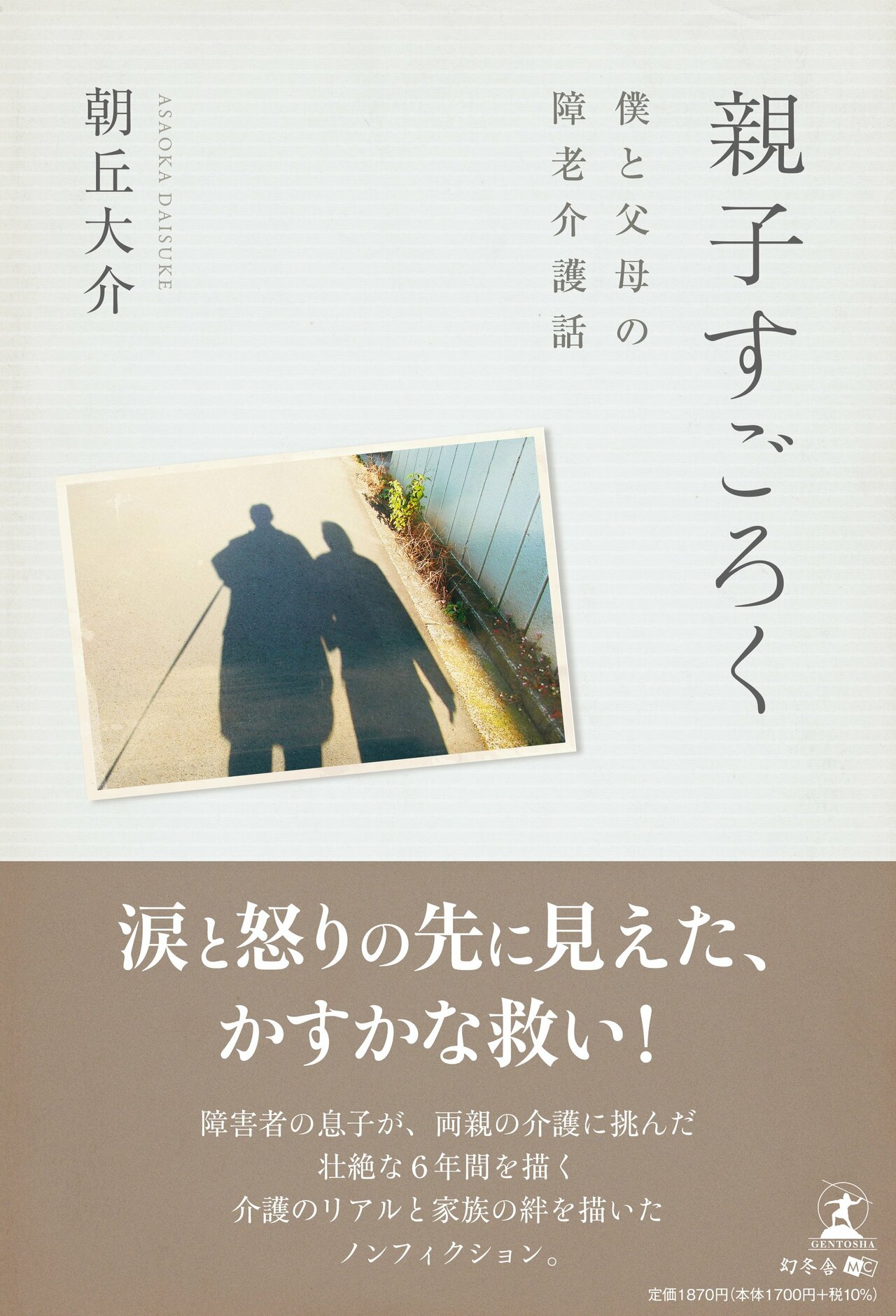女性は不審顔で、久仁子にたずねた。
「あなたは何者なの?」
「私は岡本久仁子。この病院の女医よ。ERの」
「ええええぇえ! クニクニ先生? クニクニ先生なのですか!?」
目の前にいる女性が、目を丸くした。
久仁子はすぐにぴんときた。自分を“クニクニ先生”と呼ぶ人間は、この病院でひとりしかいない。
「……香澄。そうなのね」
目の前の女性がうなずく。
「もう鏡はみた?」
「いえ」
「だったら、そこのガラス窓をごらんなさい」
女性は、久仁子が示したガラス窓に目を転じた。そして、あっとさけんだ。
「わたし、クニクニ先生になってるぅ~」
「どうりで……。今日はいつもより胸が重たいわけですね。きゃはっ」
「そんなことは、どうだっていいでしょ!」
と久仁子。
「問題なのは、私たちが入れ替わちゃったっていうことでしょう?」
「はい……。わたし、クニクニ先生として生きていく自信ないです。救急医療のスキルも、決断力もないしぃ」
「私だって、香澄みたいな“不思議ちゃん”にはなれないわ」
ふたりは黙り込んだ。しばらくの沈黙のあと、久仁子は香澄にたずねた。
「どうしてこの病室に来たの?」
「目を覚ましたら、二階にある女当直室のベッドに寝かされていたんです。なぜだかわからないですけれど……。それで、先週盲腸の手術をして、この病室に入院していたから来てみたんです。そしたら、わたしの体になったクニクニ先生がいて……」
久仁子はうさぎ顔で考え込んだ。
「……ということは、スタッフのだれかが意識のない私を、香澄だと思って、この部屋にもどしたのね」
「なるほどー。ということは、ちがうスタッフが意識のないわたしを、クニクニ先生と思って女当直室のベッドに寝かせたのかもしれないですね」
「……ここは外科病棟?」
「いえ、リハビリ病棟です。外科病棟は満床になっちゃったから、盲腸の手術が済んだあと、こっちへ移されたんです」
「ふうん。でも、私たち、どうして入れ替わちゃったんだろ」
「さあ。どうしてでしょう?」
「ええと……」
久仁子は記憶をたどろうとした。頭にはぼにゃりとモヤがかかっていた。それは香澄も同じようだ。