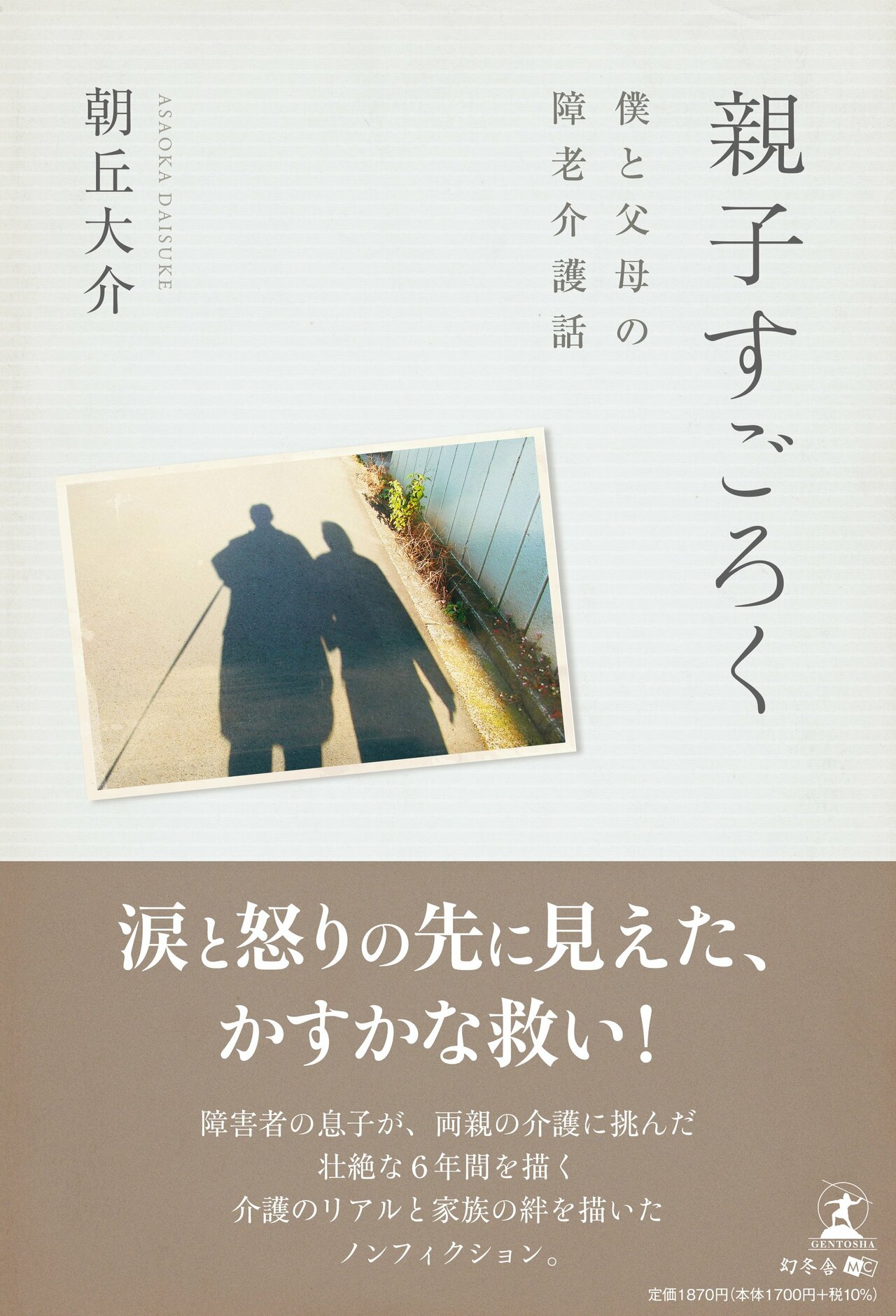十八時 プロローグ
ピーポー
ピーポー
サイレンの音を高らかに鳴らして、猛スピードで走る救急車。
道をあけてくれる車たち、こちらを見ている通行人、夕紅に染まったアップタウンの光景、いろいろなものがみるみる後ろへと流れていく。
車の揺れに身を硬くしながら、岡本久仁子は狼狽していた。
眼下には、七歳の少年が横たわっている。息子のさとるだ。瀕死の重傷を負っていた。
どこからか鈴を転がすような歌声が聴こえる。
♪シャボン玉飛んだ
屋根まで飛んだ
屋根まで飛んで
こわれて消えた
子どものころ、音楽の授業でならった歌だ。
そこらじゅうに光の粒子が舞っている。
どうして救急車に乗っているのか、なぜ息子が血を流しているのか、久仁子には身に覚えがあった。八年前、目にした光景だった。
親子ふたりで東京に出た休日。道を歩いていたところを、信号無視をした車が突っ込んできたのだ。
あまりにも突然のできごとだった。
洗練された都会の夕景色に目を奪われている寸の間に、ドン!という衝撃音がして、となりを見るとさとるが消えていた。
あたりを見まわすと、十五メートル後方でさとるが倒れていた。
「だれか、救急車を呼んでっ!」
必死にさとるを抱きかかえながら、久仁子はまわりの人だかりにさけんだ。
顔面は血まみれ。衣服のところどころが破れ、手足が不自然に折れ曲がっていた。
ほどなくして救急車が現れ、久仁子は息子とともに後方ハッチから乗り込んだ。車内は運転席と処置室に分かれ、医療機器がいたるところに置かれていた。
ほんとうは、これから会社を早引けした夫と落ちあうことになっていた。親子三人でナイトタイムの遊園地を楽しむ予定だった。
車内では、救急隊員がシャツからズボン、そしてパンツを目にもとまらぬ早業で切り裂いた。素っ裸にされたさとるの体は、ところどころ皮膚がえぐれていて、輸血、点滴とともに簡易な応急処置がほどこされた。
「救急車が進入します! 救急車が進入します!」
くり返しマイクで警告する運転手。一刻を争うので、かなり荒っぽい運転だった。
五分ほど走ったところで、白い建物が見えてきた。
――いまなら何とかなる。
だが、救急車は停まらなかった。玄関前のターミナルをぐるりとまわると、そのまま病院から離れていった。
「ねえ、どうしたの!? なんで停車しないのよ!」
白いカーテン越しに遠ざかっていく病院を視界のすみに入れながら、久仁子は救急隊員に突っかかった。