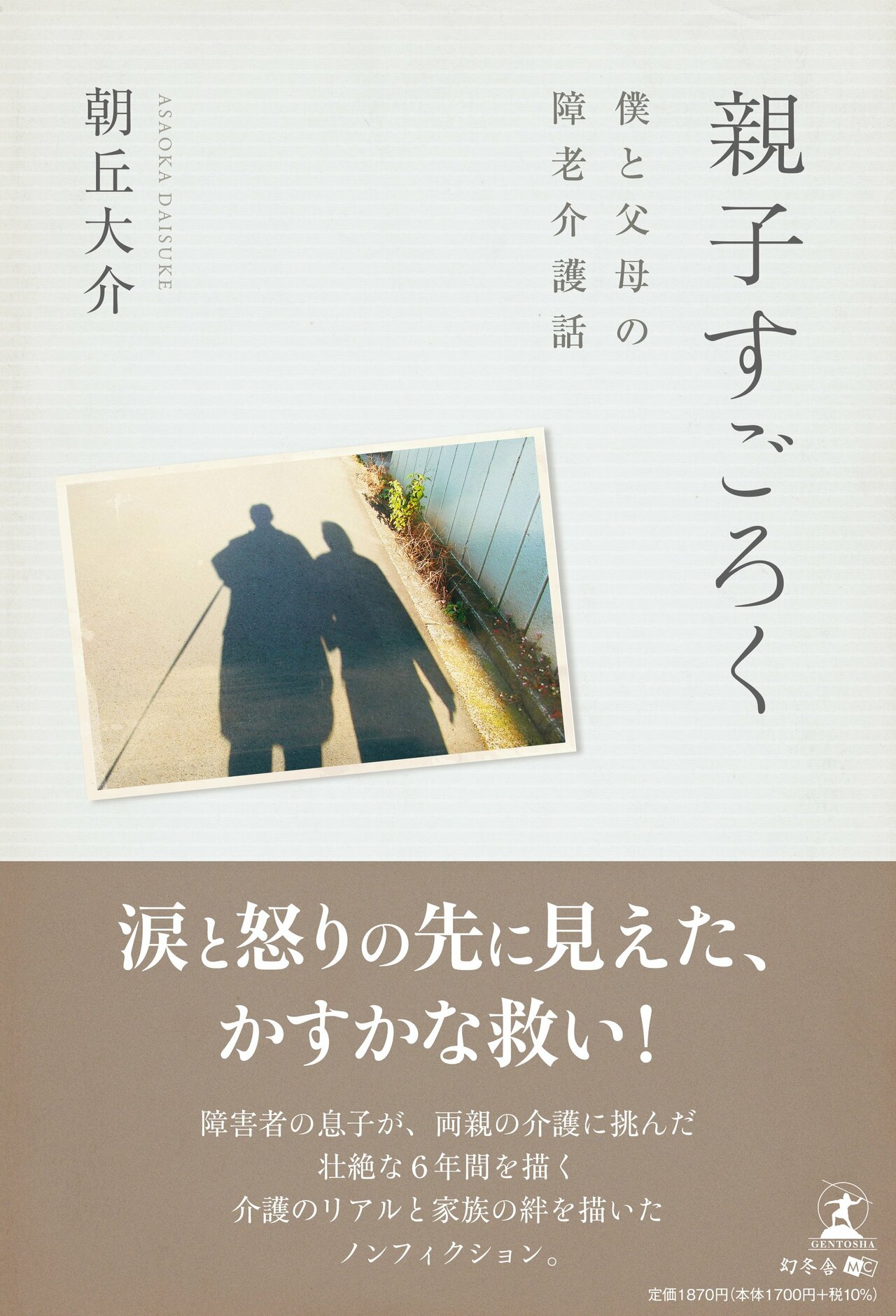十八時 プロローグ
夢か現かわからないまま、久仁子は天井を見ていた。
あたりはシンと静まりかえっている。首すじにぐっしょりと汗をかいていた。
天井からぶら下がったビニールバックから、透明な雫がぽとりぽとりと落ちている。
吐き気。酸欠間。底の知れない不安感。お腹が痛い。頭も痛い。
久仁子は自分に何が起きているのかわからなかった。自分の体が自分のものでないような違和感があった。膜を一枚かぶったような感覚のなかにいる。
桃色のパジャマを着せられ、ベッドに寝かされている。ベッドの右手には液晶テレビが載った床頭台。台にはスライド式のテーブルがついていて、その上にドラえもんの置き時計がちょこんとある。久仁子の趣味ではなかった。
体の苦しみとは裏腹に、心のなかは静けさがただよっていた。
——さとる。
久仁子は涙をこぼした。自分の息子が交通事故で死んだ。そのことを思うと、事故から八年たったいまも、悔やみきれなかった。ずっと楽しみにしていた、ナイトタイムの遊園地に連れていってあげられなかったことも心残りだった。
さとるが死んでから二年ほど、久仁子は無気力、無感動、無表情の日々を送った。電池が切れたように全身の力が抜けたまま、動かなくなった。
「あの奥さん、息子が倒れているのに、何の応急処置もできなかったんですって」
「医者なのにねえ」
「ヤブ医者なんじゃないの」
「それ、言いすぎ」
道を歩いていると、近所の主婦たちのひそひそ話が背なかに刺さった。
「助けられなかったのは、おまえのせいじゃない。あれは事故だったんだ。悪いのはおまえでなく、さとるを轢いたあの運転手だ」
夫はやさしくかばってくれたが、それでも久仁子は自分を責めつづけた。
——あのとき私が車道側を歩いていれば……。救命医療のスキルがあれば……。研修医時代、もっと貪欲に学んでおけば……。
その後、久仁子は夫と別れ、それまで住んでいた長野から単身で上京した。さとるが亡くなった音原大学附属病院で救命医となるために。