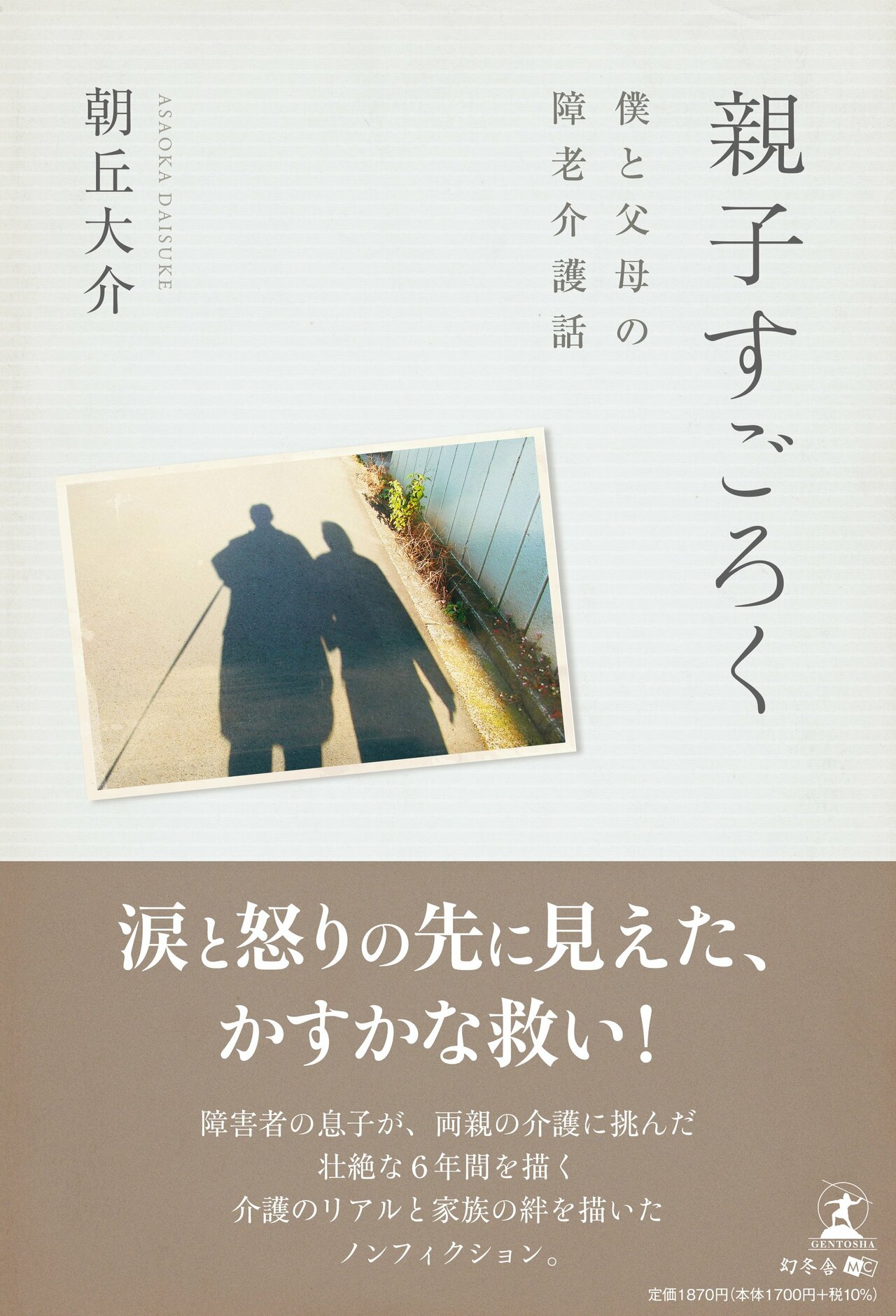十八時 プロローグ
十九時 リハビリテーション科(ST)
「はぁーっ」
リハビリ病棟の南側にある男子トイレ。
鏡の前で自分の顔を確かめながら、マイケル・シマモトはため息をついた。
顔に深く刻まれた三本の傷。一本は額いっぱいに。一本は鼻のつけ根から右のほおにかけて。残る一本は左のほおからあごにかけて刻まれていた。
もともと悪い顔ではない。日本人とアメリカ人のハーフなのだ。頭の金髪はダークブラウンの地毛を染めたものだが、目鼻立ちははっきりしている。
それまでのシマモトは、こわいものなしの“オレサマ男”だった。この病院で薬剤師をしている。言いたいことはずけずけ言う。だれにでもタメ口であったが、欧米人のような顔立ちをしているせいか、職場で彼をとがめる者はいなかった。
それがたった一晩で変わってしまった。半年前、尾島太志というモンスターペインシェント(怪物患者)とかかわったことによって——。
当直の夜のことだった。シマモトは処方箋の記載内容と、電子カルテとを照らし合わせていた。
薬の使用量は適切か。成分は二重になっていないか。過去に副作用を起こしていないか。飲ませてはいけない持病を持っていないか。薬同士が相互作用を起こし、効果が変わる心配はないか。飲みかたに問題はないか。
小児に対しては量が適切か。妊婦に対しては服用して問題はないか。念を凝らし、調べあげた。
問題があれば、オーダーした医師に問い合わせ、処方を再検討してもらい、なければ、薬を正しく使用できるよう薬袋に指示を記入していった。
夜間も薬剤師の需要はそれなりにあった。すべての病棟、夜間外来からのさまざまな薬のオーダーに応えるのがシマモトの役務だった。加えて、医師から「この痛みなら、どの薬が一番効果があるか」といった問い合わせがたまにある。
♪錠剤よし
散剤よし
うんこよし
チェックが終わると、シマモトは何段にも色分けされた調剤棚の前に立った。薬品のキャビネットに囲まれた調剤室は、シマモトの王土だった。七段にびっしりと並べられた千二百品目におよぶ薬品のなかから、お目当ての薬をさがしだした。
棚の一番上に置いてある水剤(液体の薬)の大瓶を取りだすと、量を測りながら小さな容器に寸分の狂いもなく移しかえる。たった一度の算用ちがいも、ぜったいに許されぬことだった。
単に処方どおりに薬をそろえるだけでなく、市販されていない薬剤や求められる剤形がない薬剤は、必要に応じて独自の製剤を行なった。
高齢者や小児など、錠剤のままでは服用量の調整が難しい場合は、粉砕して散剤(粉薬)にしたり、乳糖やデンプンといった薬理作用のないものを混ぜ合わせ、うすめて調整した。
♪錠剤よし
散剤よし
うんこよし