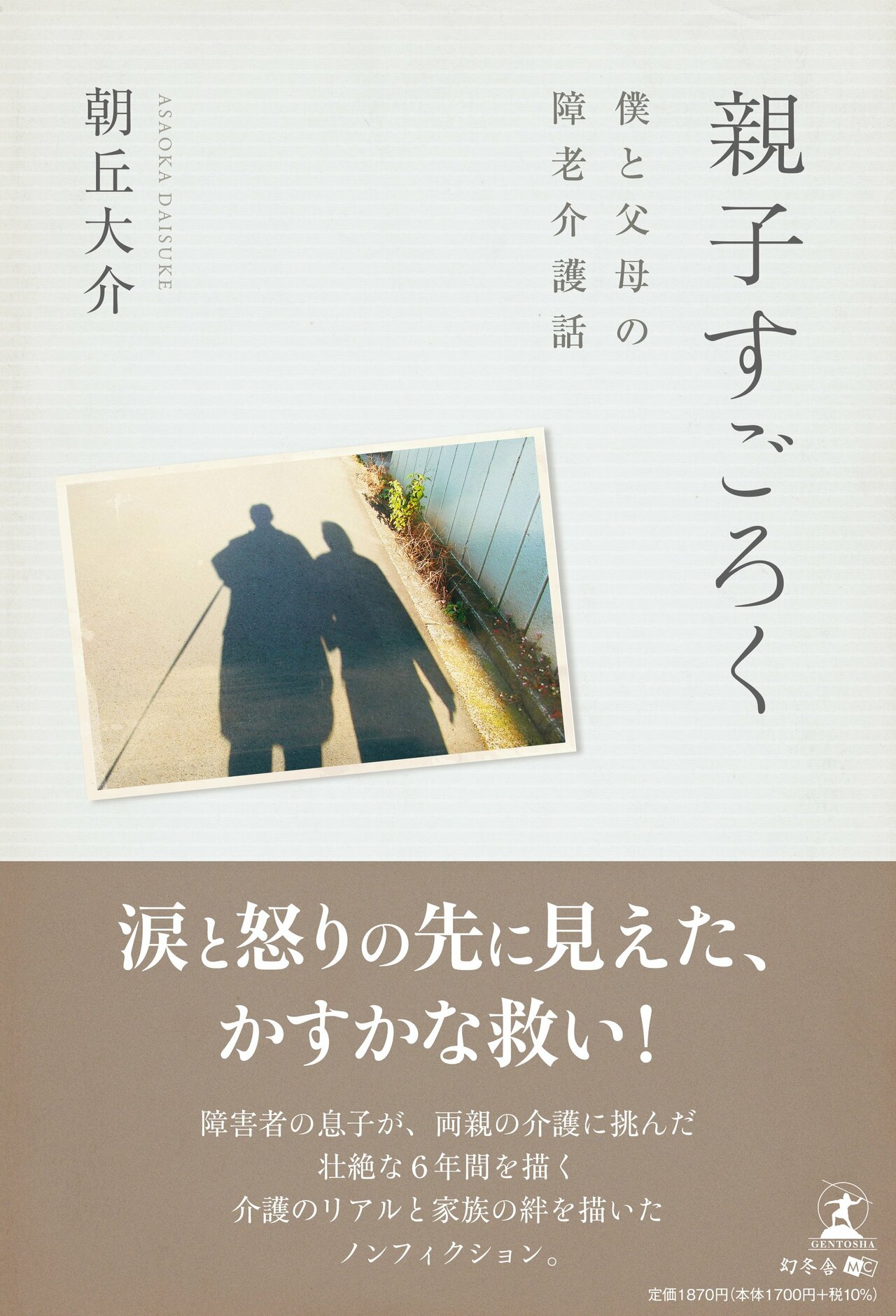父親のいるシアトルの病院から声が掛かっていたが、育った日本に残った。コミックやアニメといった、日本のオタク文化に熱を上げていたせいだ。
この病院にも、オタクっ娘の女医がひとりいることは聞いていた。
小林香澄という、うさぎ顔の皮膚科医だ。
仲良くなりたくて、半年前に駅前の居酒屋であった病院スタッフの飲み会に出席したことがある。
宴会が盛り上がる座敷のすみっこで、ぽつんと冷やっこをつついている香澄に、シマモトはウイスキーのボトルを手にすり寄っていった。
「香澄先生、さっきから野菜ばかりで、お肉ぜんぜん食べてないじゃないですかあ」
「え。ええ……」
「だめですよ、ちゃんとパワーつけないと。何か注文しましょう。食べたいものありますか?」
「え。ええと……」
シマモトはメニューをひろげた。
「ほら、なんでもありますよ。串焼き……鶏の唐揚げ……サイコロステーキ……馬刺し」
メニューを手にする香澄の横顔は、キュートだった。
香澄はふむふむとうなずきながら、緊張をほぐすため、コップに注いだウイスキーを一気に飲みくだした。
「何がいいいですか?」
「……それじゃあ、馬刺しとトマトジュースを」
「お姉さん、馬刺し、それとトマトジュースも。サビ抜きでね」
バイト店員の女の子がくすりと笑った。
シマモトはメニューを置くと整った顔を香澄に向けた。
「どうしてみんなと話さないんですか?」
滅多に飲むことのないハードドリンクで緊張がほぐされ、いい気持ちになった香澄は、自分の考えを口にした。
「……かすみね、人に対してATフィールドを張っているの」
「ATフィールド?」
「そう。かすみ、エヴァンゲリオンのシンジくんと同じなの」
「エヴァはネットでちょびっと解説を読んだことがあるけれど……。要するにそれって“人に対して心のバリアーを張っている”っていうことだよね」
「そう。かすみね、よく人からヘンだって言われるの。それで自分をだすと人に笑われるから、いつもATフィールドを張って目立たないようにしているの」
「あはははっ」
シマモトが笑った。
「おれだってヘンですよ。てゆうか、うちの病院なんて変人の集まりだし。平気へーき。たとえば、あそこでエアギターを弾いている放射線技師の渋井さん。変わり者だから、みんなに“ゴッホ”って呼ばれているんですよ」
「そうなんですか」
「そうですよー。それでも、あの人なりにみんなとコミュニケーションをはかりながら、なんとかやっている。まあ、仲間なんだから、お互いの弱点をフォローし合いながら、楽しく仕事していけばいいんじゃないですかあ」
「ふふっ。“人類補完計画”ですね」
「わけのわからんことを」