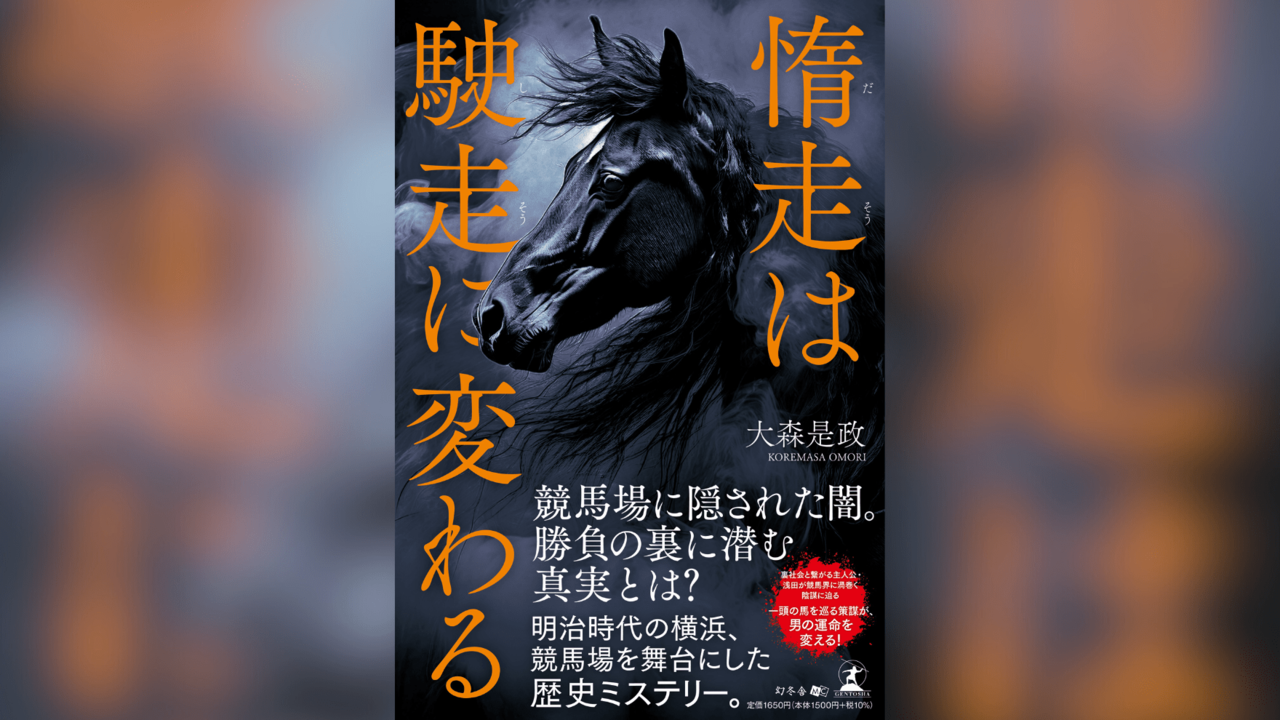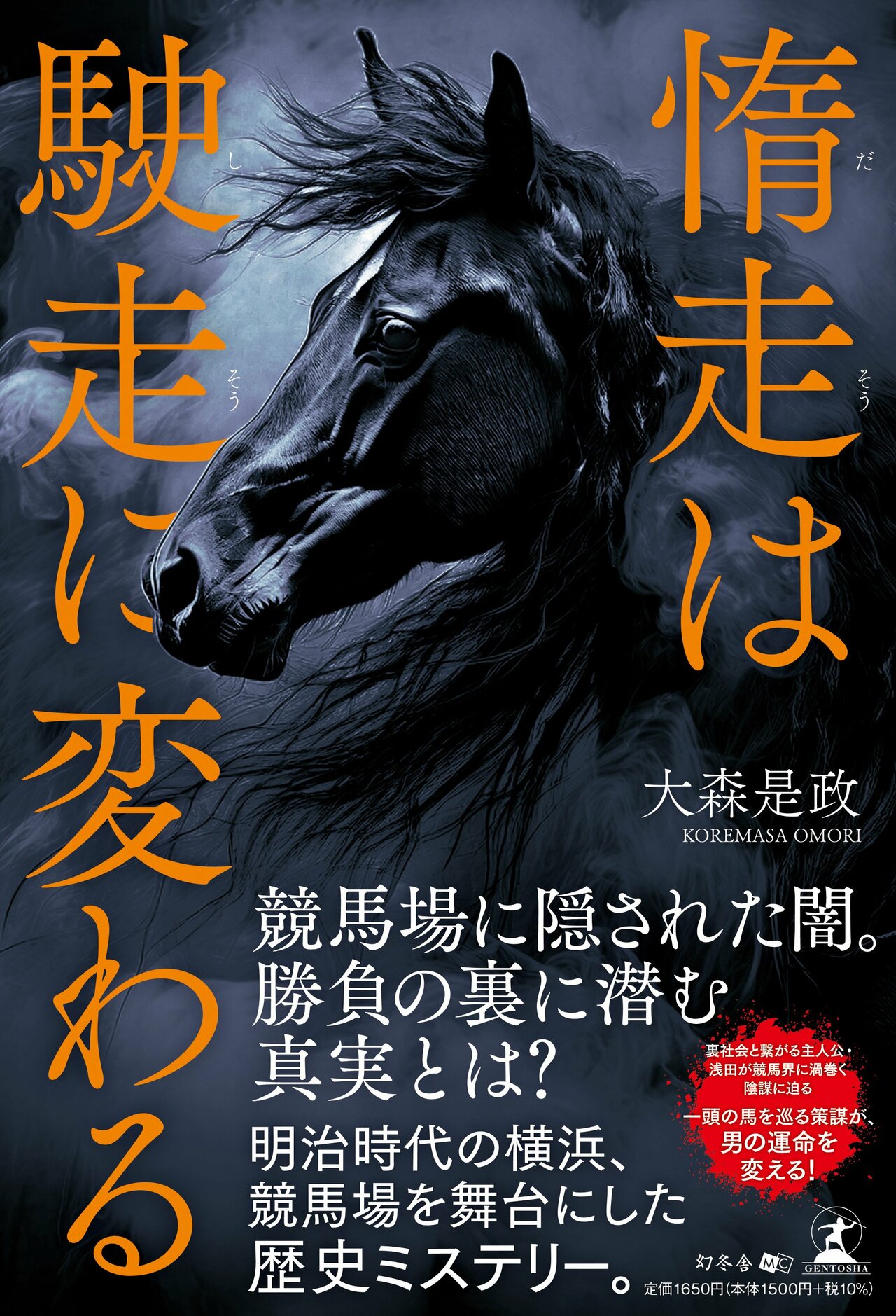【前回の記事を読む】横浜貿易を一時止めた根岸競馬場の熱狂――慶応年間の創設から明治時代の皇族・政財界人を魅了した馬かけ文化とは
惰走は駛走に変わる
初日の最終競争である第九競走は、婦人財嚢(ざいのう)競走というものだった。来場している婦人らからの寄付を募って、賞金に上乗せするという趣旨の競争である。競馬会の会員や招待客の婦人は、入場料を免除されている。そのためか奮発してくれるご婦人が多いとの話で、賞金総額は桁違いのものとなることも予想される。
「兄さん、馬券は買えてるのかい?」
焦茶色の着流しを身に着けて、同じような色の中折れ帽を目深に被り、隙間からは栗色の髪がはみ出している。その上に普通の日本人よりも頭ひとつ背の高い、浅田譲治である。
日本かぶれの外国人と思われることが多いのか、場所がどのようなところであろうとも、他人から話しかけられることはない。浅田は声が聞こえてきた方に視線を向けた。すると、六十歳ぐらいの男性が立っていた。洋装で紺色のフロックコートを身に着けている。
目を合わせた際に、青白い顔と青みがかった灰色の瞳が見えたのか「英語で聞くべきだったかな?」と男は聞いてきた。
「日本語で大丈夫だ」
「それならよかった。いやね、何度か馬券売場の近くまで来ているのを見かけたけど、買わなかったようだからさ、買い方がわからないのかと思って」
一方的に話しかけてきて、作法や流儀を教えようとする。賭場客の中にはこうした手合が少なからずいる。親切心からのようでもあるが、聞いているうちに、裏に見え隠れしているのが自尊心であると気づかされることもまた、多い。
元より馬券を買うのが目的で足を運んだわけではない。適当にあしらうことは簡単だが、競馬場を訪れるのが初めてであるのは間違いなく、少し話を聞いてみることにした。
「いや、わからないわけではないんだが、いざ、買う段になると迷ってしまってね。お父さんなら、次の競争はどの馬を買う?」
「いいときに聞いてくるな。次の競争には自信があるんだ。断然、買うべきなのは七番のダンジュウロウだ」
「強いのか?」
「既に旬を過ぎてはいるが、結果を残してきた馬だし、なによりも、騎手がいい」
「騎手? 騎手の力がそこまで影響するものなのか?」
「普通は馬の能力で買うべきだろうが、あいつ、滝本市蔵は別格なんだ。伊原孝善のお抱え騎手でね」
古くから続く旧家、伊原家の当主である。肩書は伊原物産の社長のはずだった。
「去年までは上野の弁天島競馬に出場していて、イチという通り名で呼ばれていた。あいつを知らない客はもぐりってことになるだろうな。
『へぇ』と言わせる乗り方もできるが、『ほう』と思わせる乗り方もできる。そういう騎手なんだ。これについては、うまく伝わるかどうかの自信はないんだがね」