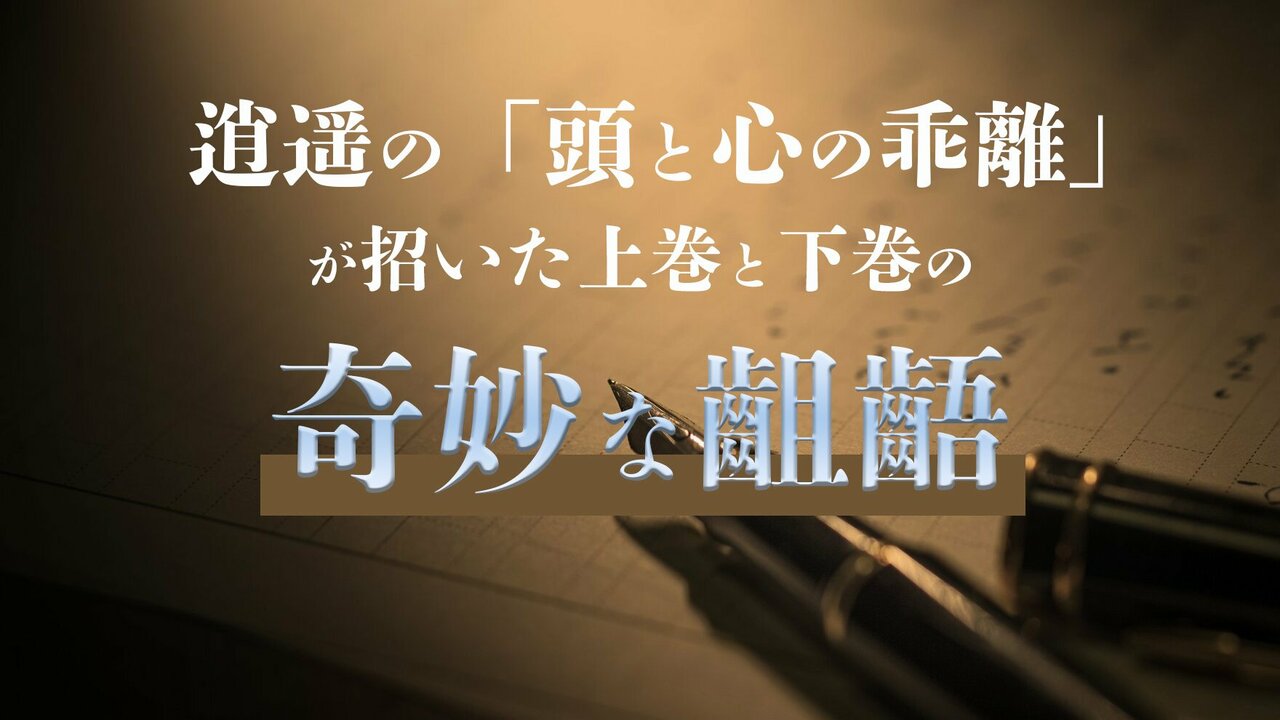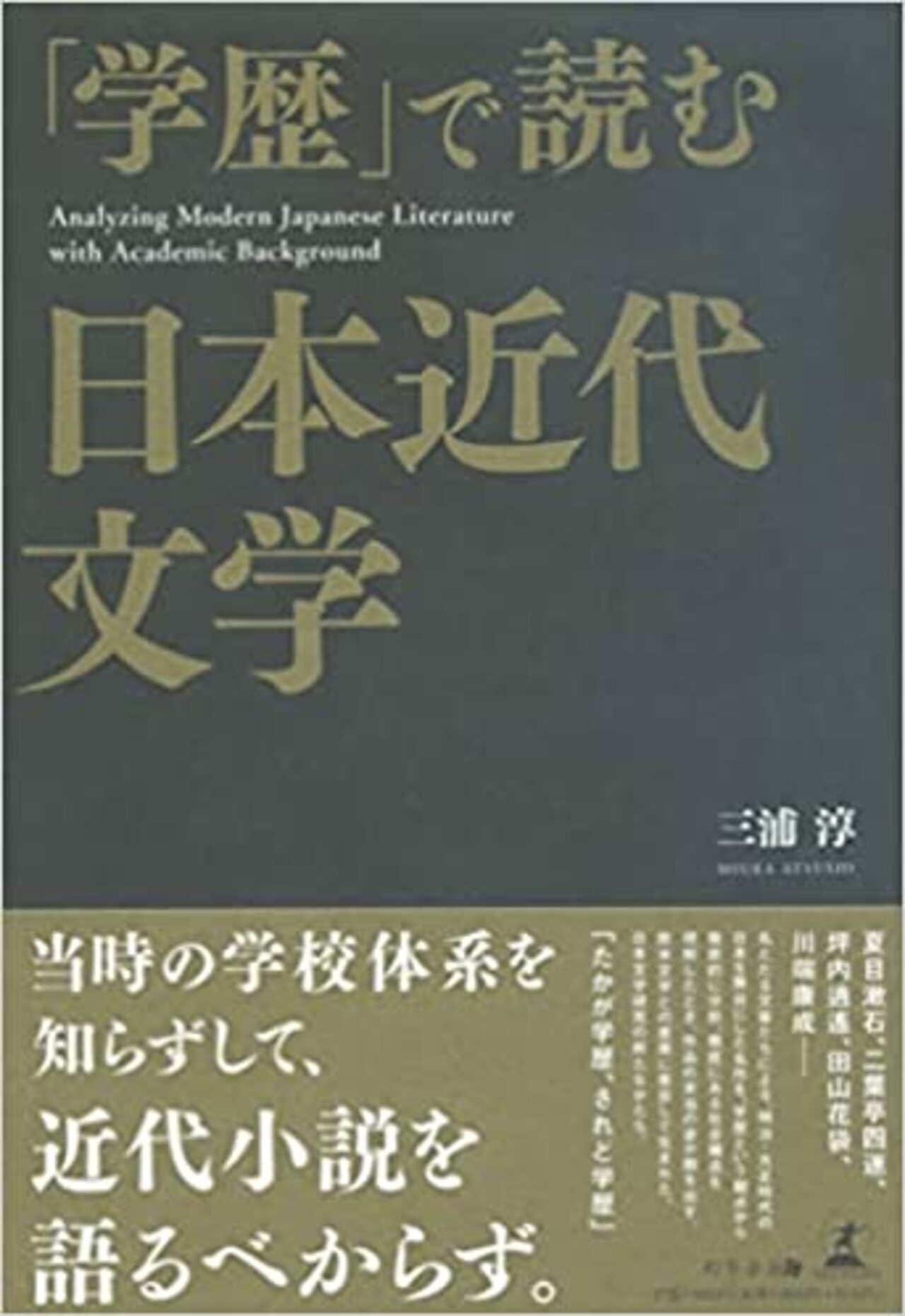【前回の記事を読む】逍遙の小説理論はダーウィンの影響?進化論が文学に与えたものとは
第一章 日本近代文学の出発点に存在した学校と学歴――東京大学卒の坪内逍遙と東京外国語学校中退の二葉亭四迷
第一節 坪内逍遙
■『小説神髄』の特徴(その二、下巻)
さて、しかし『小説神髄』も「下巻」になると、様相は一変します。「上巻」は今の読者が読んでも、言葉の古さを別にすれば或る程度うなずける内容なのですが、「下巻」はそうではありません。「下巻」は小説の実作にあたっての細かな技法や注意点を述べているのですが、そこに出されている実例の多くは江戸期やそれ以前の日本文学から取られているからです。「上巻」ではヨーロッパの近代小説に見習えと言っていたのと明らかに矛盾しています。
ではなぜそうなったのでしょうか。逍遙は子供の頃から馬琴など江戸期の文学に親しんでいました。彼が心躍らせながら読んだ小説とは、「上巻」が否定したローマンスだったのです。しかし彼は東京大学で英国人の教員から西洋文学の理論を教わり、日本の江戸期の小説はローマンスにとどまっておりノベルになっていないから遅れているのだ、と考えるようになります。
しかしそれは頭で理解した文学観でした。彼の親しんだ、つまり心で理解した作品とは、あくまで江戸期の小説だったのです。こうした頭と心の乖離が、「上巻」と「下巻」の奇妙な齟齬を招来したように思えるのです。
そうは言っても、ローマンスでもノベルでも人物や風景の描写などには共通部分もあるのだから江戸の小説の技法にも使えるところがあるのでは、という意見も出るかも知れません。しかし実際に読んでみれば分かりますが、「下巻」の技法論はその後の日本近代文学の展開にとってはほとんど役に立たない代物でした。
例えば「文体論」での「雅文体」では、江戸期の滑稽物と『源氏物語』を例にしながら分析を進めているのですが、文体はもちろん、描写の方向性においても、さらに読者に想定される知識においても、その後の日本近代文学はまったく異なる道を歩むことになったのであり、そうした(漱石や藤村や芥川などの)作品に親しんだ人間からすれば、この「下巻」には古色蒼然という形容を付けざるを得ないのです。下巻においては、逍遙は新しい革袋に古い酒を入れたと言うしかありません。