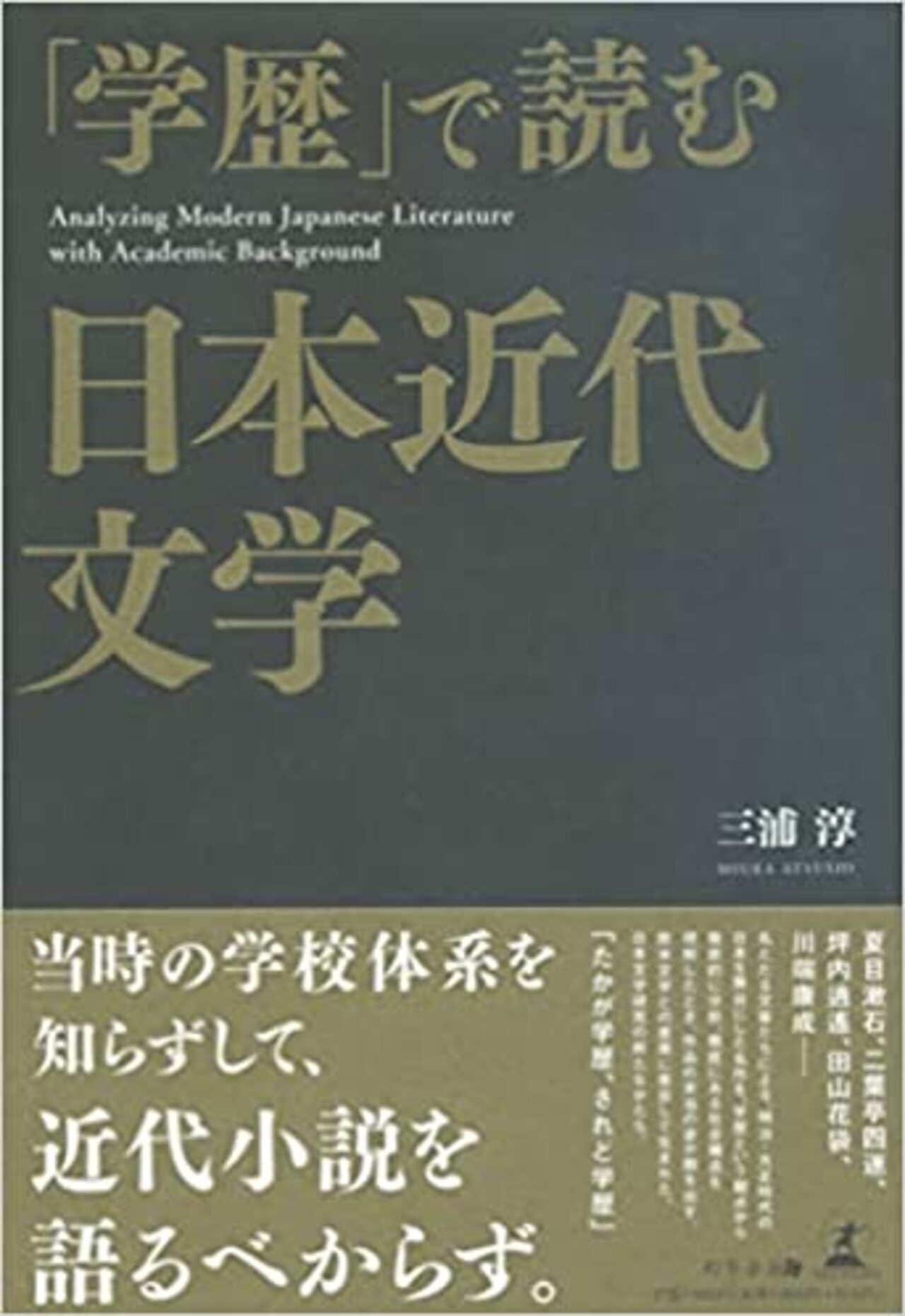【前回の記事を読む】逍遥の「頭と心の乖離」が招いた上巻と下巻の奇妙な齟齬
第一章 日本近代文学の出発点に存在した学校と学歴――東京大学卒の坪内逍遙と東京外国語学校中退の二葉亭四迷
第一節 坪内逍遙
■『当世書生気質』の限界
実際、逍遙は『小説神髄』の中でも作中人物の描写について、「従来の教育と其営業の性質によりて其人物の性はさらなり其感情の作用にも何等の差違を生ずるかと、いと細密にさぐり写して、外面に見えざる衷情をあらわに外面に見えしむべし」と述べています。(「上巻」の「小説の主眼」)
つまり、人間は受けた教育やそれまでの体験によって性格はもとより感じ方も異なるものであるから、その点を詳細に描写して、人間の心理や葛藤を読者に理解できるようにするべきだ、と言っているのです。
ここでの「教育」は必ずしも学校教育のことだけではありませんが、近代においては学校教育が誰にとっても重きをなすようになったという歴史的経緯を踏まえるなら、日本初の近代小説を目指して書かれたこの作品で学生を対象に選んだことは当然だったと言えるでしょう。
小説の冒頭近くには次のような文章があります。江戸から名を改めた東京においては、
大都会とて四方より、入りこむ人もさまざまなる、中にも別て数多きは、人力車夫と学生なり。おのおのその数六万とは、七年以前の推測計算方。今はそれにも越えたるべし。
要するに東京には学生が非常に多く、七年以上前の段階で六万と言われたから、今はもっと増えているはずだ、というわけです。もっともこの後で、本当に真面目に勉強している人間はごくわずかだから、日本が学者だらけになる心配は当分なさそうだが国家のためには損失だ、と付け加えてもいます。
たしかに上京した若者は必ずしも勉学に励むわけではなく、都会の遊興にお金と精力を使い、当初の高邁な志を忘れてしまう場合も多かったことでしょう。またこの頃には勉学の計画も立てずに何はともあれ上京すれば、と考える若者が少なからず存在したことも事実です。(この点については後で二葉亭四迷の『平凡』を論じる際に触れます。)
けれども、この小説を読んでいくと、登場する書生たちは遊び呆けているわけではなく、近代的な知識を一応身につけている様子が会話に西洋人の名や英書のタイトルや英語の概念が出てくることから分かるのです。その意味ではタイトルの『当世書生気質』は羊頭狗肉とは言えません。