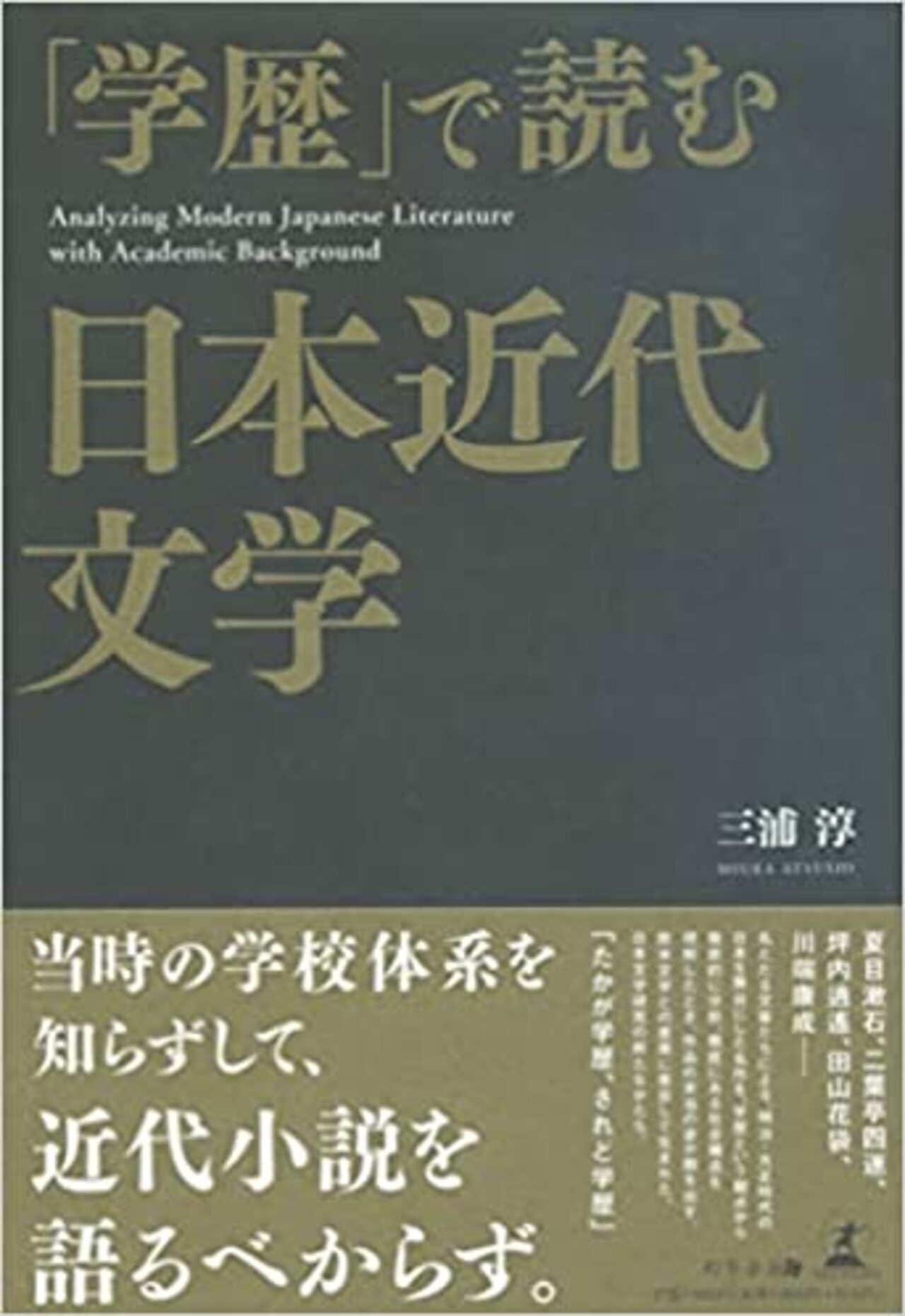しかし問題は、そうした知識があくまで表層的で、文字どおりの風俗にとどまっており、自分の生き方や抱えている悩みや将来の進路と結びついていないという点なのです。
例えば第二回では「ビイトン氏の、『普通学識字典』」なる書物に言及がなされますが、「実にこれは有用ぢゃ。君これから我輩にも折々引かしたまえ。歴史を読んだり、史論を草する時には、これが頗る益をなすぞウ」という評言がなされるにとどまります。
たしかに学校で学ぶ際に手助けとなる書物を紹介し合うのも学生の仕事のうちでしょうが、あくまで学術書を理解するのに役立つ、レポートをまとめる際に頼りになるといったレベルでの話に留まるのであり、それが自分の人生や日本の状況とどう交わるのかといった話になることはありません。
もっとも、あくまで表層的な風俗小説だと割り切って読むなら、当時の東京の学生の風俗はそれなりに描かれているとも言えます。例えば同じく第二回では守山という学生について以下のような会話が交わされます。
「守山君はどうしちょるかネ。」
「守山は相替らず、書物と首ッ引サ。今日も我輩が、浅草まで遊歩せんか、というたが、翻訳物を草しはじめたから、といって、更に出ない。而してその為すところを見れば、学校へ通うのと、東光学館へ行のと、折々温泉に浴するのみサ。」
「東光学館というは。」
「君はまだ知らんか。法律家が立てた法学校ぢゃ。守山君も余暇に教授しちょるという事ぢゃ。」
この時代、西洋の書物には未邦訳のものが多く、また外国語に堪能な人間も少なかったので、学生の翻訳でも出版することが可能だったのです。翻訳で金を稼ぐ話題は第十二回にも出てきます。
また守山という学生は本来在籍している学校に通う以外に、別の(私立)法学校で教鞭をとっていると言われています。
『当世書生気質』の発表は明治一八年半ばから翌年初めにかけて、時代設定は(後編・第十一回の前に挿入された断り書きによれば)明治一四、五年とされていますが、その明治一四年、のちに明治大学となる明治法律学校が、そして明治一八年には中央大学の前身である英吉利法律学校が設立されました。
これらの学校については後で詳述しますが、専任の教員をほとんど持たず、官立学校教員や役人、或いは東大生がアルバイトで教えている場合が多かったのです。漱石は帝大生時代から東京専門学校(のちの早大)で教えていました。『当世書生気質』の描写はそうした現実を写し出しているのです。