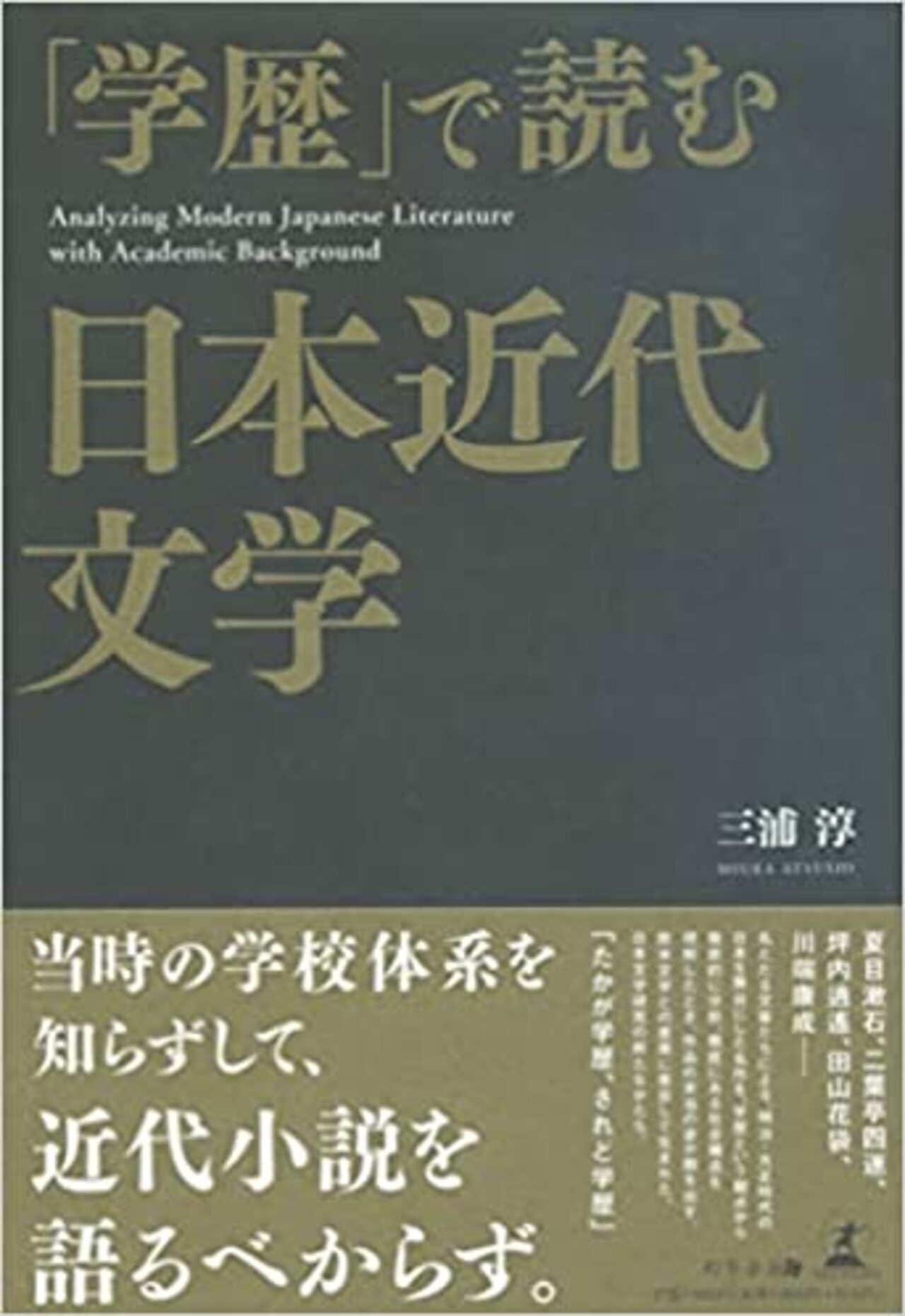それにしても、「上巻」が頭で理解した理論で作られているなら、「下巻」も同じであってよかったはずです。なぜそうならなかったのでしょうか。心で理解した江戸文学が逍遙の足かせになったのではと先に述べましたが、別の事情もあったと考えられます。
つまり当時の日本人にとって、西洋近代小説に登場する人物の行動や心理、街の様子や郊外の風景、或いは西洋の社会や制度や習慣などは、あまりに自分たちと隔たっていたということです。したがってそうしたものを前提に書かれた小説から実例をとっても、日本人には理解が困難だったのでしょう。
もしかしたら、逍遙自身にとってもそうだったのかも知れません。いかに東京大学で英国人などに薫陶を受けた優秀な人物とはいえ、当時の逍遙は二〇代半ばの青年でした。海外旅行が困難で西洋に関する情報量も比較にならないほど少なかった明治一〇年代にあって、小説の分類だけならまだしも、小説の具体的な文章や描写について西洋の小説を例にとっていたら、和食しか知らない日本人がいきなり洋食を出されるようなもので、味わうどころか、これが食物かと疑問を覚えるだけに終わった可能性もあるでしょう。
いずれにせよ、『小説神髄』における「上巻」と「下巻」の乖離は、そのまま、逍遙が近代的な小説として書き上げたはずの『当世書生気質』の質につながっていったのです。つまり、「上巻」の理論にのっとって書いたはずの小説は、実際には江戸期の文学とさほど違わないものにとどまったのでした。次に、その『当世書生気質』について検討しましょう。
■『当世書生気質』の限界
『小説神髄』で近代小説の理論を提供した逍遙が、それをもとにして実際に書いた小説、と言うより、そうなるはずだった作品が『当世書生気質』です。明治一八年(一八八五年)六月から翌年一月にかけて十七冊の分冊形式で刊行されました。
先に述べたように、出版は『小説神髄』より少し前でしたが、実際の執筆順は逆だったと考えられています。なお「書生」とは、故郷を離れて学生生活を送るために他家に寄宿している人間を言います。当時は単身者用のアパートなどはほとんどなかったからです。
日本における最初の近代小説を目指して書かれたこの作品が「書生」を描いているのは、或る意味必然だったと言えます。近代小説とは近代人の風俗や懊悩を描くものであり、明治維新によって近代化のスタートを切ってまもない日本では、近代人の代表とは学生に他ならなかったからです。
西洋から近代的な知識や文化を輸入する最先端にいたのが学生である以上、近代的な小説を生み出そうとするなら学生を主人公にするのが最も手っ取り早い方法だったのであり、同時に新時代を主導する若者たちの風俗を描けば読者の興味をも惹きつけることが可能になるからです。