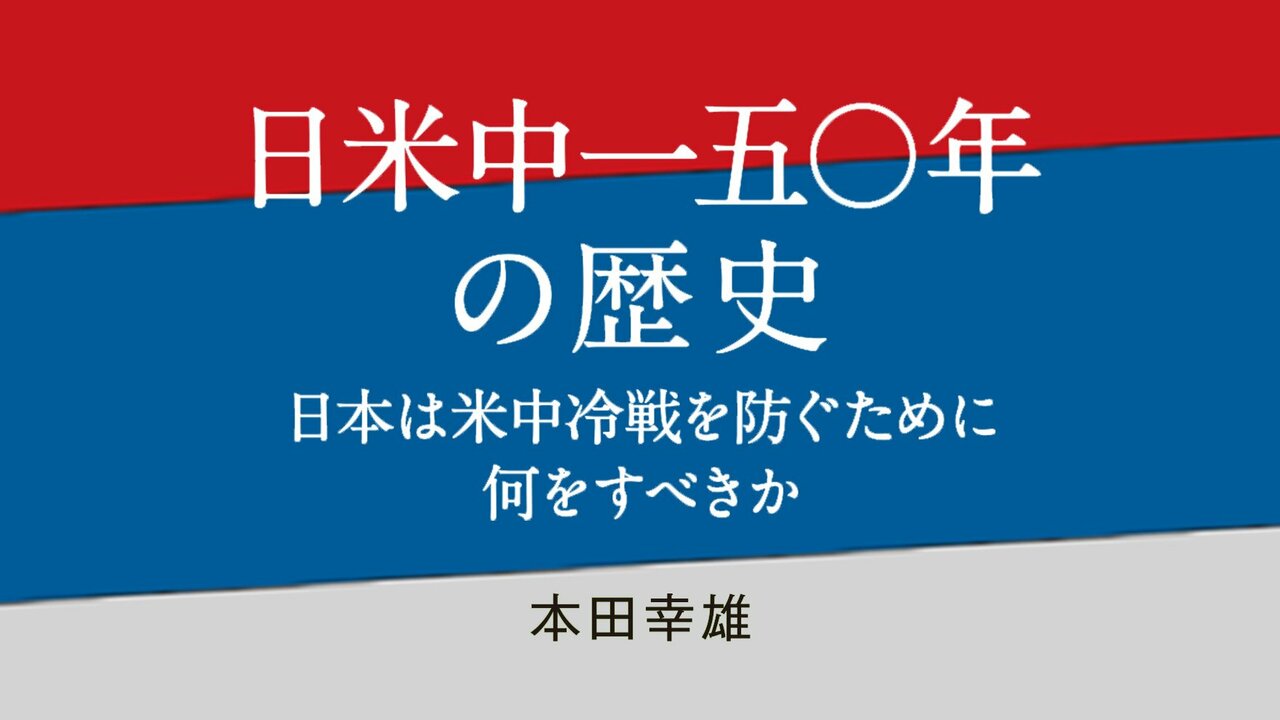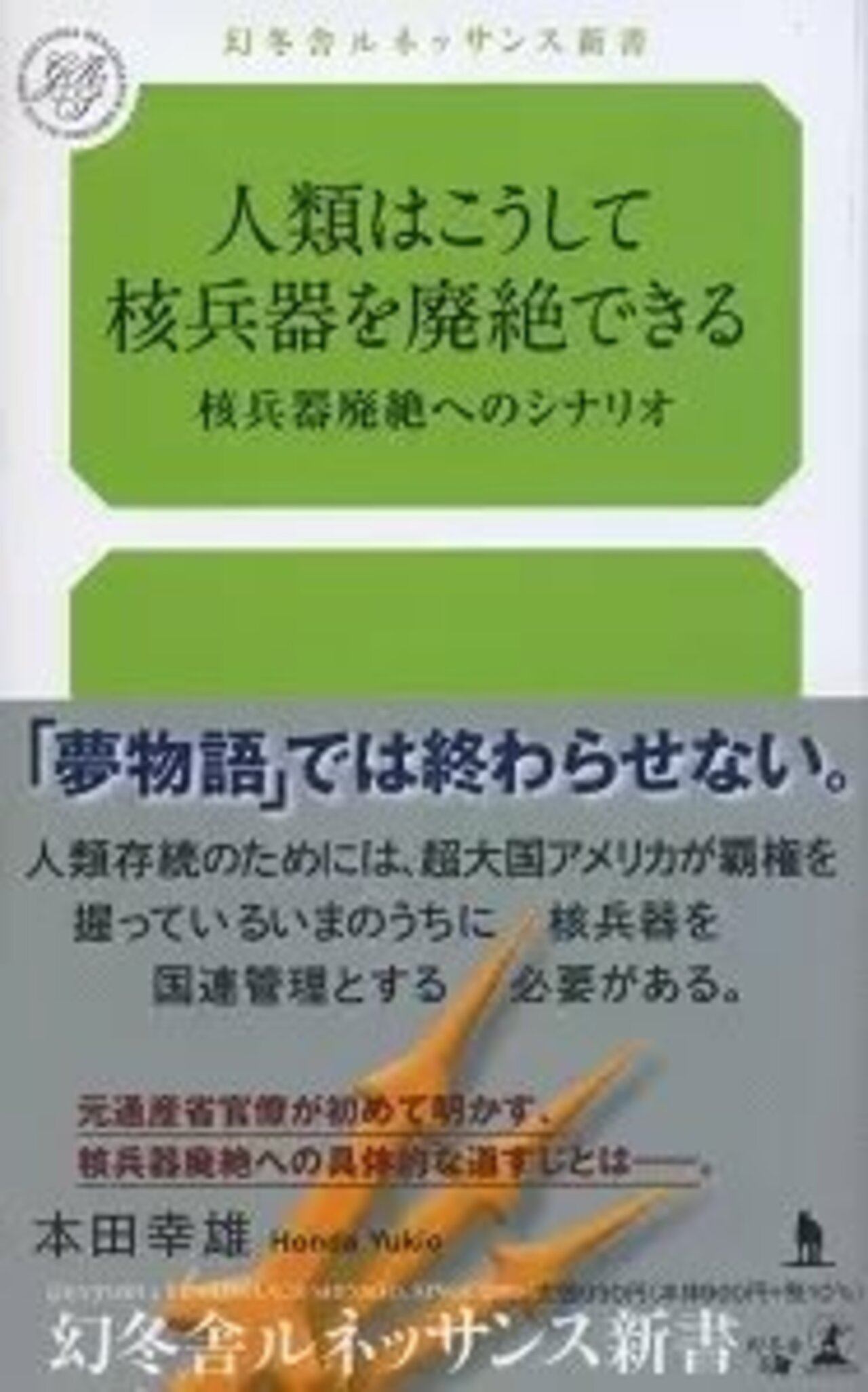第一章 第一次世界大戦までの日米中
《二》欧米列強の仲間入りした日本
ペリー来航と日本開国
一八世紀末から一九世紀初めにかけてのヨーロッパはフランス革命とナポレオン戦争で戦争に明け暮れていました。また、産業革命の最中で武器も量産されるようになってきて、ヨーロッパの戦争技術は格段と高まり、世界の他の地域を圧倒するようになってきていました。
一九世紀はヨーロッパが進出した南北アメリカも、アフリカも、アジアも戦争の時代で、ぼやぼやしていると、ヨーロッパ列強に難癖をつけられて、砲艦外交に訴えられました。戦争に敗北すると「城下の盟い」としての条約を結び、賠償金を払わされ、領土を割譲させられましたが、当時の世界はこれが当然と考えられていました。
アヘン戦争(一八四〇~四二年)に敗れた清国の南京条約がその典型でした。さらに厳しい場合には、条約さえ結ぶことなく、国家の主権の三権(立法・司法・行政)をすべて失い、植民地とされました。アフリカ、中東、インド、東南アジアへとヨーロッパ列強の植民地化の波はそこまでやってきていました。
次は日本の番でした。幕末開国については、徳川幕府が無能無策であった、ペリーの強力な軍事的圧力があった、したがって日米和親条約は極端に不平等な条約になったと、言われていますが、これは幕府を倒して成立した明治政権下で故意に強調されたことで、実際のところ、幕府は国際経験がないわりには(清朝の外交などと比べると)最大限の努力をしていたと考えられます。
一八五三年七月八日、浦賀沖に四隻のペリー艦隊が現れたとき、幕府はペリー来航から六日目に久里浜の仮設応接場にペリー一行を上陸させ、アメリカ大統領国書を受理しました。ペリーは、来航の目的を簡単に述べただけで、大統領国書への即答を幕府には要求せず、わずか九日間で去っていきました。
一ヶ月以上の食料を有していなかったため、交渉が長引けば困ると考え、ペリーは早々に出直したので(あとでペリーの日記でわかったことです)、砲艦外交など考えてもいませんでした。ペリーは、離日以降、中国沿海の各港や琉球、小笠原などにいて、補給をはたし(アメリカへは帰っていません)、七ヶ月後の一八五四年二月に二度目の来日をしました。