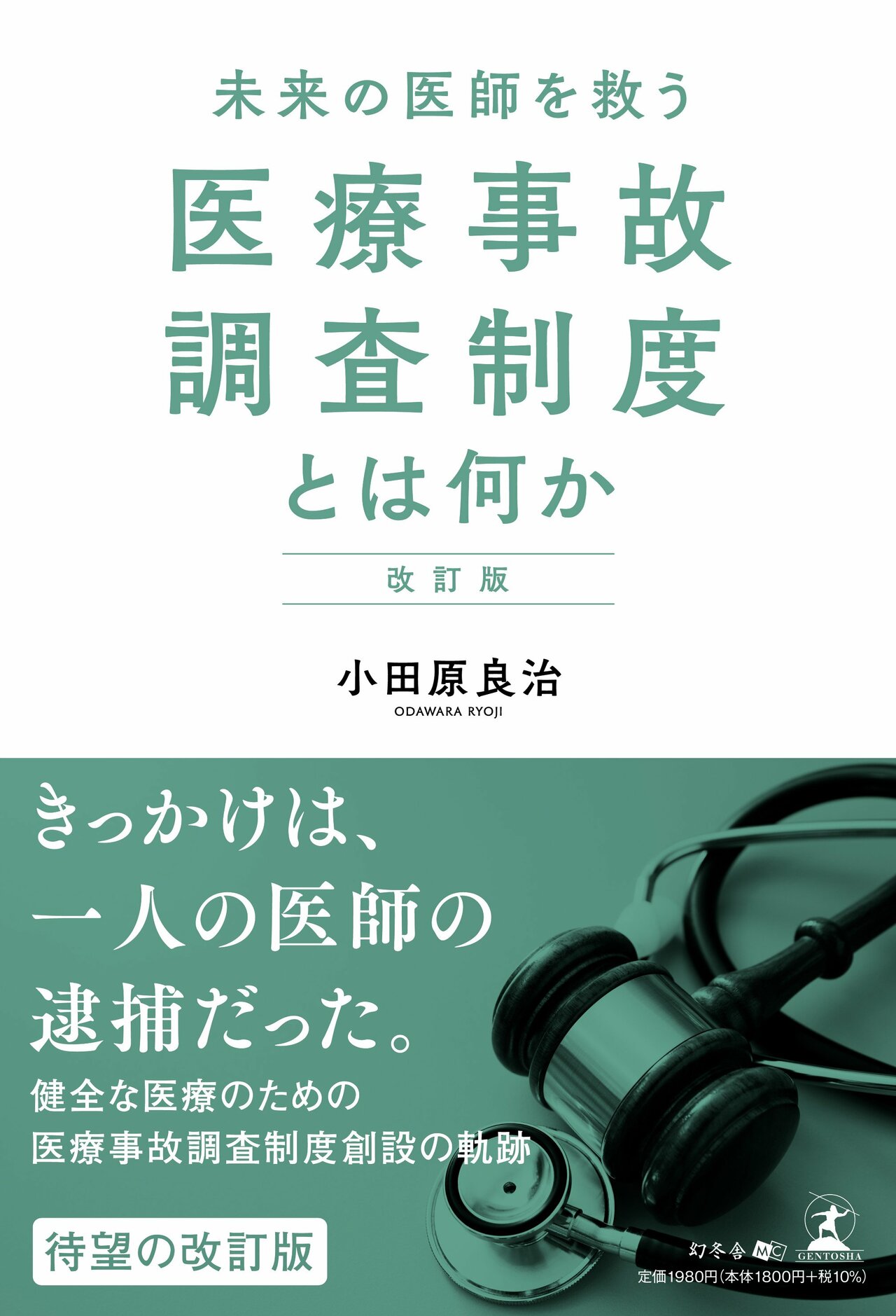第6点、原審においては、被告人は、初めて診察したときは、仮死状態にあると信じ、死亡しているとは思わなかったと陳述し、『死体』との認識はなかったと言うが、原判決では、被告人が死体を認識して、これを検案した事実を認定したと解すべきであり、上告理由とならない。
第7点、この部分は本判決の核心部分であり、漢字で意味の使い分けをしているため、『死屍』、『死體』、『屍體』など、原文中の文字を使用する。
(弁護人上告趣意書の形をとっているが、大審院が認定したものと考えられる)法律(警察犯処罰令第2条第10号)上、何人も自己の占有する場所内で『死屍』があることを知った者は、刑法第192条の検視を受けるべきものである。
従って、もし、法律上の『死屍』と認めるべきものがある場合は、近親者又は医師といえども警察官の指揮なく『屍體』に触ってはならない。
しかし、けが人、中毒者、病者等の場合は、近親縁者が介抱をし、医師の診察を受けるのは当然である。
故に、警察に届けなければならない『屍體』(死屍といえる屍體)とは、「だれが見ても、死亡していることが確実で、死後多少の時間を経過しており、ふつうの人が見ても、その死因に疑念がある場合」である。
このような場合こそ、先ず警察官に連絡し、その指揮の下に、医師の検案を受け、また、埋葬するためには、検視を受けるべきものである。
しかし、「医師が『屍體』を検案して死因に何ら疑わしいものがない場合は、医師は、何ら届出をする必要はない」。
もし、その死因につき、「他人の犯罪行為の関係があると認めること、即ち、『異常あり』と認めるときは、医師は、医師法施行規則第9条(現、医師法第21条)により24時間以内に警察に届出なければならない」故に、医師法施行規則第9条にいう『死體』は医師の診療を受けていない人の『死體』で、だれが見ても死因が疑わしい『屍體』のことである。
もし、第1審の考えに立てば、『死亡診断』の場面がなく、常に『屍體検案』となる。
しかし、原判決は何ら見解を示していないという。