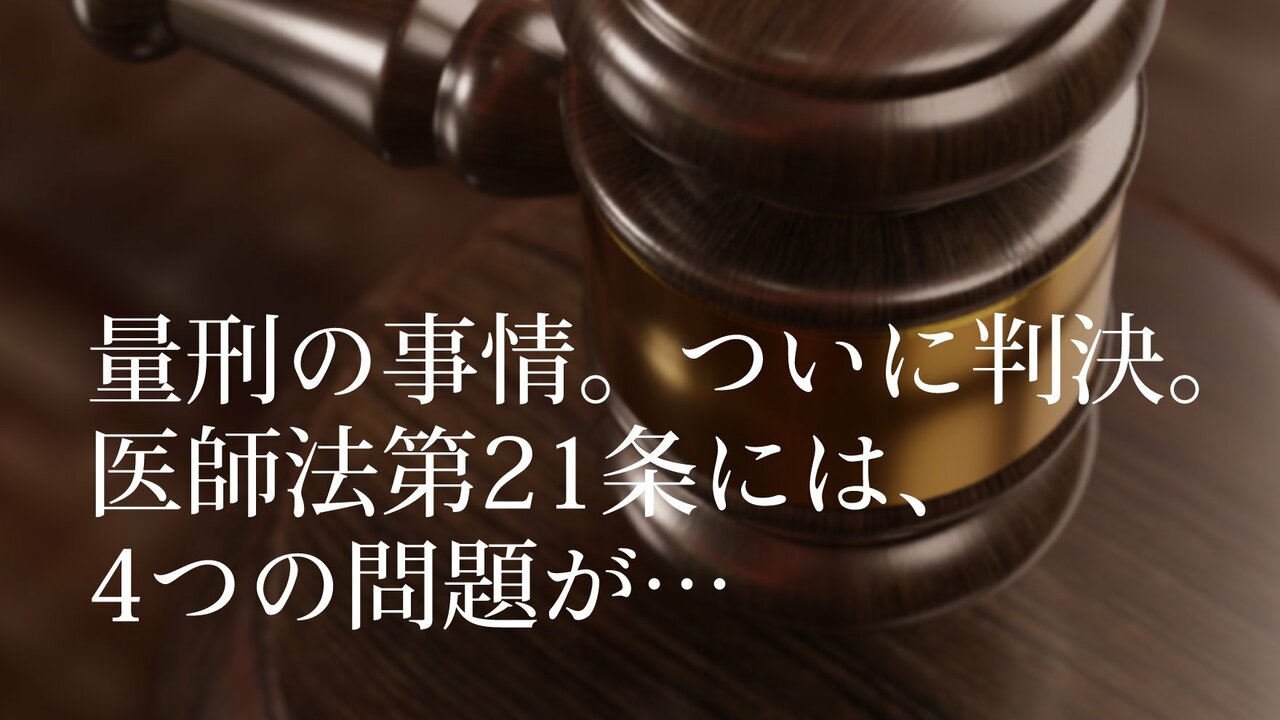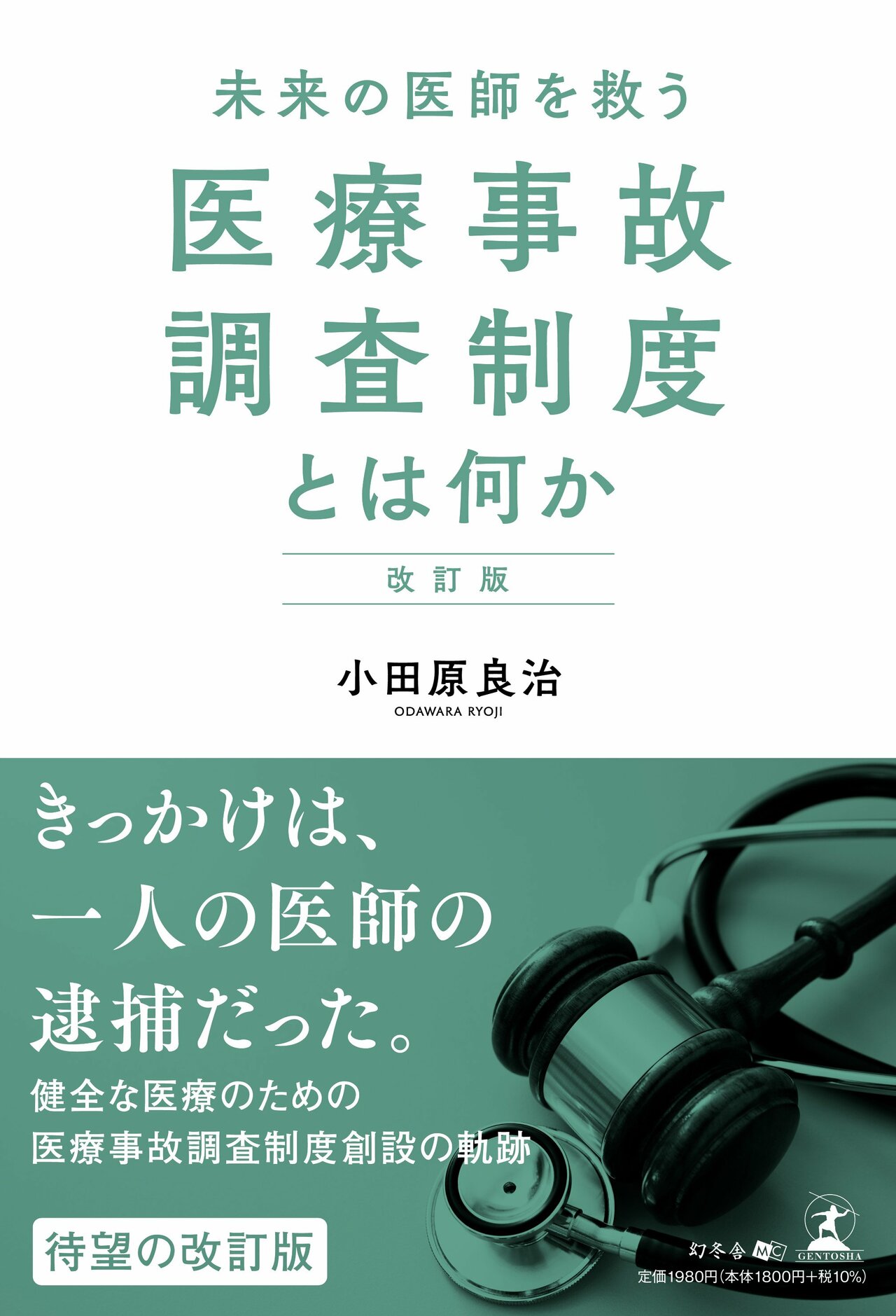量刑の事情
本件は、看護師の誤薬投与による入院患者の死亡事故の際に、患者の主治医らと共謀の上、医師法上定められた警察への届出をせず、また、その遺族から死亡診断書、死亡証明書の作成を依頼された際に、公務員である主治医らと共謀の上、死因として虚偽の記載をした死亡診断書、死亡証明書を作成、行使したという、医師法違反、虚偽有印公文書作成、同行使の事案である。
判示第一について、被告人は自己が院長を務める都立広尾病院において、看護師の誤薬投与により入院患者が死亡した疑いのある状況の発生に際し、病院幹部による対策会議を開いて、警察への届出等の対応を検討し、一度は警察に届け出る旨決めたのに、その後、東京都衛生局病院事業部と連絡をとり、病院事業部の職員が病院に来てからその話を聞いて決めることとするうち、医師法の規定する24時間が経過してしまったのであるが、
被告人は、患者の容態が急変したのは誤薬投与によるものであると看護師が勇気をもって告白し、医療過誤の蓋然性が極めて大きかったのに、医療過誤が表面化して、都立広尾病院が社会的非難を受けることをおそれていたこともあり、病院事業部とのやりとりをするうちに、結局方針を変えて、届出の指示をしなかったのであり、被告人が都立広尾病院の最高責任者であり、見識をもって対処すべきであったことなどにかんがみれば、厳しく非難されるべきである。
その後、患者の遺体の病理解剖の結果などから誤薬投与による事故死がほぼ疑いない状況となり、病死や自然死とは言えないことが明らかになってからも、誤薬投与による事故死であることは認められないとの立場に固執して、判示第二のとおり、死亡した患者の主治医から死亡診断書等の記載内容について相談を受けた際に、虚偽の記載をするよう指示しており、被告人ら都立広尾病院幹部により医療過誤を隠蔽しようとしたものであって、医療の専門知識を有する医師らから真実を隠蔽された遺族にとっては、その真実を知るには多大の困難を伴い、その心労が大きいものであることは推測に難くなく、病院や医療関係者に対する社会の信頼を失墜させたことなどにかんがみると、犯情は良くなく、その刑事責任を軽く見ることはできないというべきである。
しかしながら、患者の死亡について当初は警察に届け出る方針であったこと、これまで医師として社会に貢献して仕事をしてきたと見られること、前科前歴のないこと、その年齢など、被告人のために酌むべき諸事情を考慮すれば、主文掲記の刑に処し、懲役刑についてはその執行を猶予するのを相当とする。
よって、主文のとおり判決する。
医師法第21条にいう『検案』の意味するもの医師法第21条は、「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と規定している。この東京都立広尾病院事件裁判で争われたのは『異状』の意味と同時に『検案』の意味するものであった。この広尾病院事件以前に、診療関連死に医師法第21条が適用された例は見当たらない。それまで、医師が診療中の患者の死亡の場合発行されるのは死亡診断書であり、診療中の患者以外のものが死亡したとき、その死体を検分した場合に発行されるのが死体検案書であるとされ、死体検案書を発行される場合の死体の検分が『検案』とされて来た。